黒
-
 友禅染の桜振袖の背部分に染め分けられたやや写実的な桜の文様です
友禅染の桜振袖の背部分に染め分けられたやや写実的な桜の文様です -
 蒔絵の藤枝から垂れ下がる藤の花房を写実的にあらわした蒔絵の藤
蒔絵の藤枝から垂れ下がる藤の花房を写実的にあらわした蒔絵の藤 -
 蒔絵大鼓胴の牡丹蒔絵の大鼓胴に意匠をほどこした,牡丹の文様です
蒔絵大鼓胴の牡丹蒔絵の大鼓胴に意匠をほどこした,牡丹の文様です -
 螺鈿の朝顔櫃を覆いつくさんばかりに描かれた,蒔絵螺鈿の朝顔です
螺鈿の朝顔櫃を覆いつくさんばかりに描かれた,蒔絵螺鈿の朝顔です -
 唐織の夕顔色彩豊かな夕顔を,金糸の霞紋でまとめた構成です
唐織の夕顔色彩豊かな夕顔を,金糸の霞紋でまとめた構成です -
 螺鈿の秋草薄のしなやかな流線と,それに沿うように飛ぶ蜻蛉が印象的です
螺鈿の秋草薄のしなやかな流線と,それに沿うように飛ぶ蜻蛉が印象的です -
 蒔絵螺鈿の椿樹椿の花を随所に螺鈿で表わした椿樹の文様です
蒔絵螺鈿の椿樹椿の花を随所に螺鈿で表わした椿樹の文様です -
 唐草現代でもよく使用される,言わば唐草の代表的な文様です
唐草現代でもよく使用される,言わば唐草の代表的な文様です -
 雷文渦巻形が幾何学的に方形になった,代表的な雷文です
雷文渦巻形が幾何学的に方形になった,代表的な雷文です -
 夜着の橘夜着の背面全面に,力づよく大きな構図で描かれた橘の文様です
夜着の橘夜着の背面全面に,力づよく大きな構図で描かれた橘の文様です -
 蒔絵の波頭兎の耳を長く描かれる波頭とともに描かれた波頭文です
蒔絵の波頭兎の耳を長く描かれる波頭とともに描かれた波頭文です -
 雪輪雪の結晶に見られる美しい六角形の輪郭を描いた文様です
雪輪雪の結晶に見られる美しい六角形の輪郭を描いた文様です -
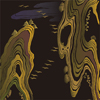 山水
山水 -
 硯箱の蔦硯箱上に,斬新な構成で描かれた蔦の文様です
硯箱の蔦硯箱上に,斬新な構成で描かれた蔦の文様です -
 花瓶の金魚花瓶に蒔絵で写実的に表現された金魚です
花瓶の金魚花瓶に蒔絵で写実的に表現された金魚です -
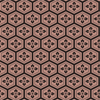 亀甲花菱亀甲文の中に花菱を入れて用いられた文様です
亀甲花菱亀甲文の中に花菱を入れて用いられた文様です -
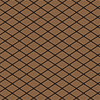 入子菱菱形の中にさらに菱形を入れて,入れ子にしたものです
入子菱菱形の中にさらに菱形を入れて,入れ子にしたものです -
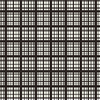 翁格子大きな格子の中に小さな格子を抱えた様を,翁と大勢の孫に見立てた格子です
翁格子大きな格子の中に小さな格子を抱えた様を,翁と大勢の孫に見立てた格子です -
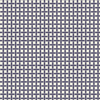 一崩しこれは割付文様の一種で,網代組とも言われています
一崩しこれは割付文様の一種で,網代組とも言われています -
 釘抜繋ぎ正方形の中央に小さく正方形を入れ釘抜きの座金を表わしています
釘抜繋ぎ正方形の中央に小さく正方形を入れ釘抜きの座金を表わしています -
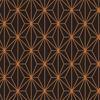 麻の葉こちらも,現代でもよく見かけることのできる文様です
麻の葉こちらも,現代でもよく見かけることのできる文様です -
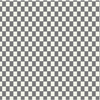 石畳(市松)別名「市松文様」です.石畳の細かいものは霰と呼ばれています
石畳(市松)別名「市松文様」です.石畳の細かいものは霰と呼ばれています -
 ふくさの宝尽くし若松とともに表わされた,ふくさに描かれた宝尽くしの文様です
ふくさの宝尽くし若松とともに表わされた,ふくさに描かれた宝尽くしの文様です
