赤
-
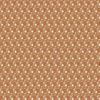 指貫の桜桜の花を立涌文様化した,舞楽装束の指貫の文様です.注:指貫(さしぬき)とは袴の一種のこと
指貫の桜桜の花を立涌文様化した,舞楽装束の指貫の文様です.注:指貫(さしぬき)とは袴の一種のこと -
 蒔絵の扉の牡丹江戸後期,絵画的な意匠が流行していた頃の牡丹立木文様です
蒔絵の扉の牡丹江戸後期,絵画的な意匠が流行していた頃の牡丹立木文様です -
 友禅染の杜若簡略化された流水と写実的な杜若を色使いで見事にまとめています
友禅染の杜若簡略化された流水と写実的な杜若を色使いで見事にまとめています -
 蓮池の蒔絵厨子の扉に描かれた,迫力ある蓮池と散蓮花の文様です
蓮池の蒔絵厨子の扉に描かれた,迫力ある蓮池と散蓮花の文様です -
 菊水菊の花束を用いた花のし文として表された文様です.
菊水菊の花束を用いた花のし文として表された文様です. -
 梅唐草中心円のまわりに5つの円で梅花を表す梅鉢の唐草文様です
梅唐草中心円のまわりに5つの円で梅花を表す梅鉢の唐草文様です -
 縫箔の椿地の鮮やかな朱色に,純白の椿の花が映える折枝文です
縫箔の椿地の鮮やかな朱色に,純白の椿の花が映える折枝文です -
 唐織の百合唐織にみられる,写実的に描かれた百合の文様です
唐織の百合唐織にみられる,写実的に描かれた百合の文様です -
 重箱の水仙重箱の蓋の表に表現された,水仙の花丸文です
重箱の水仙重箱の蓋の表に表現された,水仙の花丸文です -
 笹と若竹雲と組み合わせた,笹と若竹です.これは振袖に描かれたものです
笹と若竹雲と組み合わせた,笹と若竹です.これは振袖に描かれたものです -
 糸瓜自生風情の糸瓜を,肩衣に描いた文様です
糸瓜自生風情の糸瓜を,肩衣に描いた文様です -
 横雲霊芝雲が時代とともに簡略化された表現とも言われます
横雲霊芝雲が時代とともに簡略化された表現とも言われます -
 雪華文さまざまな種類の雪の結晶を花のように描いた文様です
雪華文さまざまな種類の雪の結晶を花のように描いた文様です -
 雁渡り鳥である雁が連なって飛ぶ姿は文様として好まれました
雁渡り鳥である雁が連なって飛ぶ姿は文様として好まれました -
 鯉水波濤に泳ぐ鯉を円にまとめた文様で,紋章としても見られます
鯉水波濤に泳ぐ鯉を円にまとめた文様で,紋章としても見られます -
 唐織の蝶静止して羽を直立にたてた蝶を文様では揚羽蝶と呼びます
唐織の蝶静止して羽を直立にたてた蝶を文様では揚羽蝶と呼びます -
 蝶丸円形に蝶をかたどった文様です.別名,「輪蝶」とも呼ばれます
蝶丸円形に蝶をかたどった文様です.別名,「輪蝶」とも呼ばれます -
 立涌の小紋立涌を小紋で表わしたものです
立涌の小紋立涌を小紋で表わしたものです -
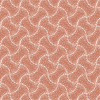 小紋
小紋
