黄
-
 肩衣の紫陽花肩衣(かたぎぬ:裃の上の部分)の背部分に大胆な構図で表現された,糊防染の紫陽花です.
肩衣の紫陽花肩衣(かたぎぬ:裃の上の部分)の背部分に大胆な構図で表現された,糊防染の紫陽花です. -
 日本画の紫陽花江戸時代に描かれた,写実を超えた見事な紫陽花の絵です
日本画の紫陽花江戸時代に描かれた,写実を超えた見事な紫陽花の絵です -
 唐織の秋草七草に含まれる萩と薄を,麻の葉文を地にした文様です
唐織の秋草七草に含まれる萩と薄を,麻の葉文を地にした文様です -
 三階松三段に重ねた松の枝葉の文様で,紋章として使用されています
三階松三段に重ねた松の枝葉の文様で,紋章として使用されています -
 桜橘立涌桜と橘を用いて立涌文にした,公家好みの京からかみです
桜橘立涌桜と橘を用いて立涌文にした,公家好みの京からかみです -
 団栗
団栗 -
 芒
芒 -
 唐草現代でもよく使用される,言わば唐草の代表的な文様です
唐草現代でもよく使用される,言わば唐草の代表的な文様です -
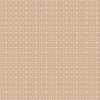 雷文渦巻形が幾何学的に方形になった,代表的な雷文です
雷文渦巻形が幾何学的に方形になった,代表的な雷文です -
 千鳥単純化された千鳥です.身近な鳥のためか,多くの文様が残ります
千鳥単純化された千鳥です.身近な鳥のためか,多くの文様が残ります -
 子持亀甲亀甲文の中に亀甲文を入れた,入れ子になっている文様です
子持亀甲亀甲文の中に亀甲文を入れた,入れ子になっている文様です -
 鮫青海波鮫小紋で青海波を表わしている文様です
鮫青海波鮫小紋で青海波を表わしている文様です -
 念じ麻の葉麻の葉の中心が捻じれたように表わされた麻の葉の文様です
念じ麻の葉麻の葉の中心が捻じれたように表わされた麻の葉の文様です -
 団扇散らし団扇を一面に散らした様子を文様にしたものです
団扇散らし団扇を一面に散らした様子を文様にしたものです -
 素襖の傘散らし傘を一面に散らした文様で,これは,素襖に描かれたものです
素襖の傘散らし傘を一面に散らした文様で,これは,素襖に描かれたものです -
 菊青海波菊の花を規則正しく並べ,青海波に見立てて創られた文様です
菊青海波菊の花を規則正しく並べ,青海波に見立てて創られた文様です -
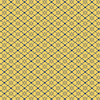 四花菱花菱を四つ集めて一つの菱にした文様です
四花菱花菱を四つ集めて一つの菱にした文様です -
 葡萄立涌この文様は,立涌の中に葡萄の葉と実が描かれたものです
葡萄立涌この文様は,立涌の中に葡萄の葉と実が描かれたものです -
 桧垣・網代檜などの薄板で組まれた垣根や羽目板を文様にしたものです
桧垣・網代檜などの薄板で組まれた垣根や羽目板を文様にしたものです -
 絣の縞部分的に染色した糸を縦横に織り,染め残った部分との差で表わされ,織りのものもあります
絣の縞部分的に染色した糸を縦横に織り,染め残った部分との差で表わされ,織りのものもあります
