指貫の桜
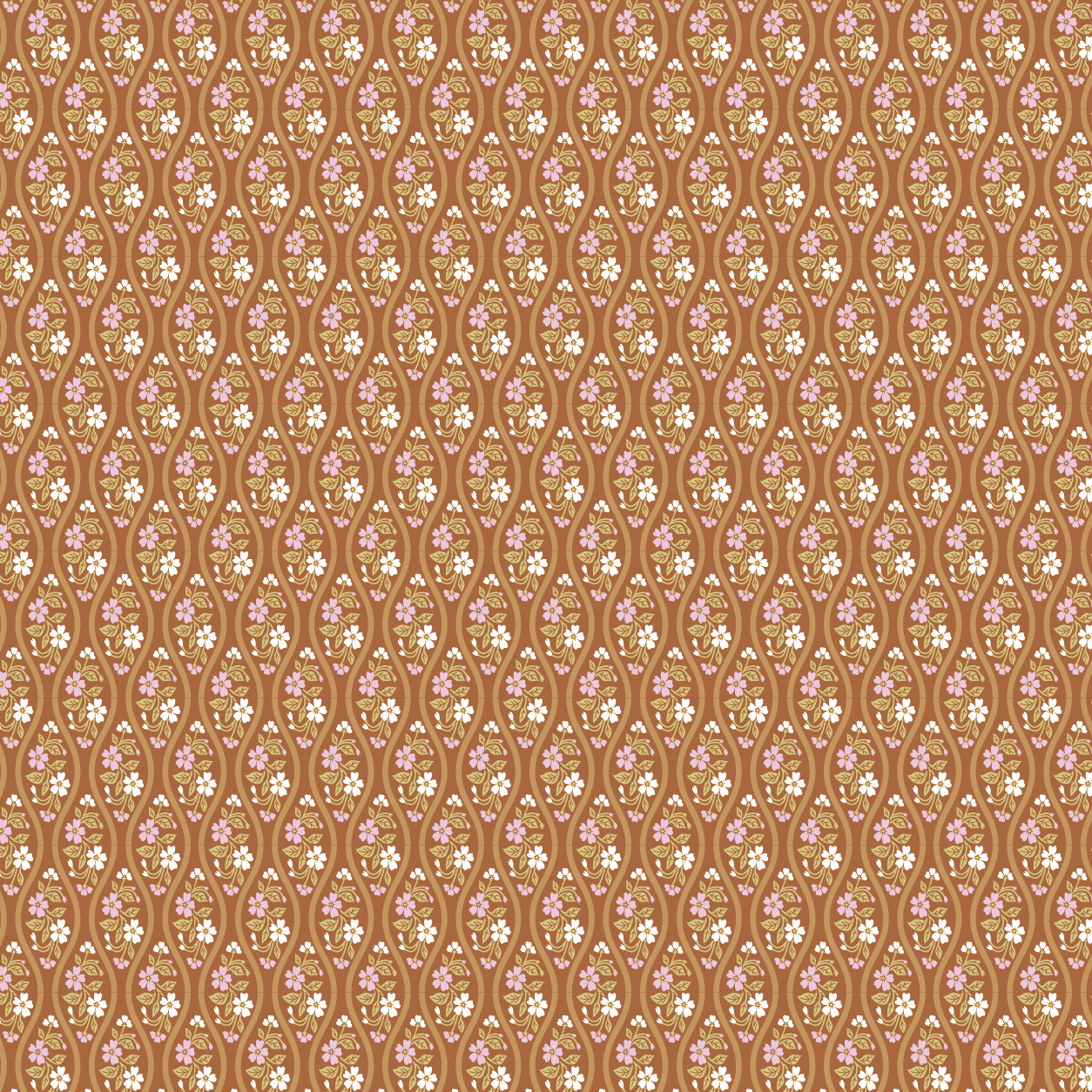
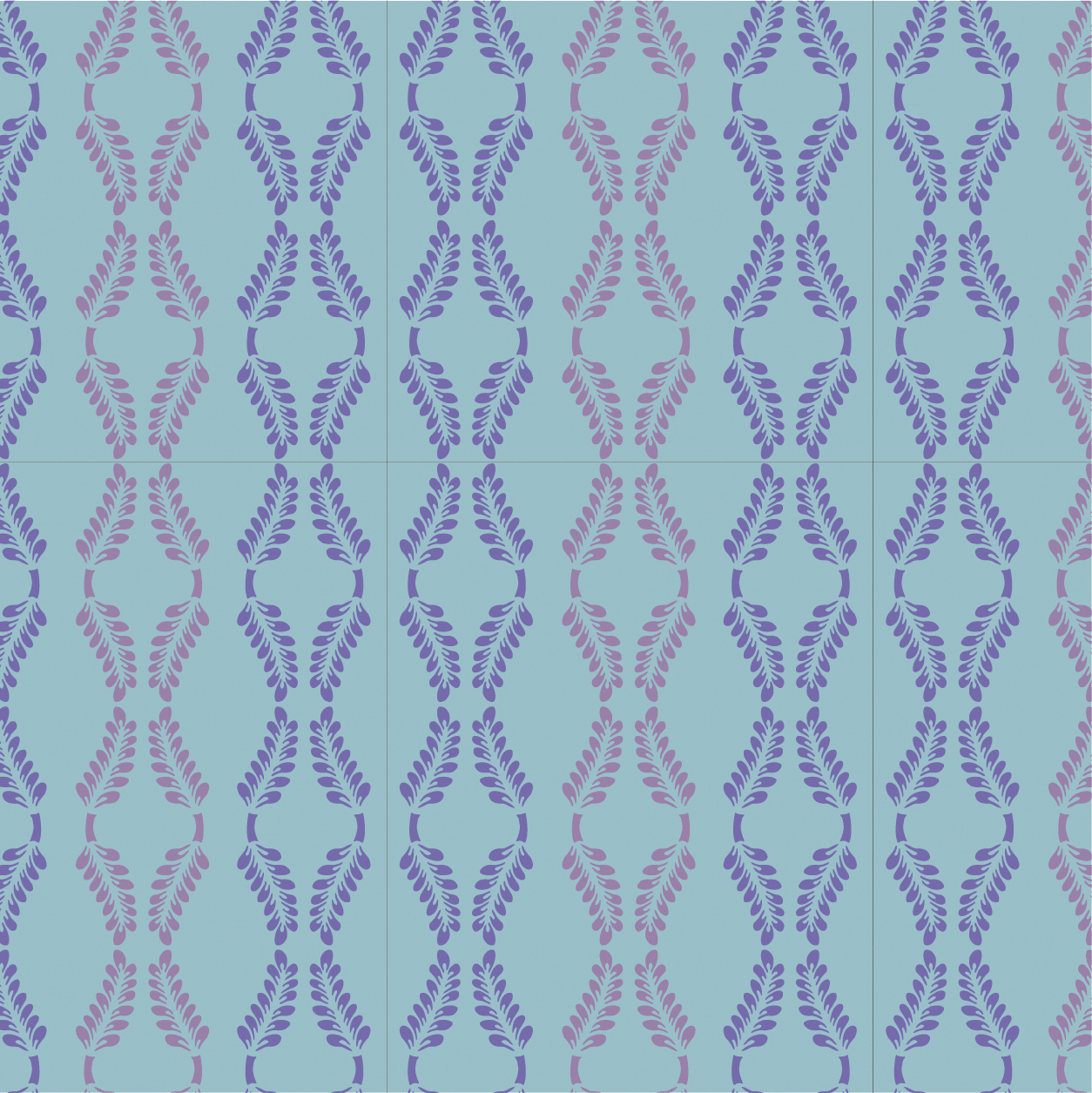


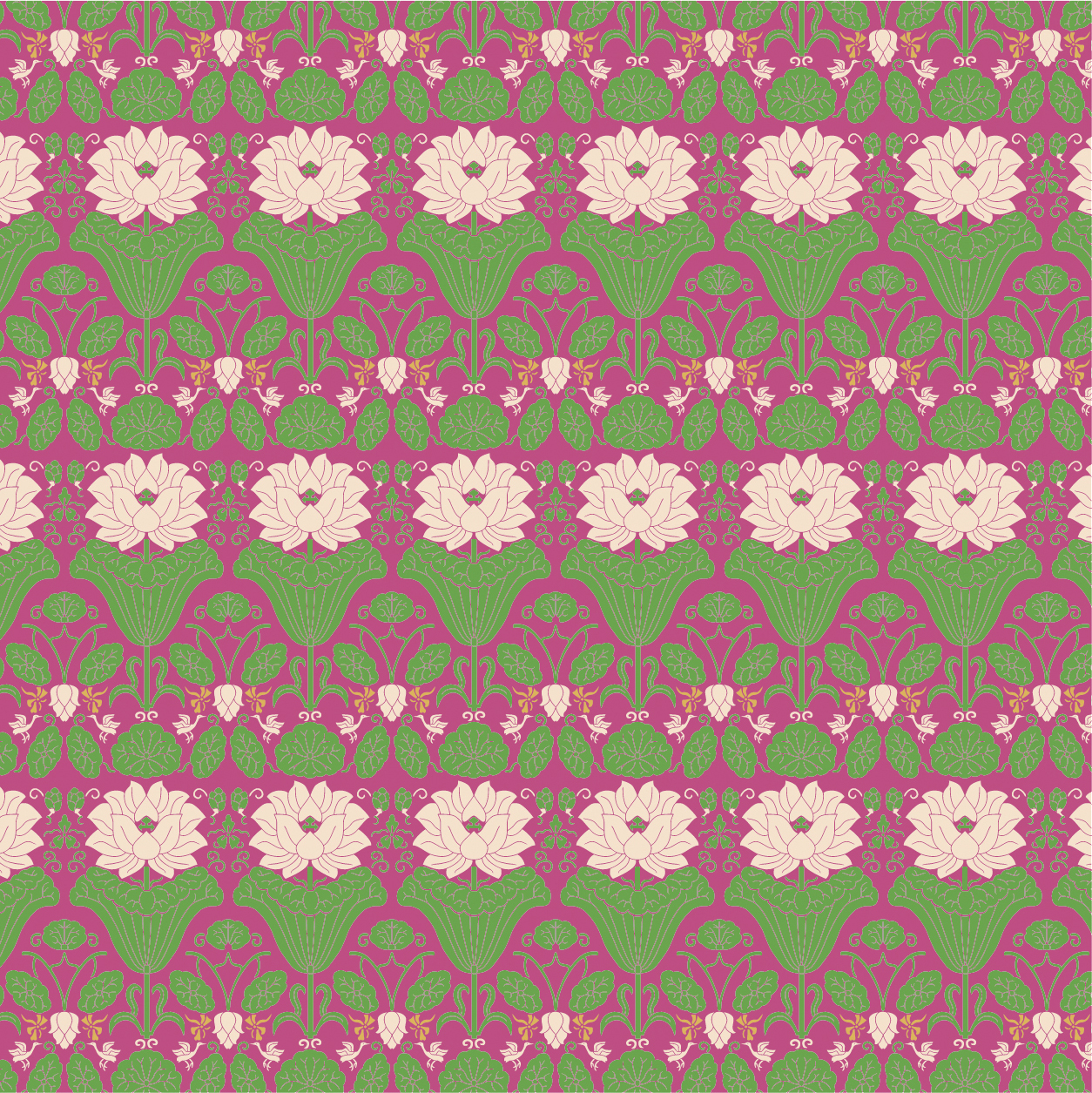




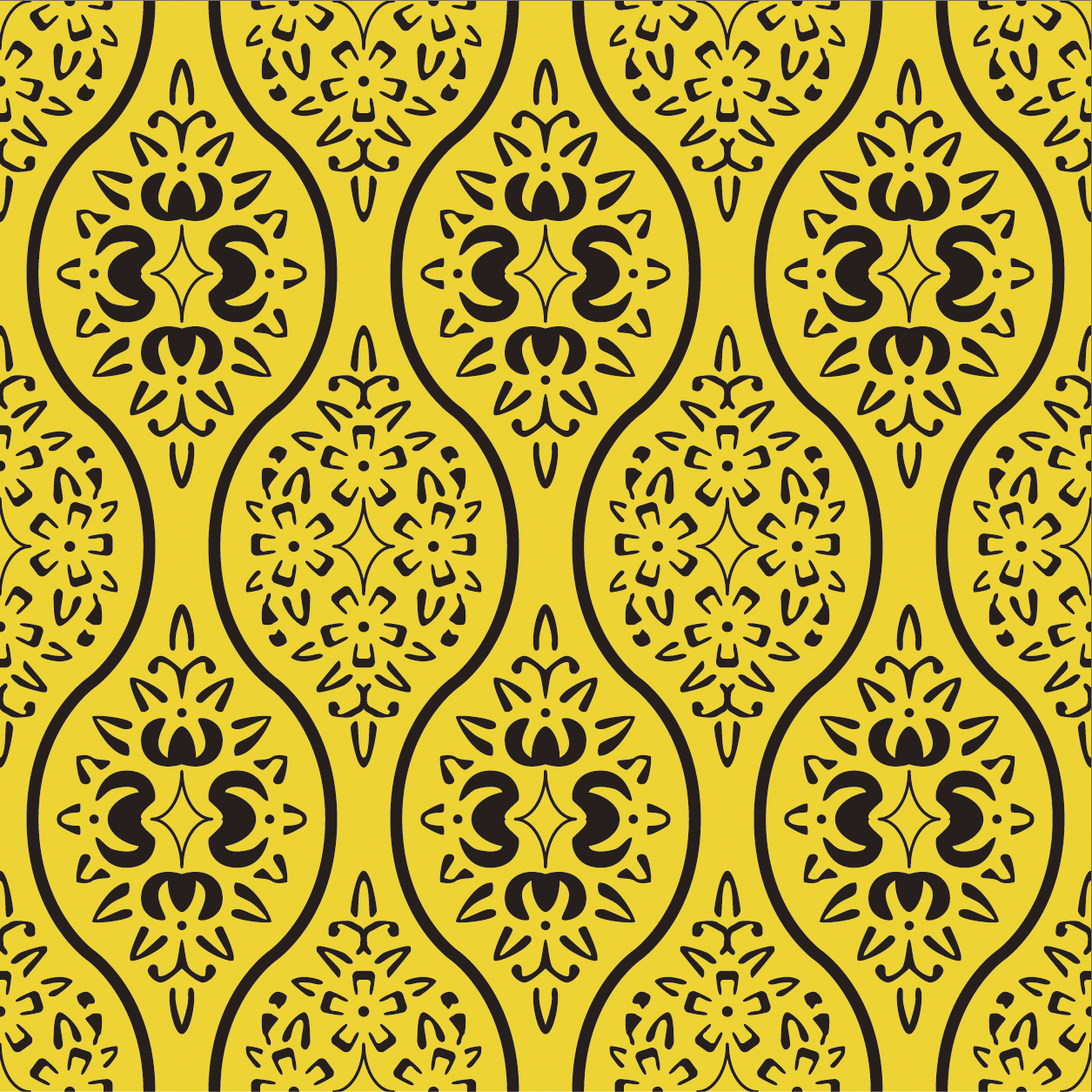


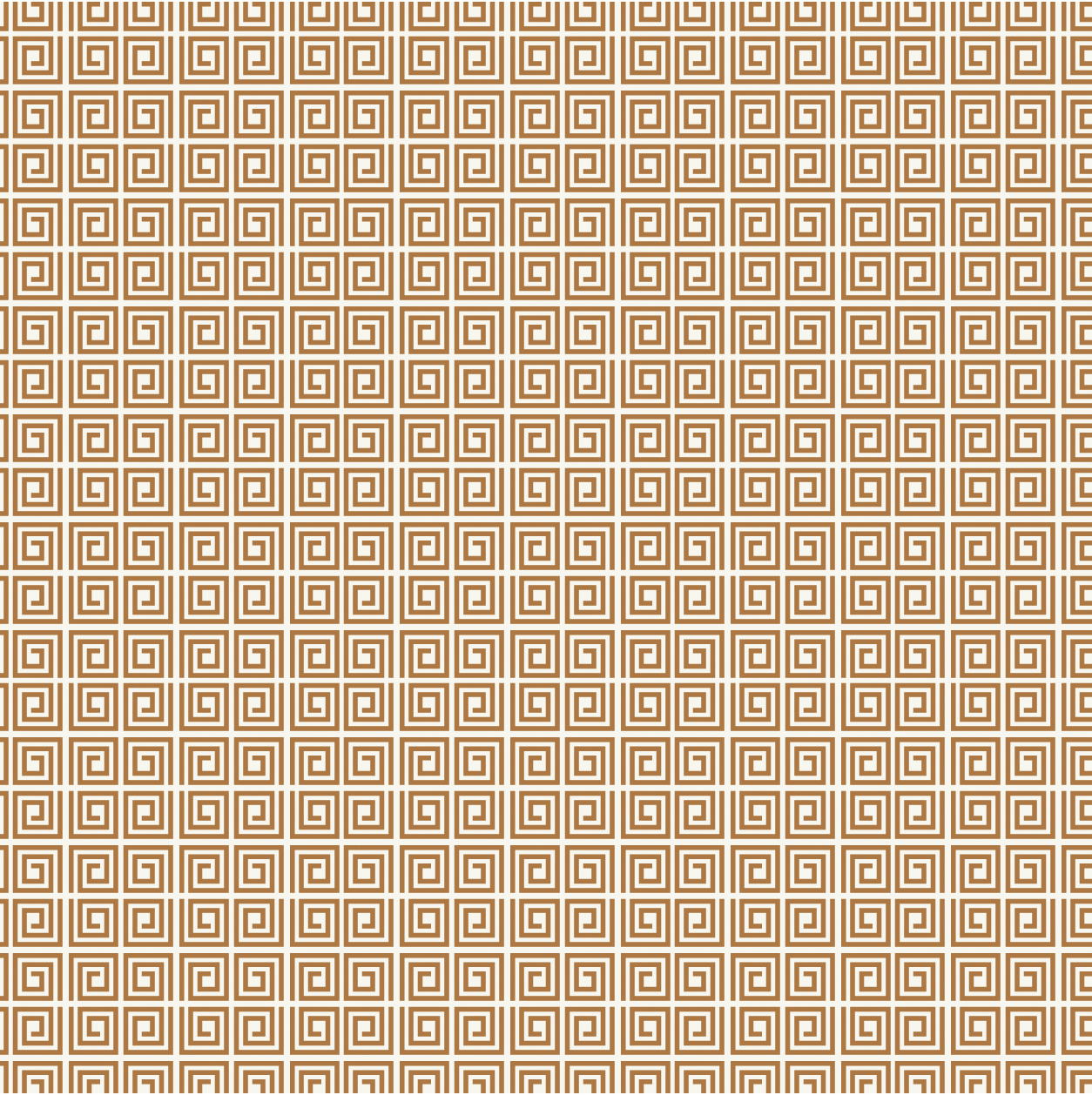

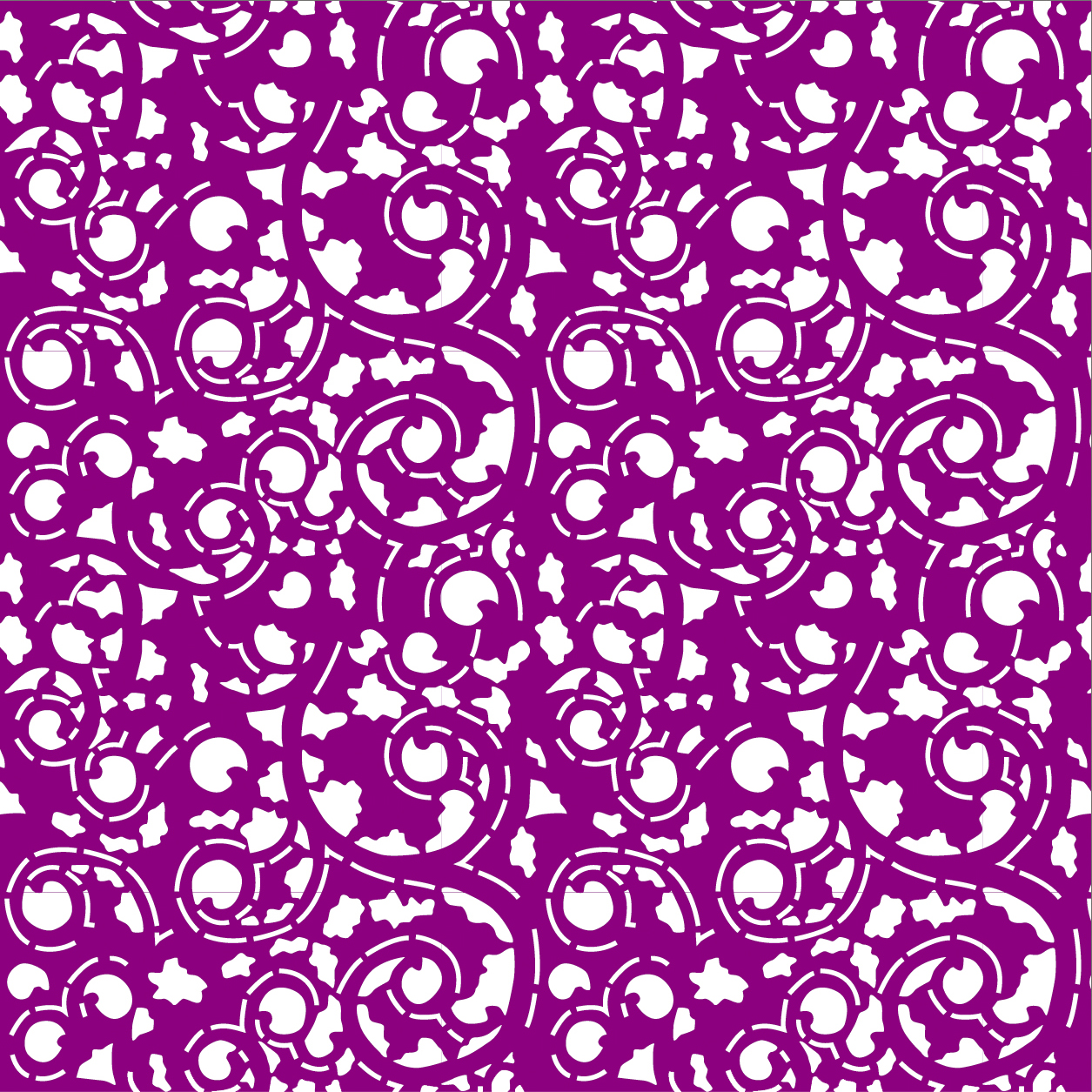

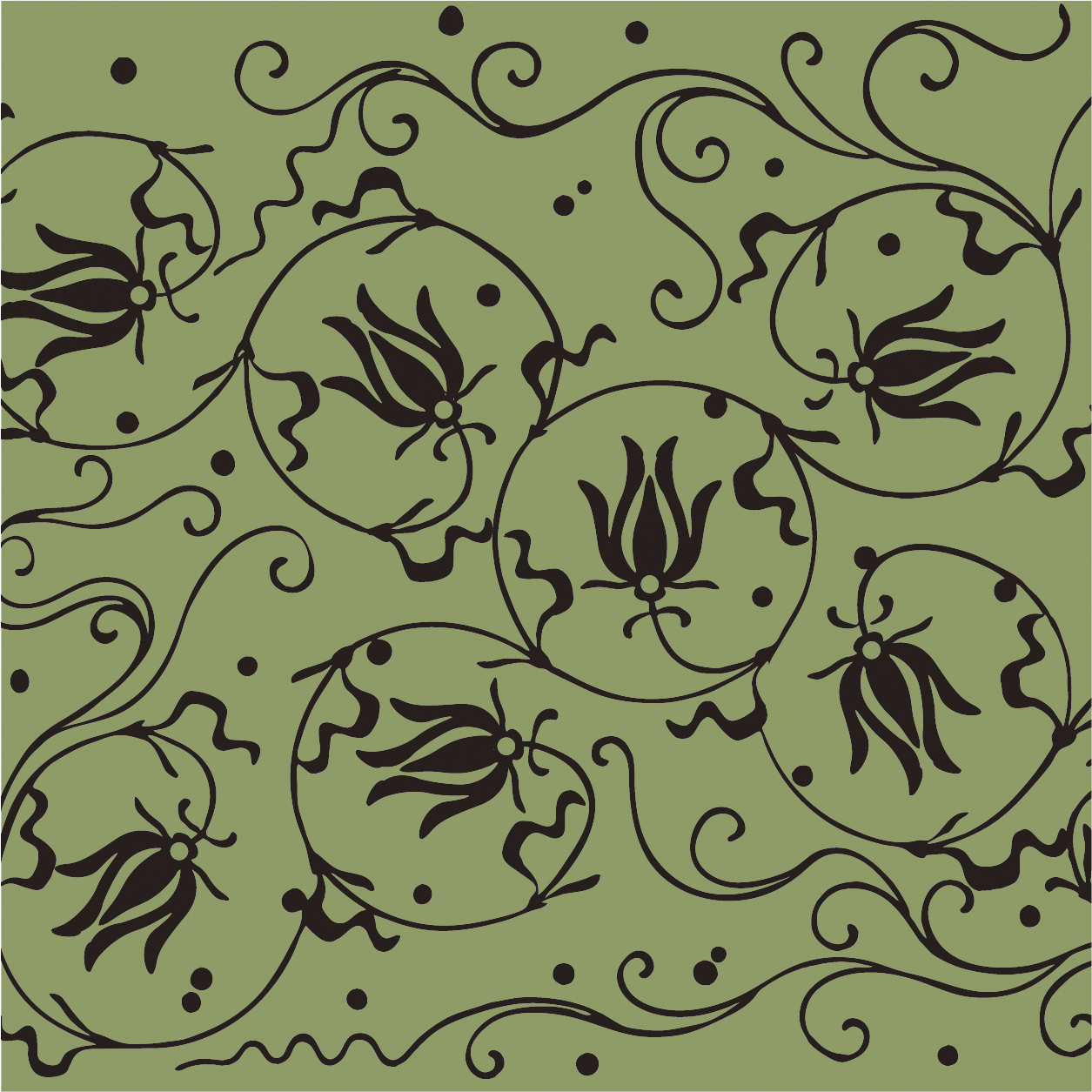

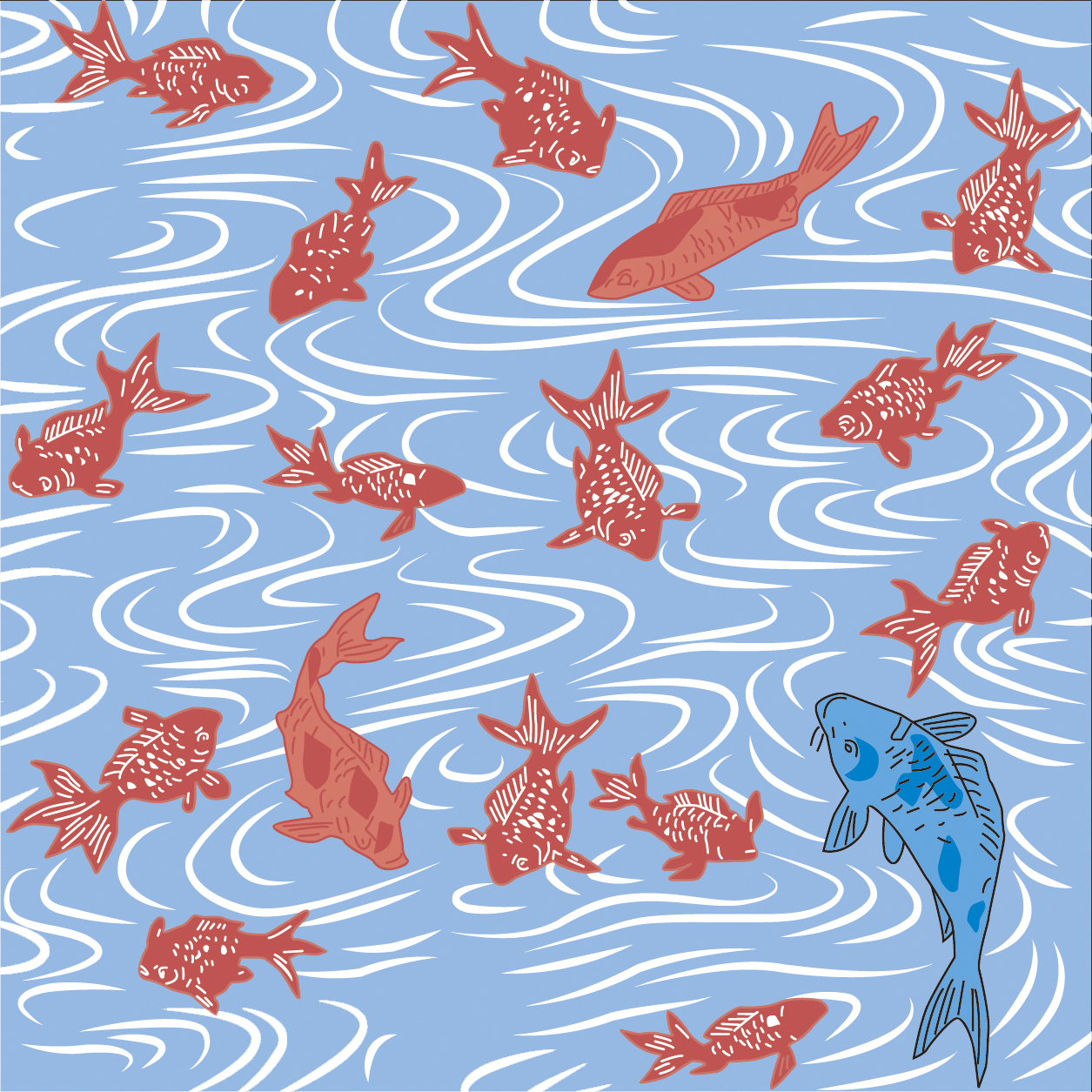
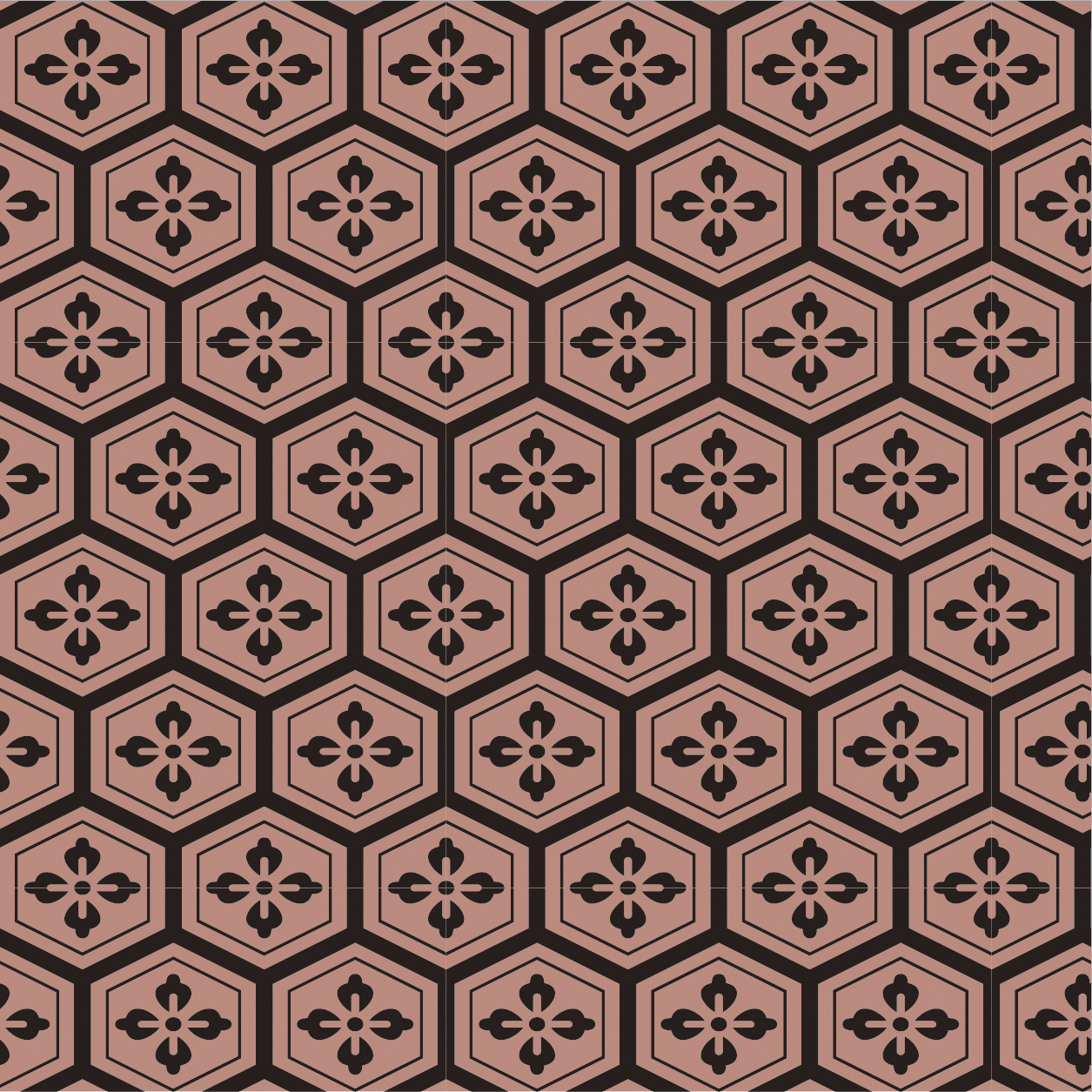
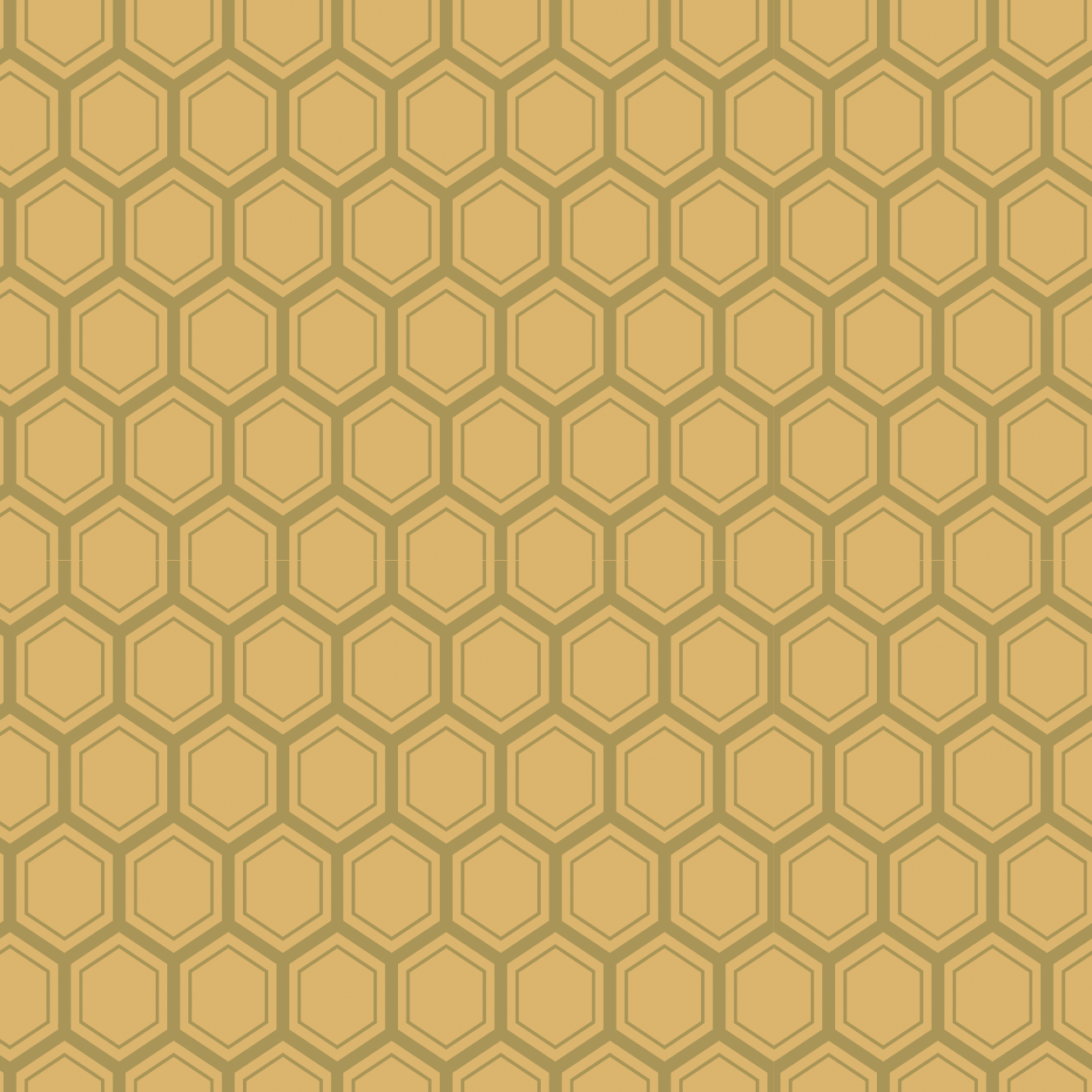
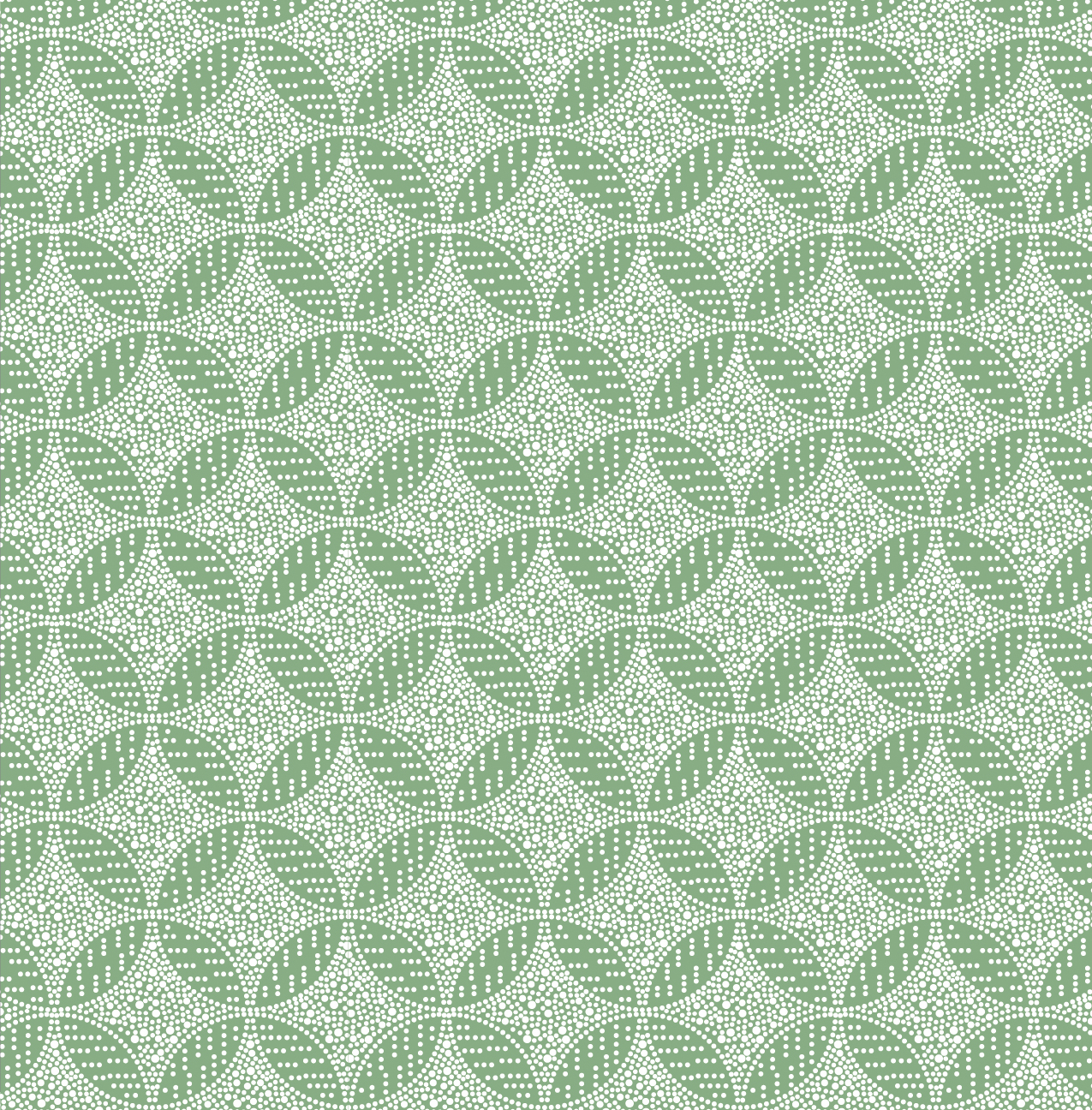
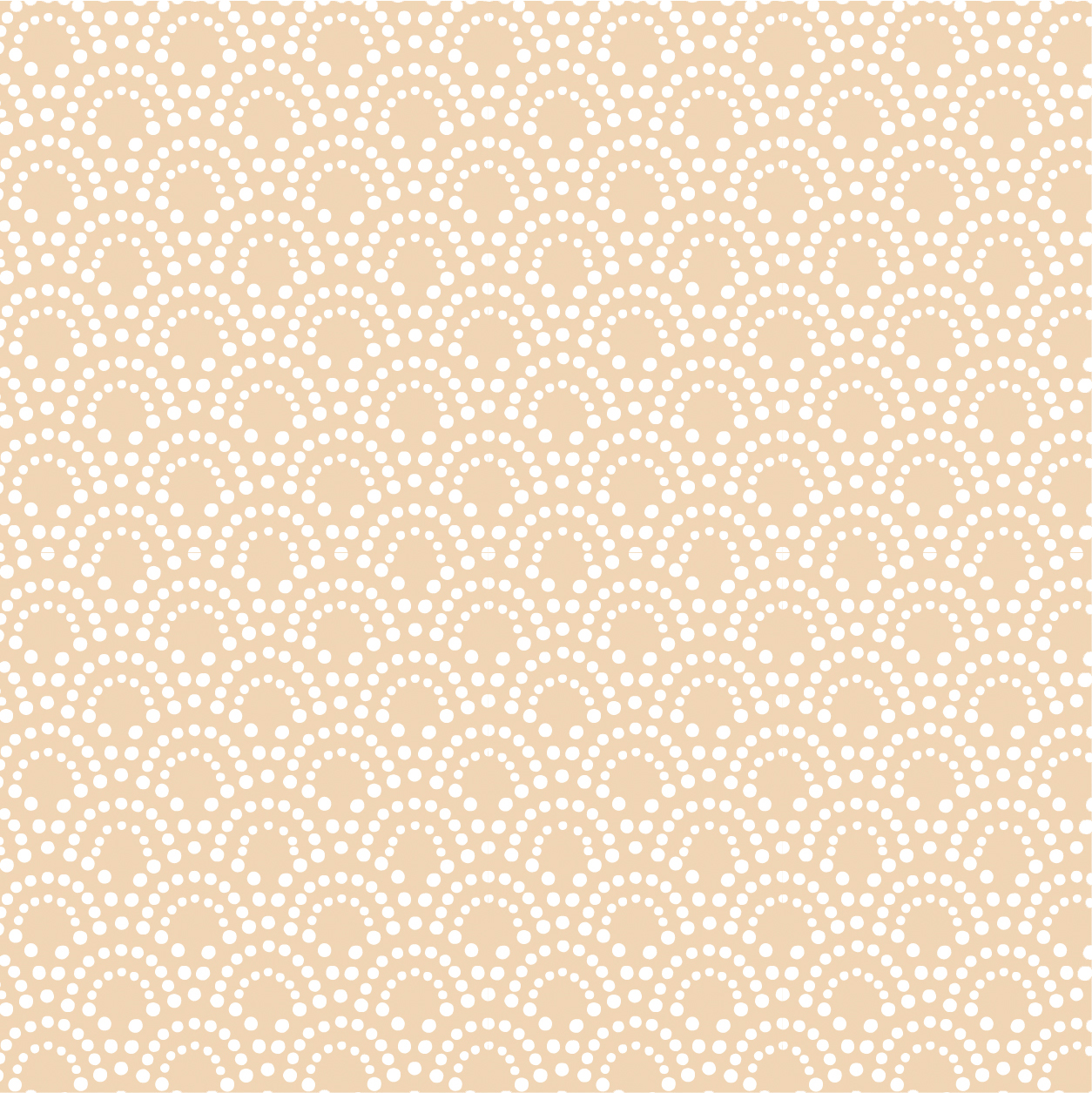
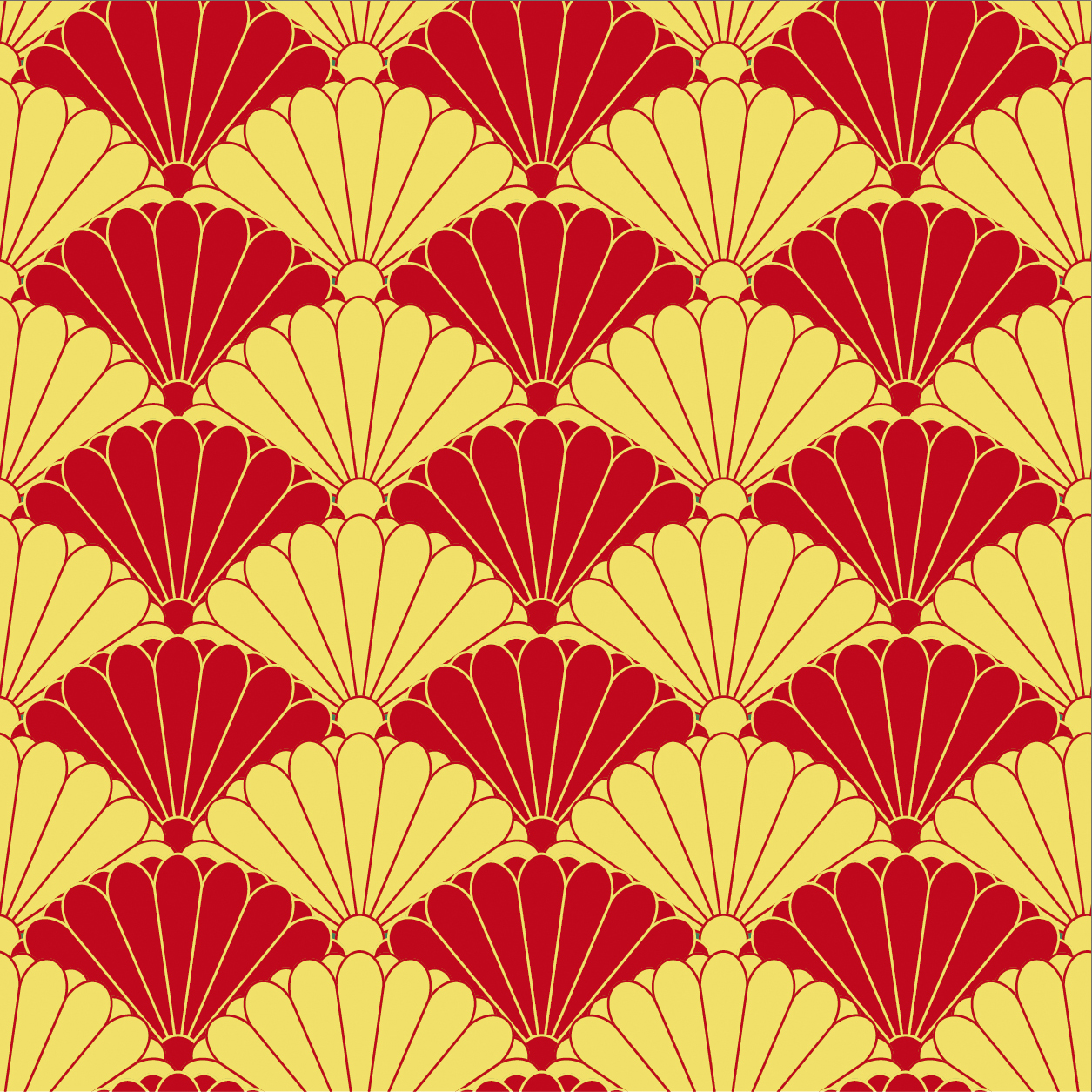
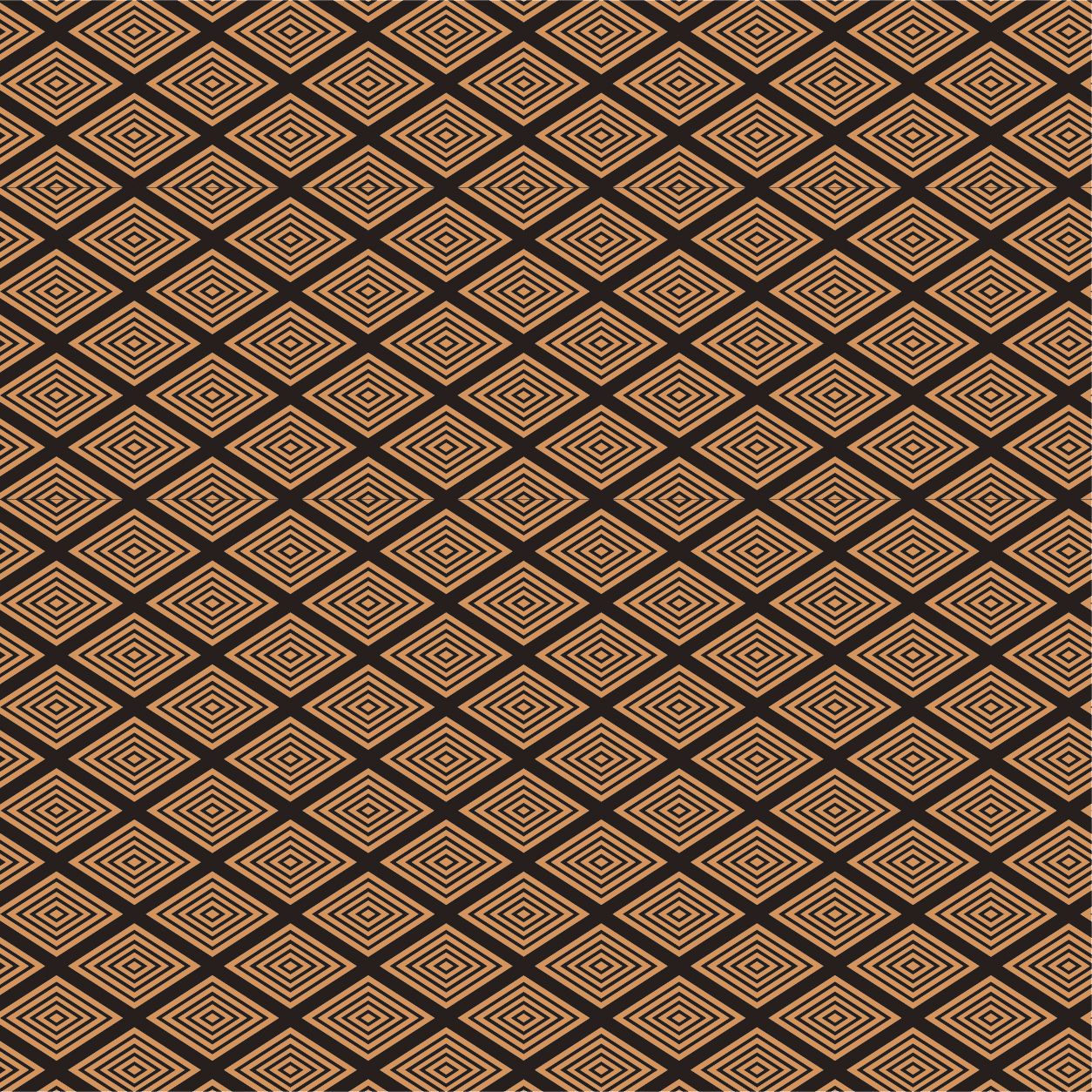
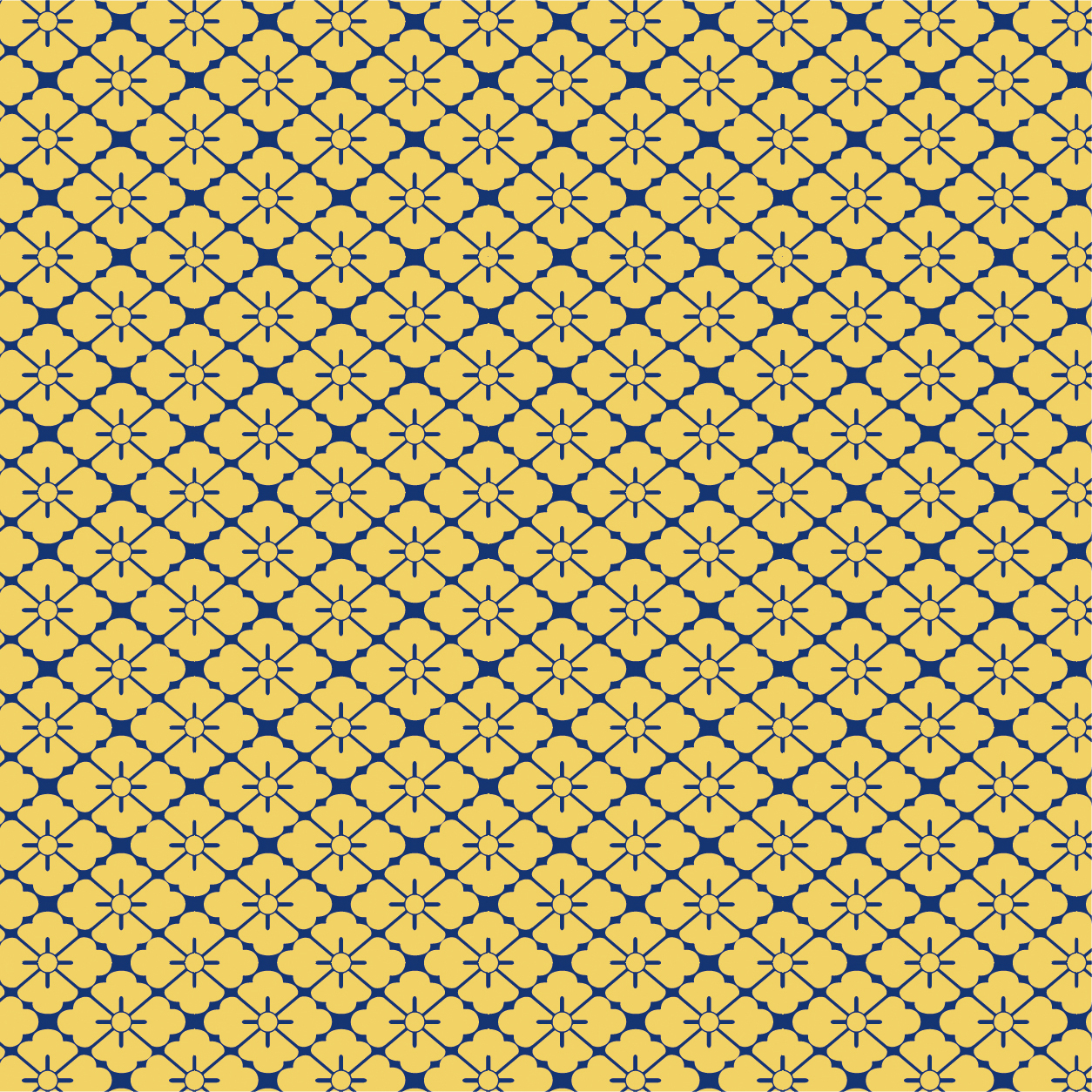
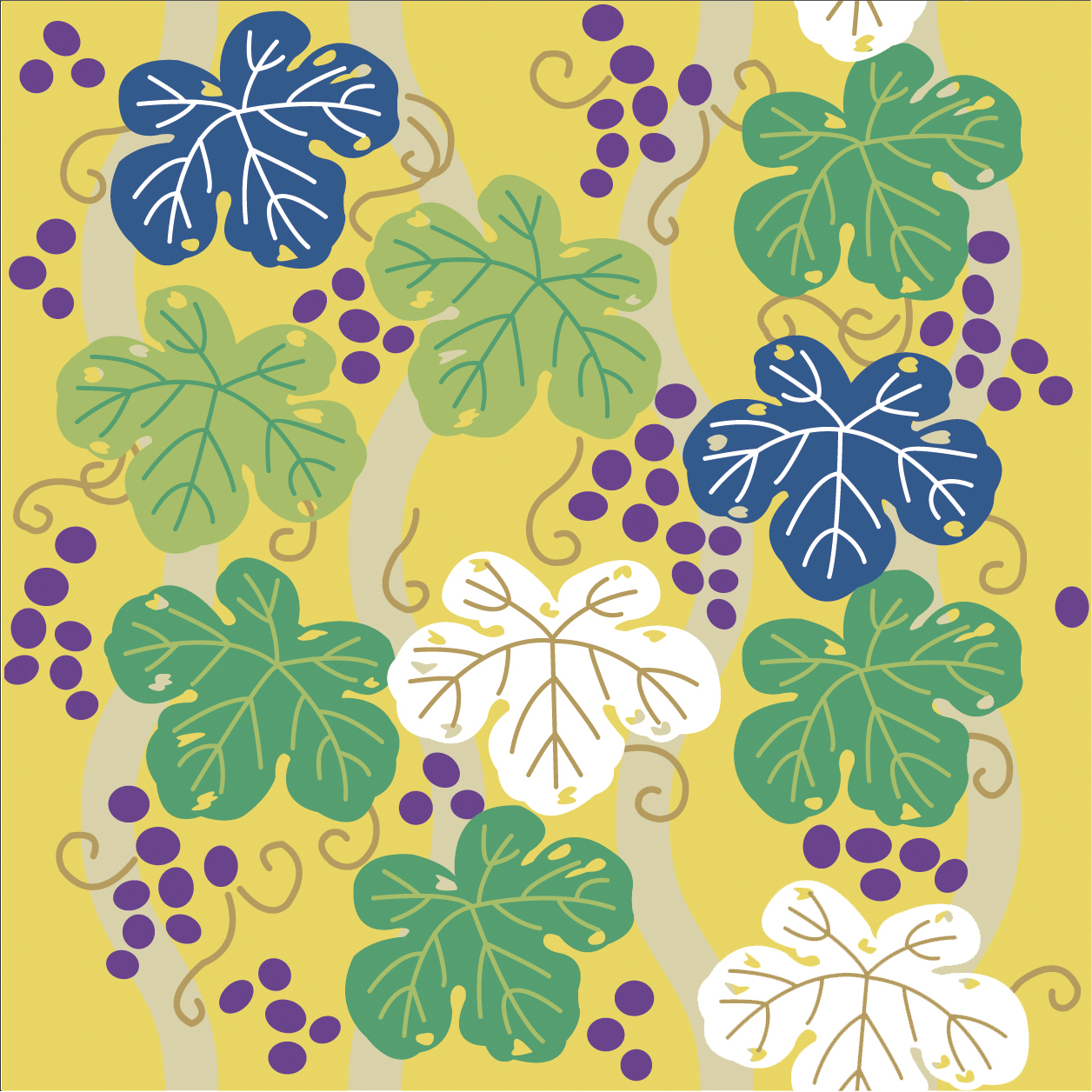
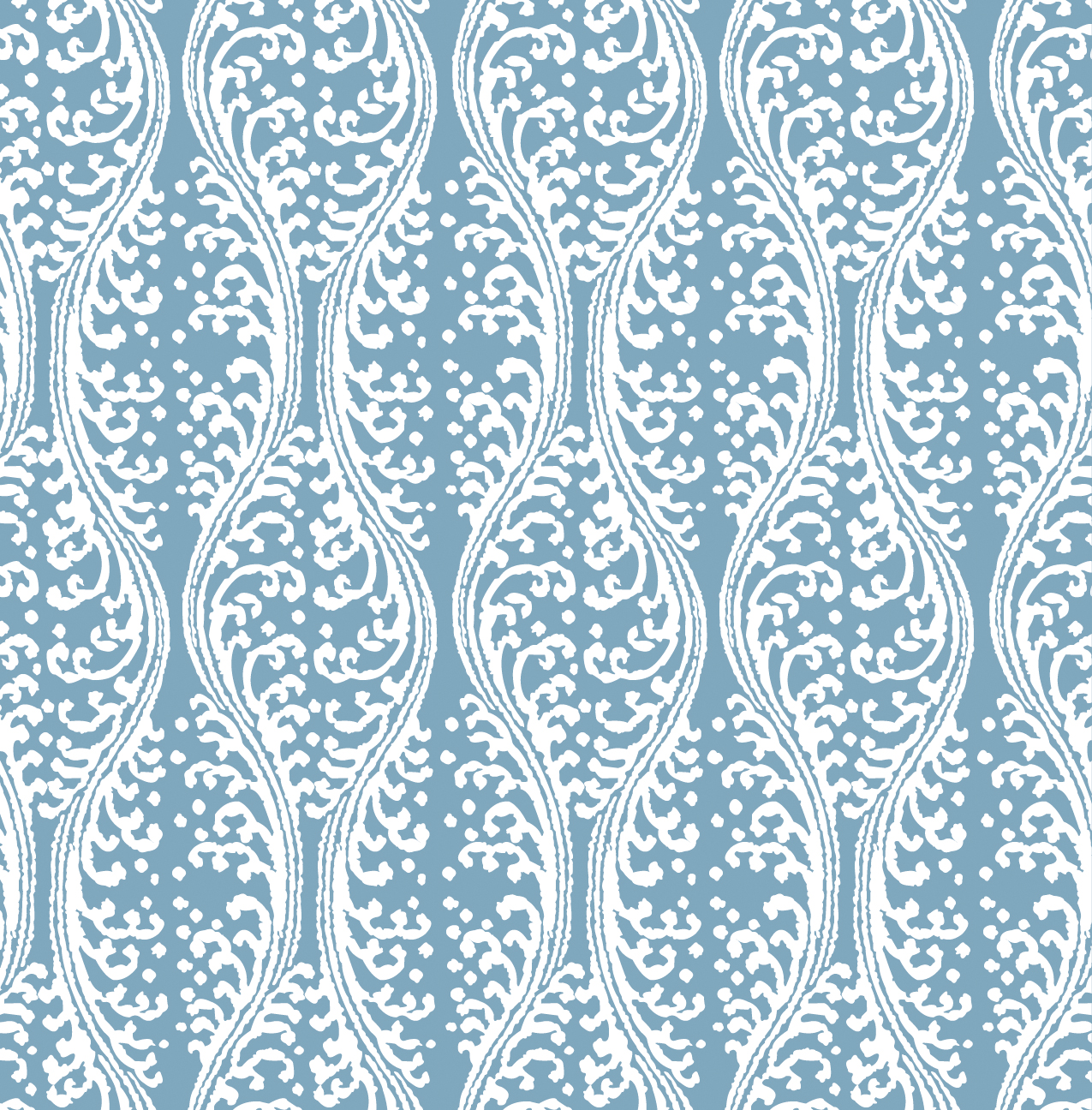
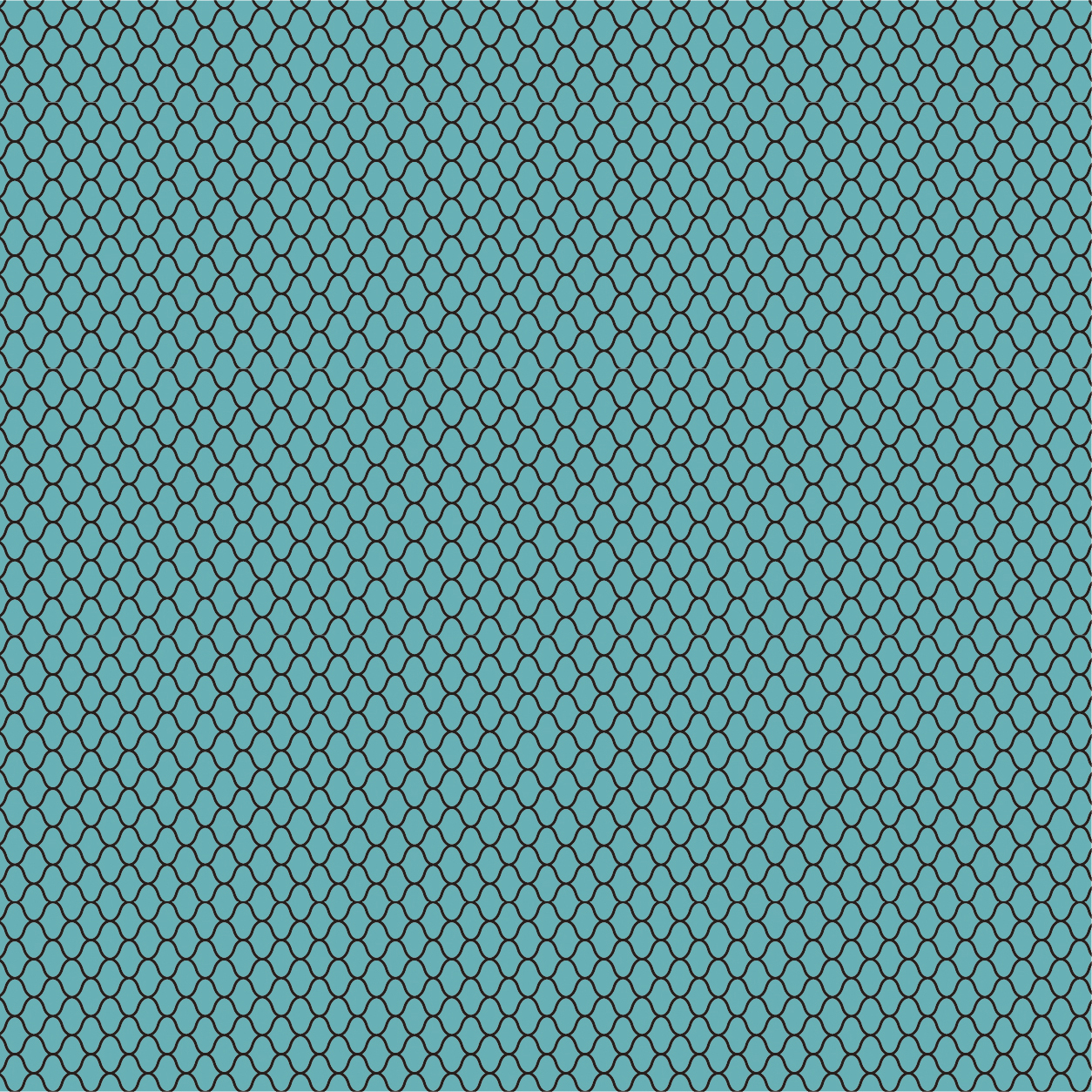
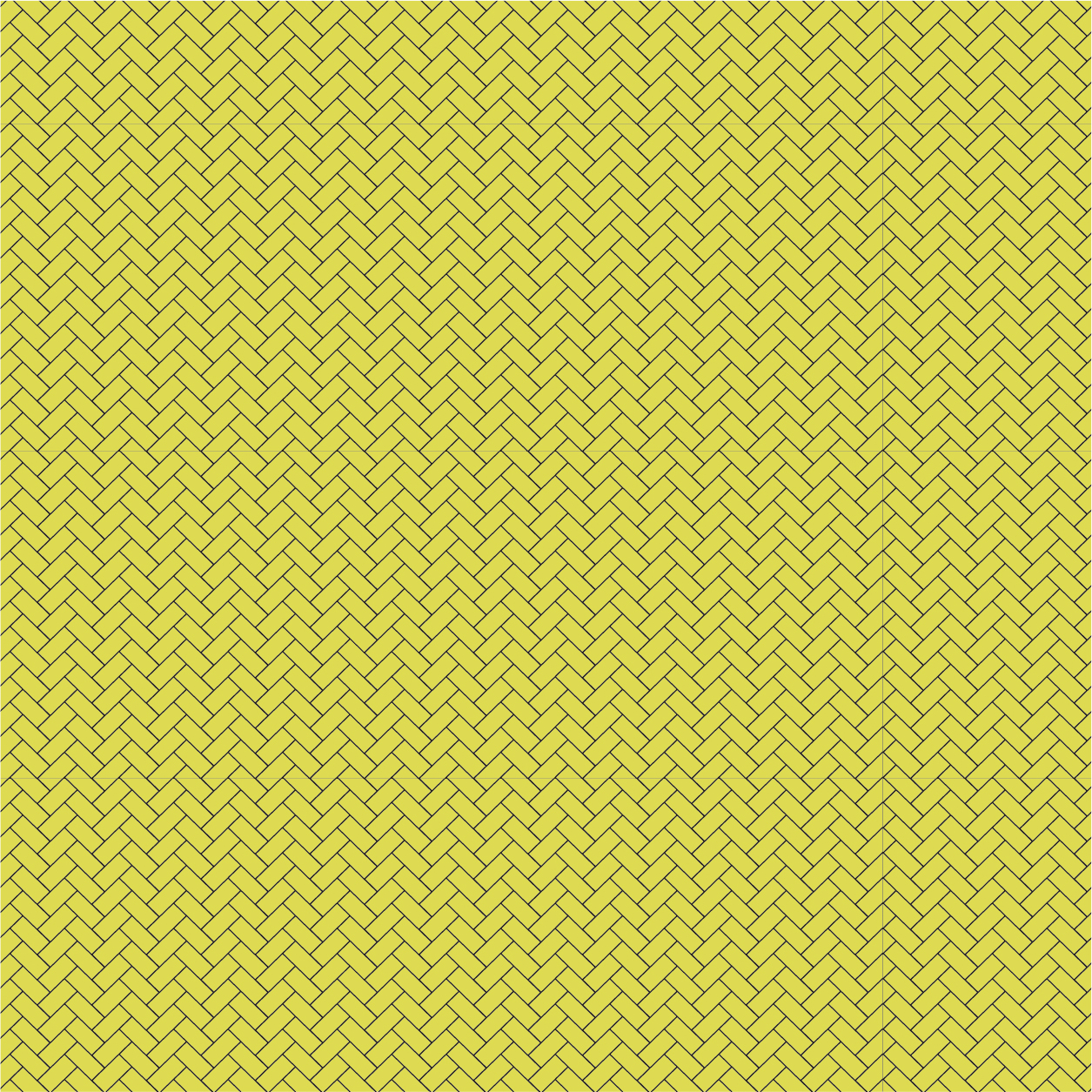
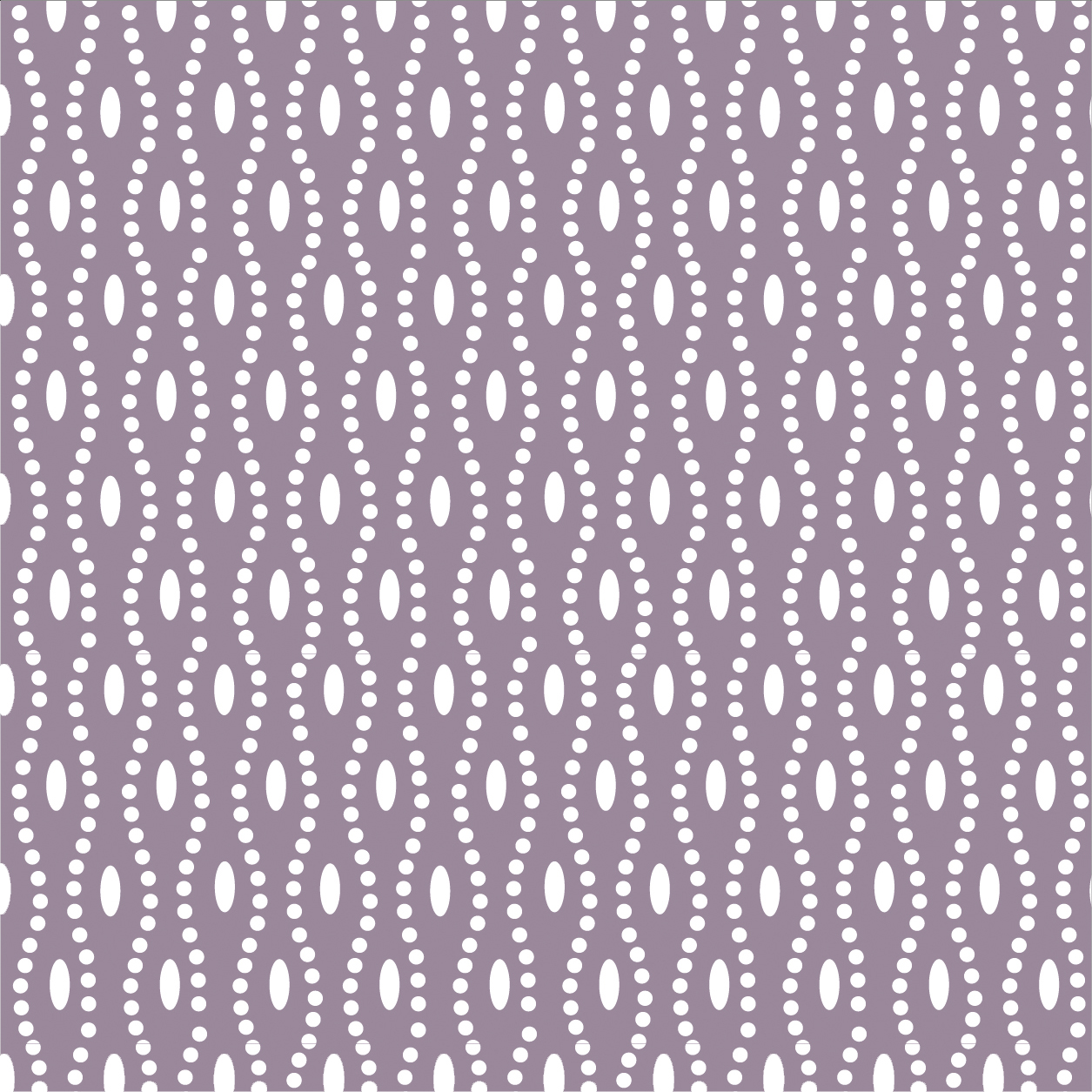
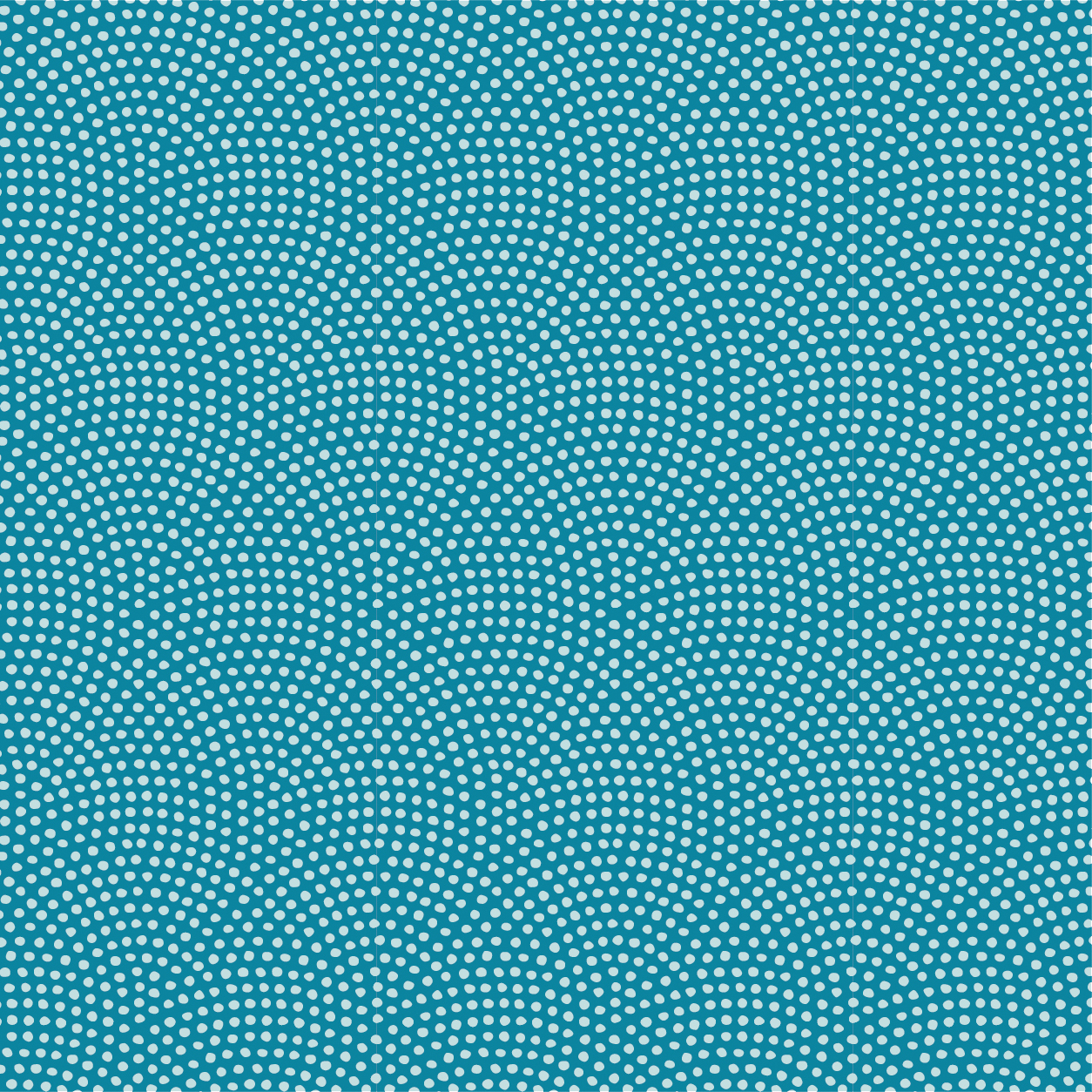
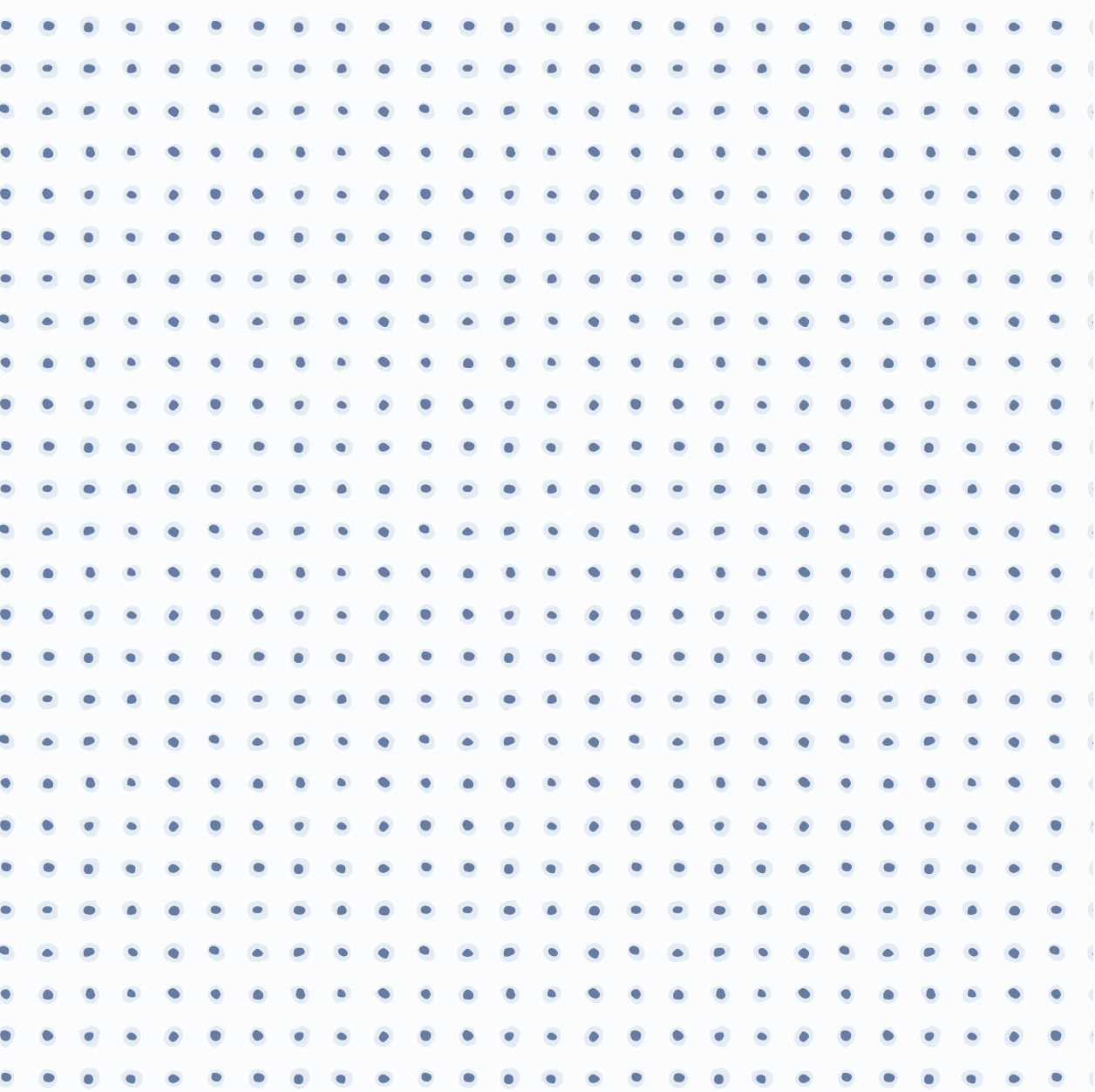
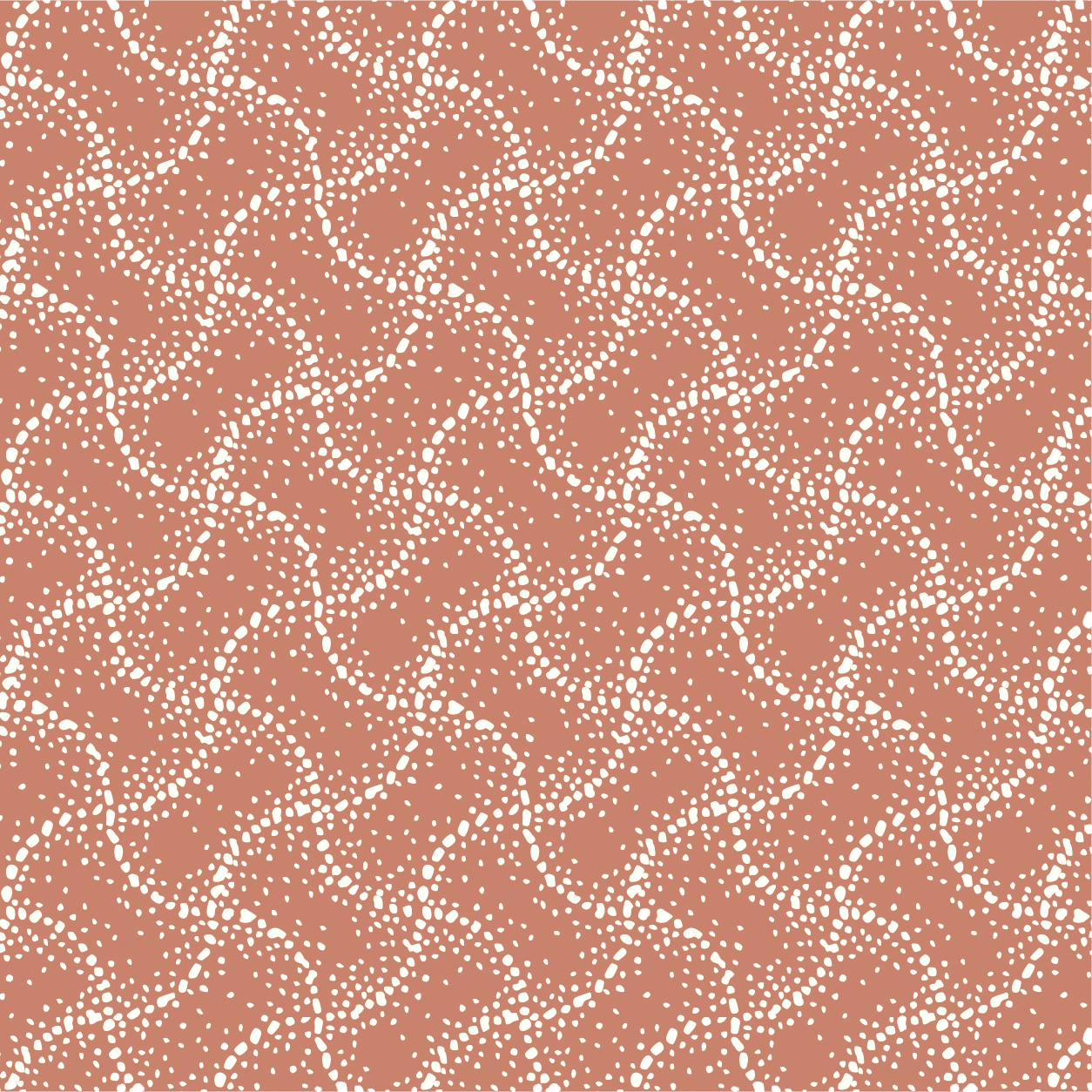
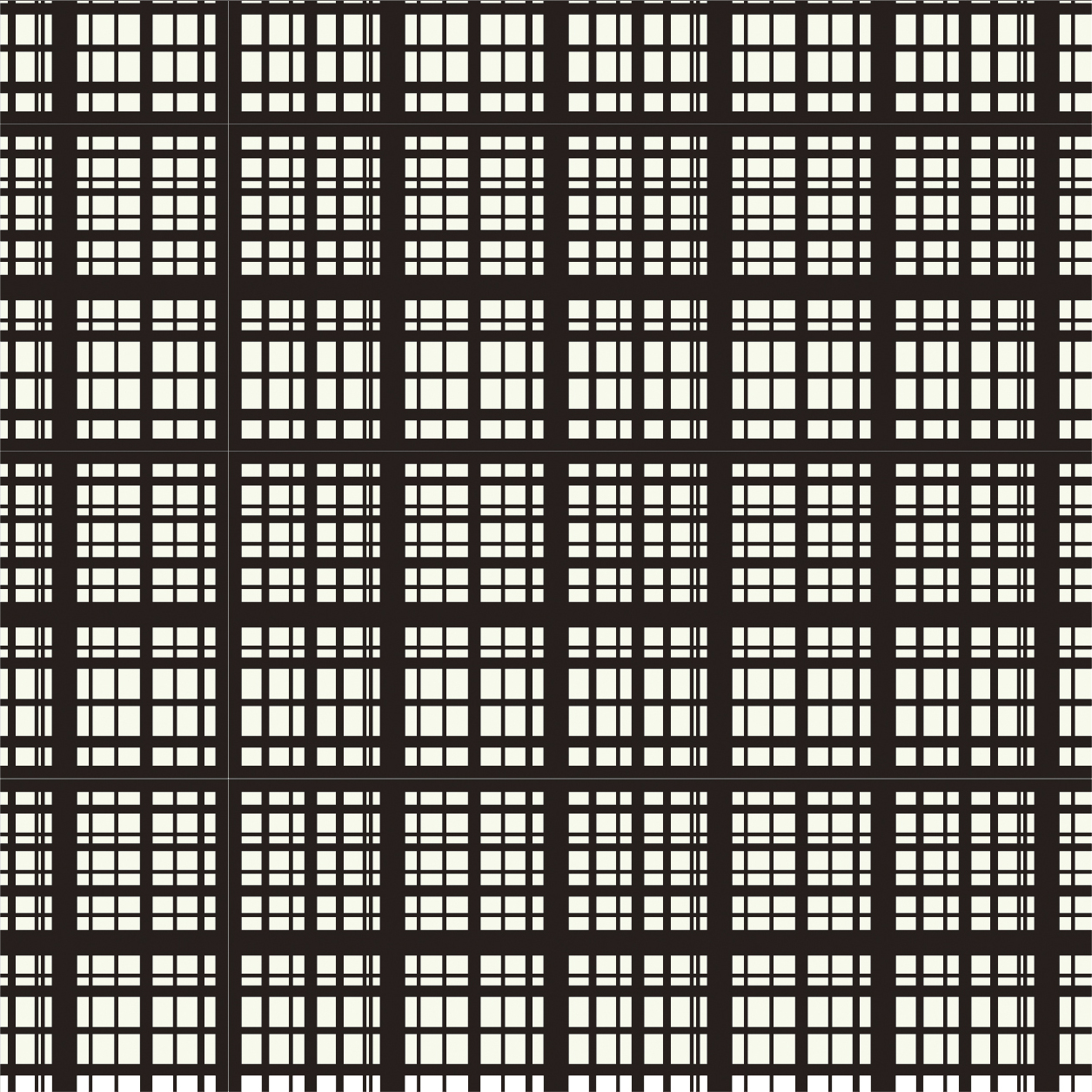
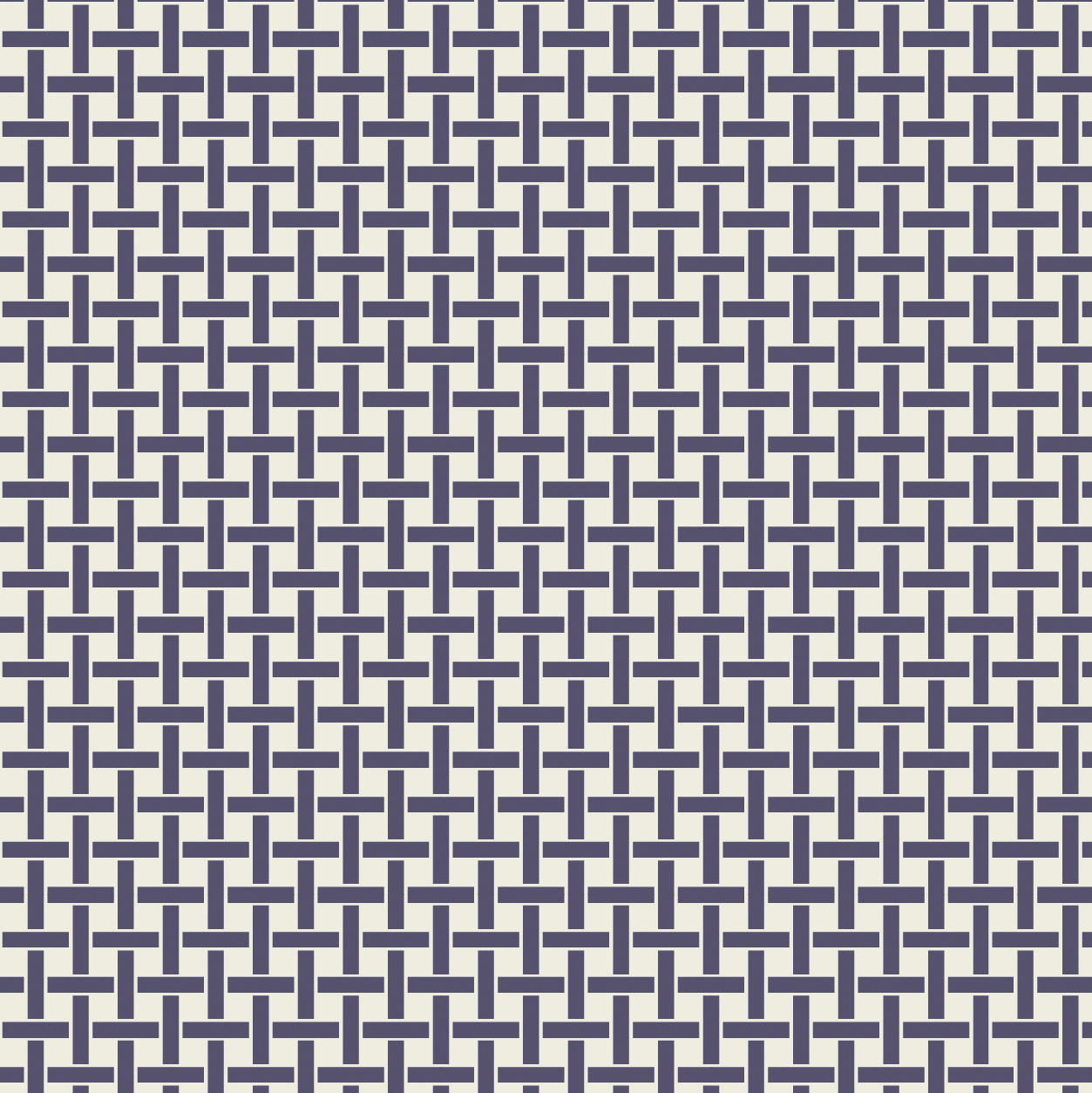
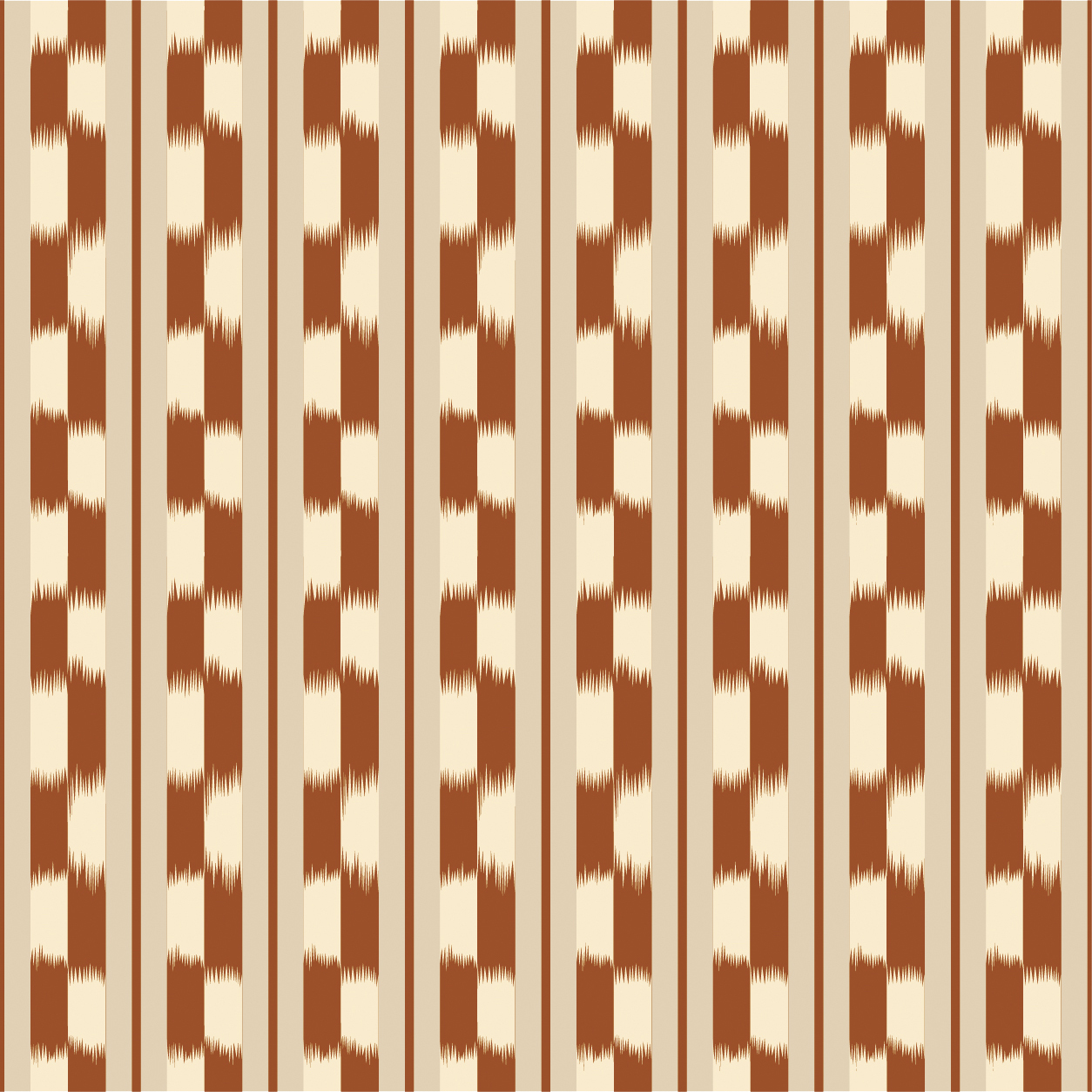

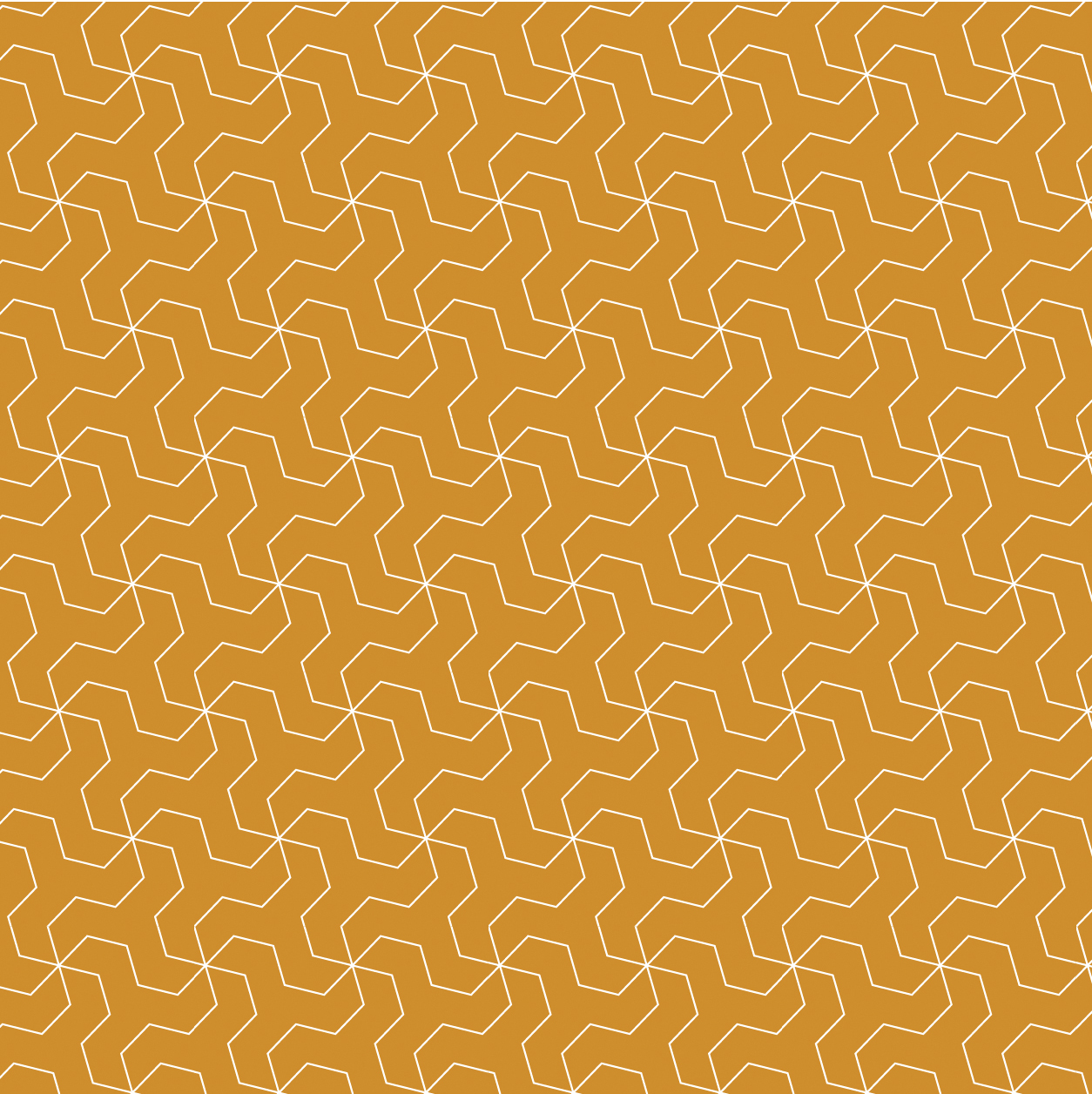
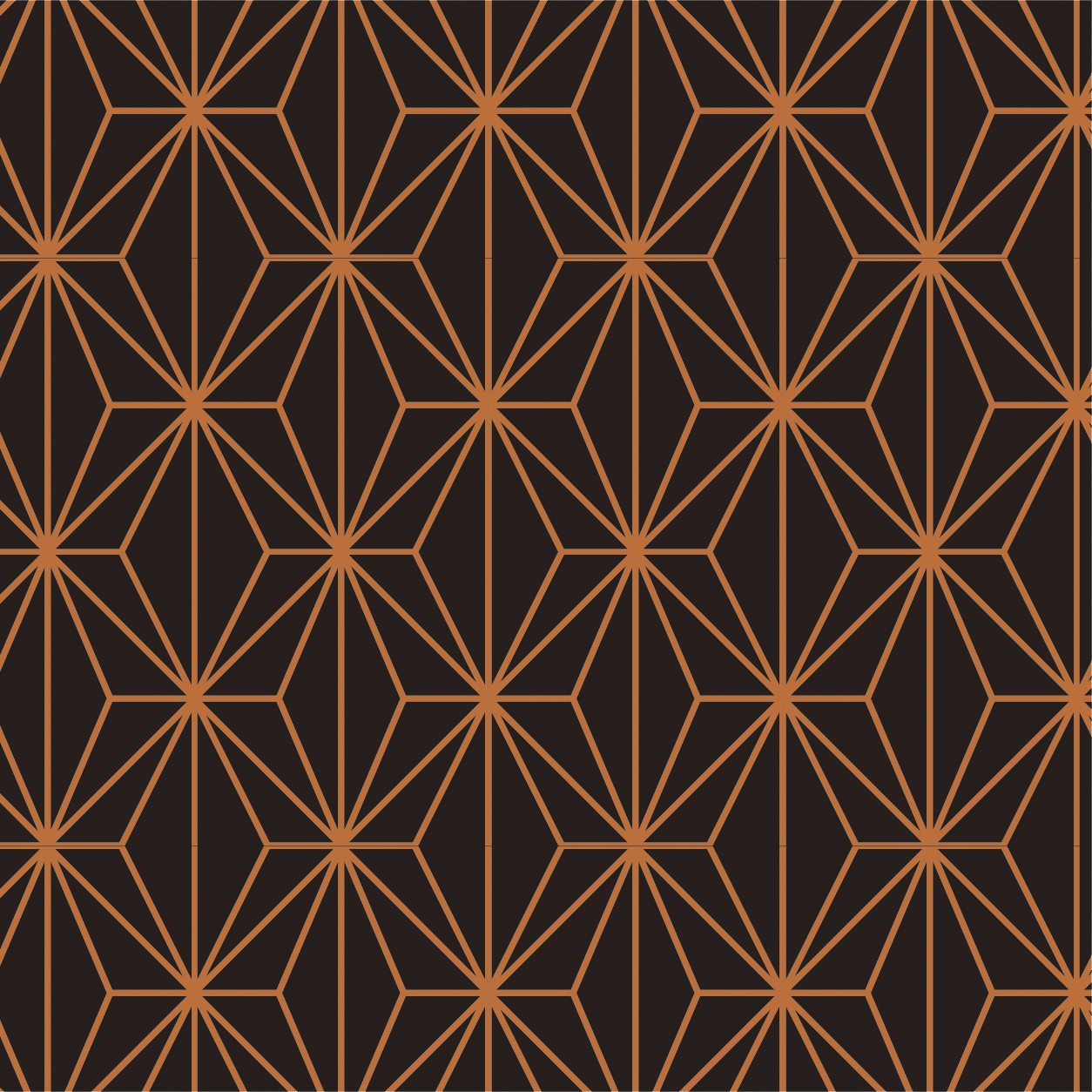
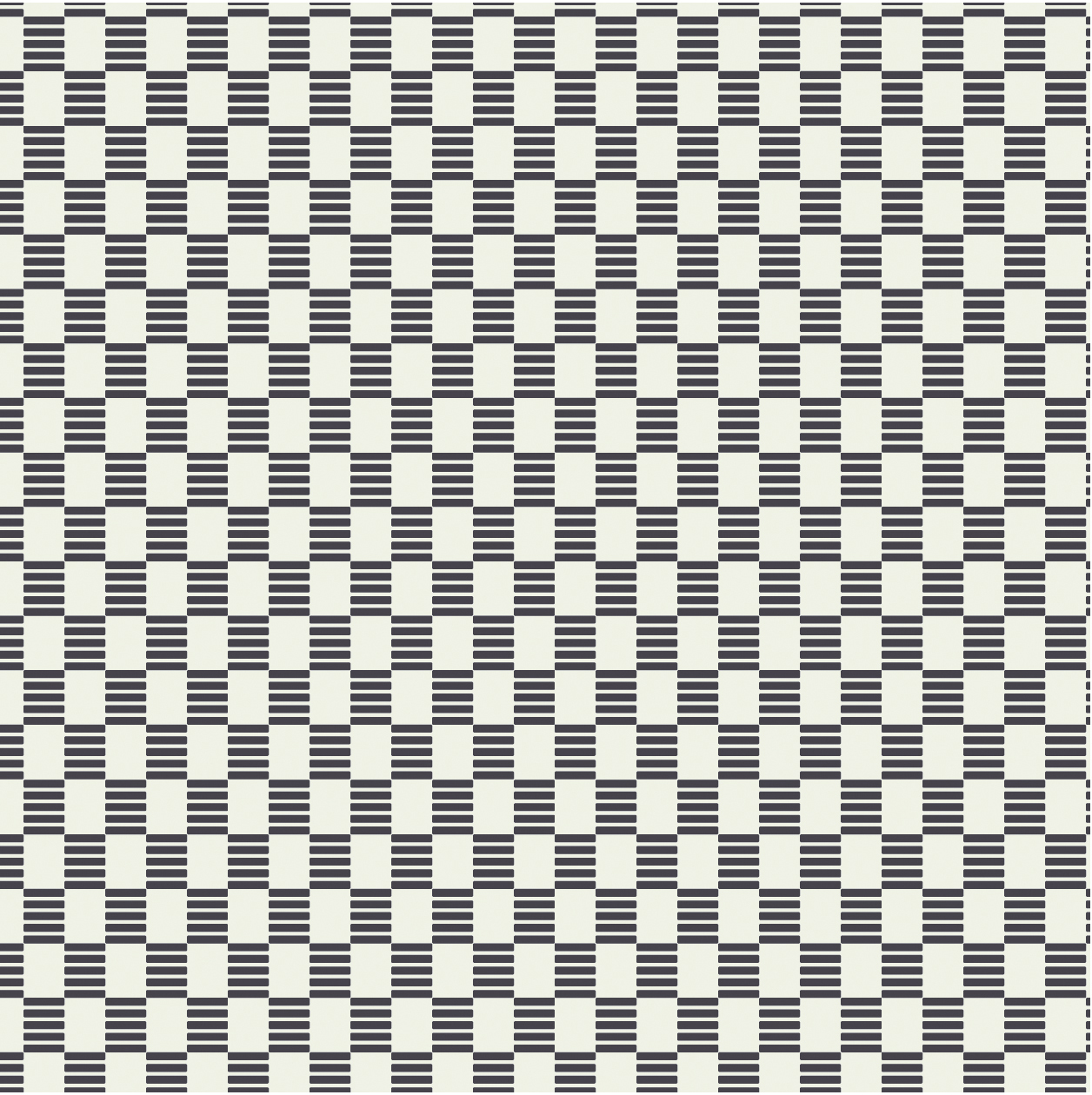
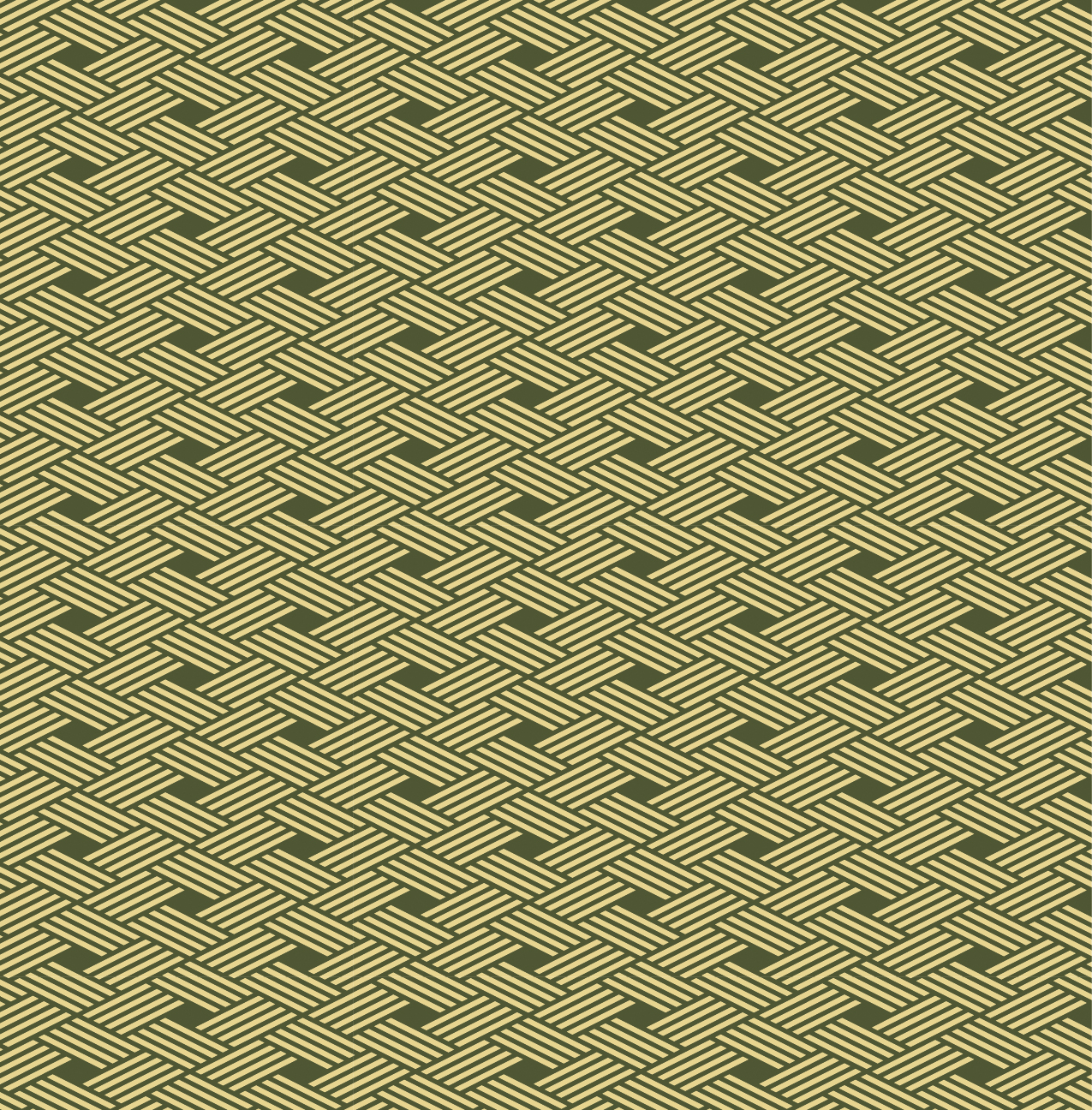
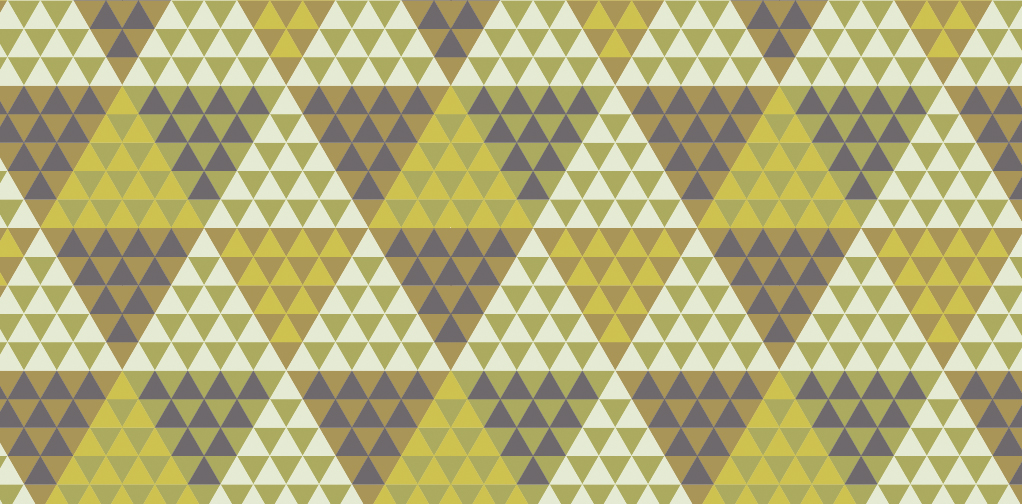
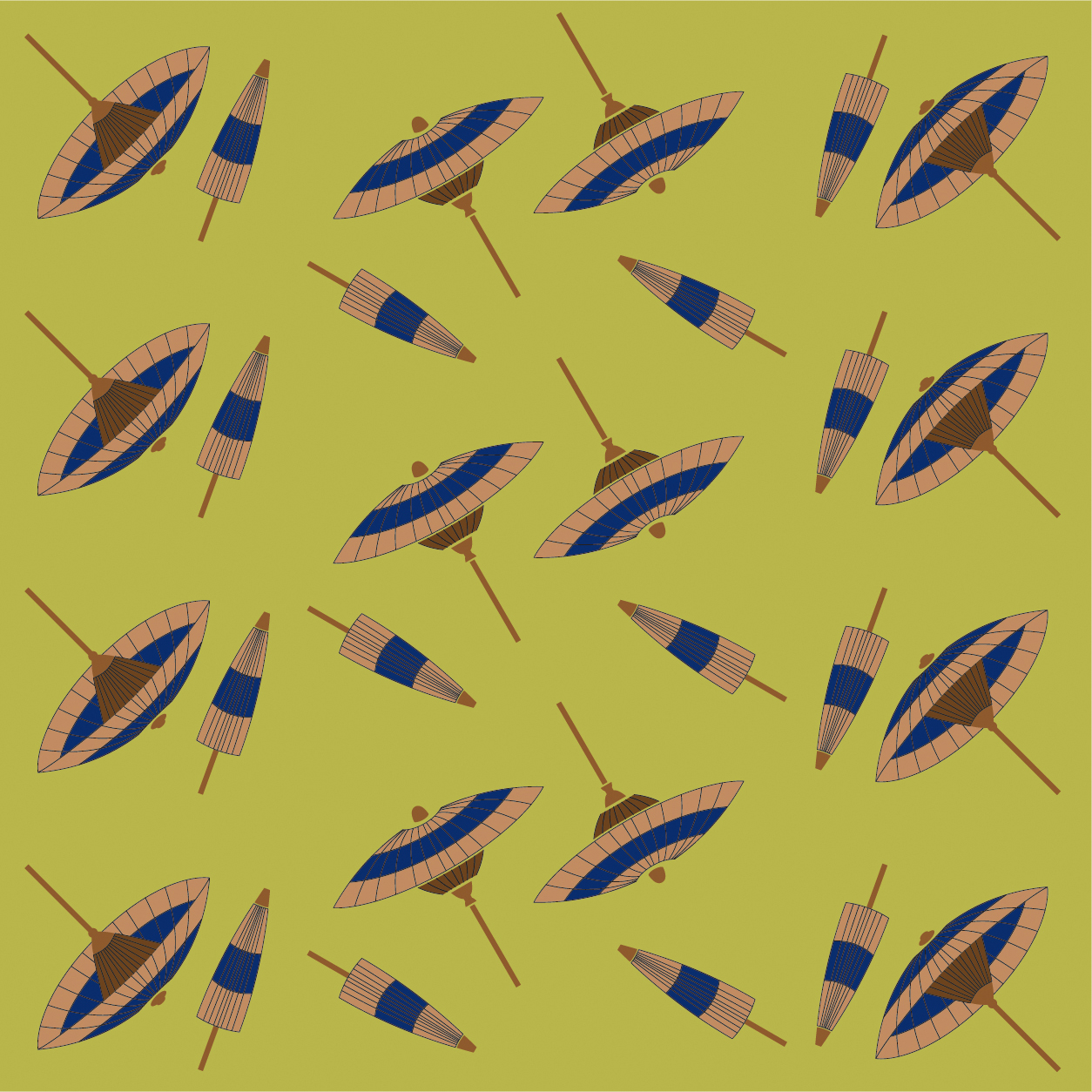
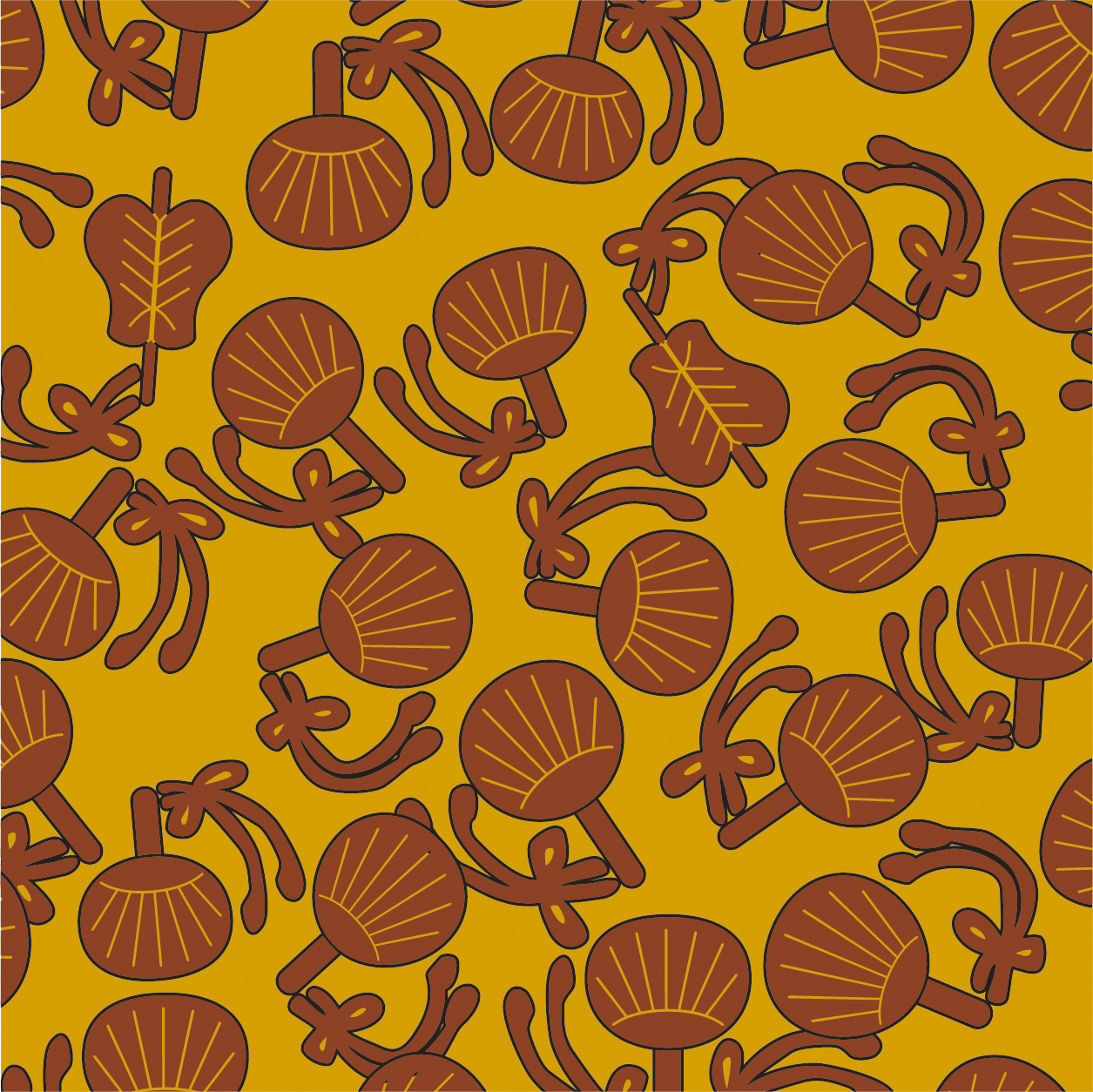
指貫の桜 |
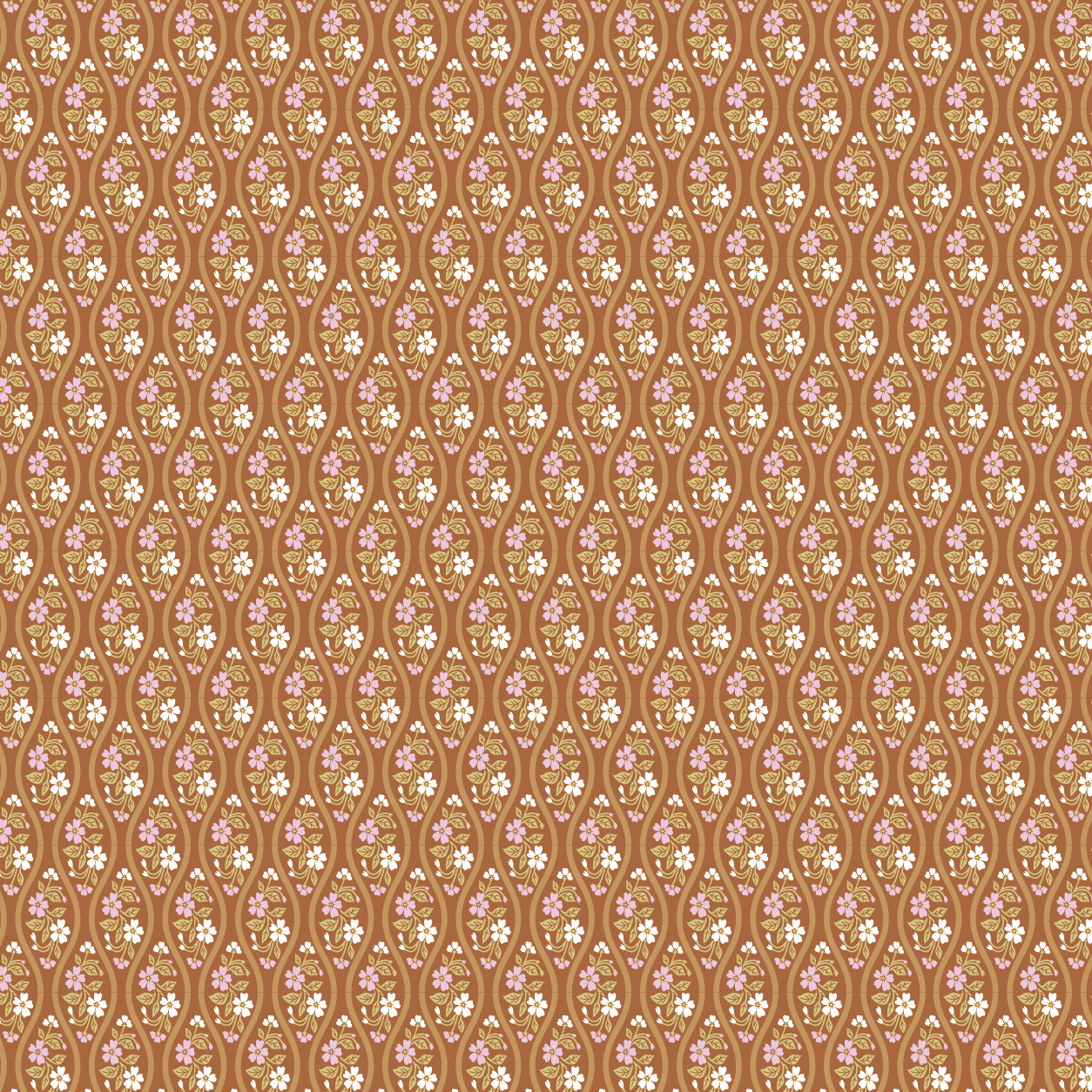 |
桜の花を立涌文様化した,舞楽装束の指貫の文様です.注:指貫(さしぬき)とは袴の一種のこと. |
| 藤立涌 | 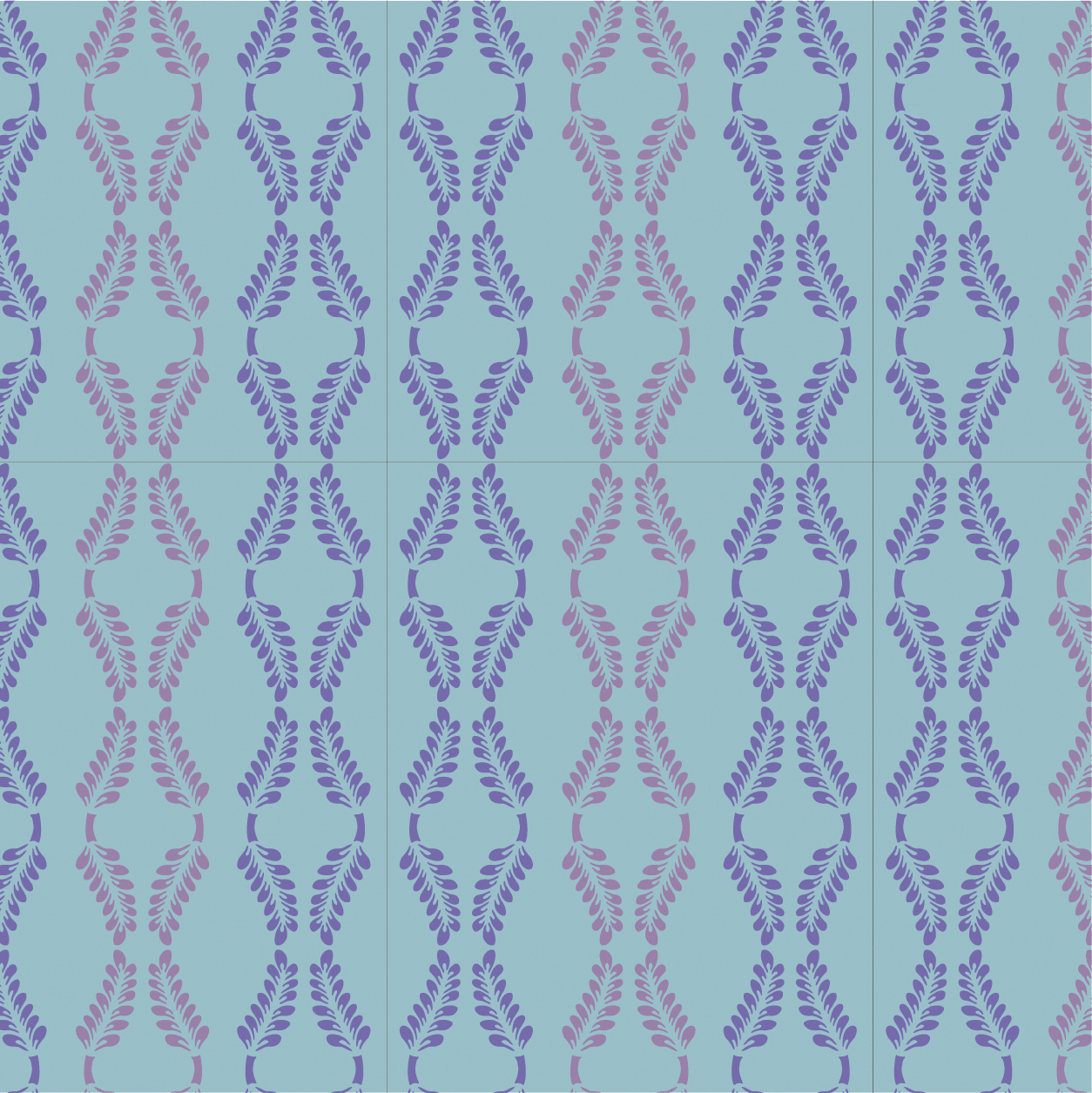 |
藤の花を立涌にみたてて規則正しくデフォルメしたものです |
| 螺鈿の朝顔 |  |
櫃を覆いつくさんばかりに描かれた,蒔絵螺鈿の朝顔です |
| 唐織の夕顔 |  |
色彩豊かな夕顔を,金糸の霞紋でまとめた構成です |
| 錦の蓮 | 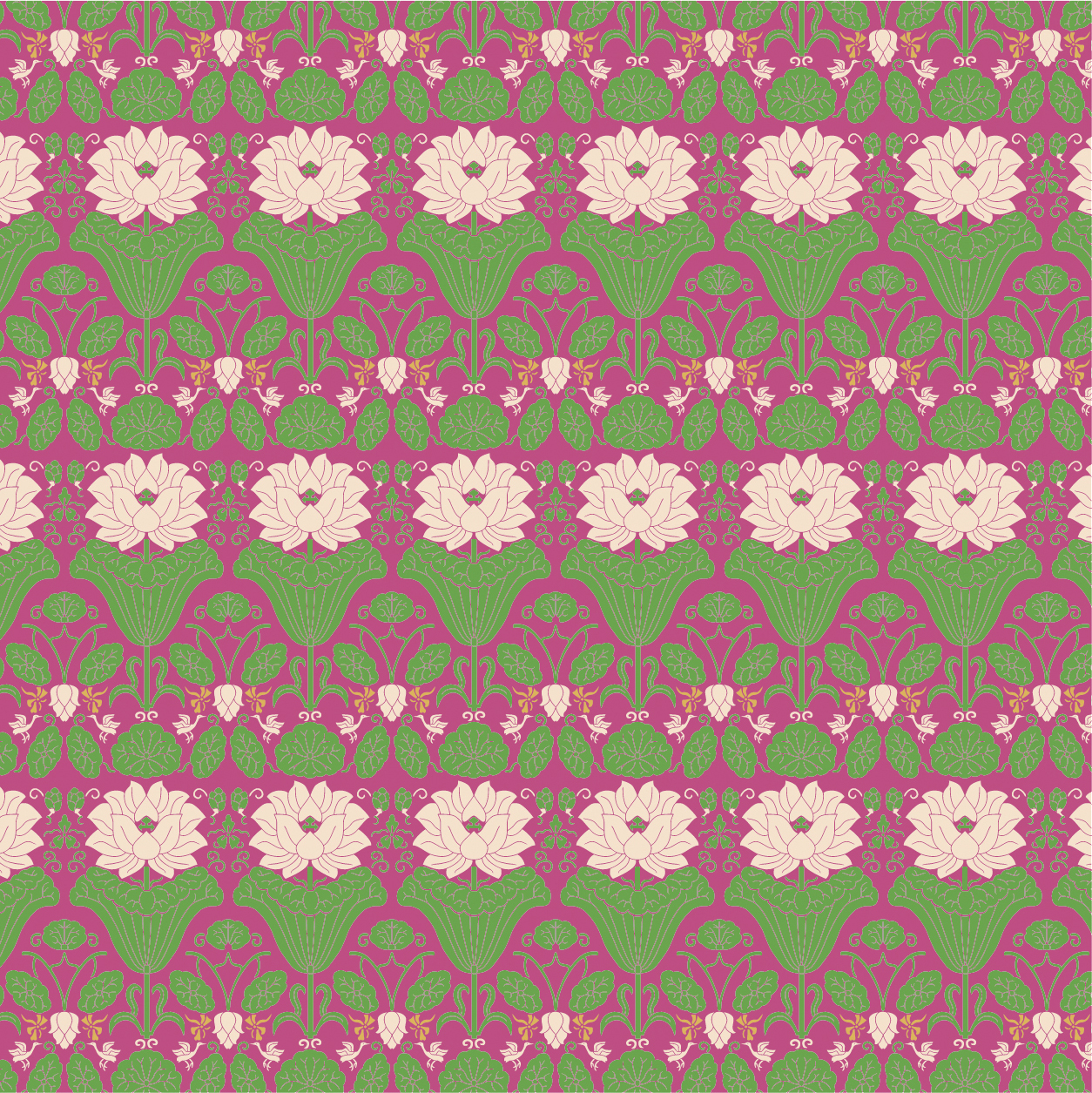 |
荷花・荷花で構成され.水禽を配することで蓮池を表しています |
| 流水紅葉 |  |
流水に紅葉が流れていく様を模様にした京からかみの文様です |
| 梅唐草 |  |
中心円のまわりに5つの円で梅花を表す梅鉢の唐草文様です |
| 松葉散らし |  |
松の葉を,自然にまかせて散ったように表した文様です |
| 梅垣 |  |
|
| 桜橘立涌 | 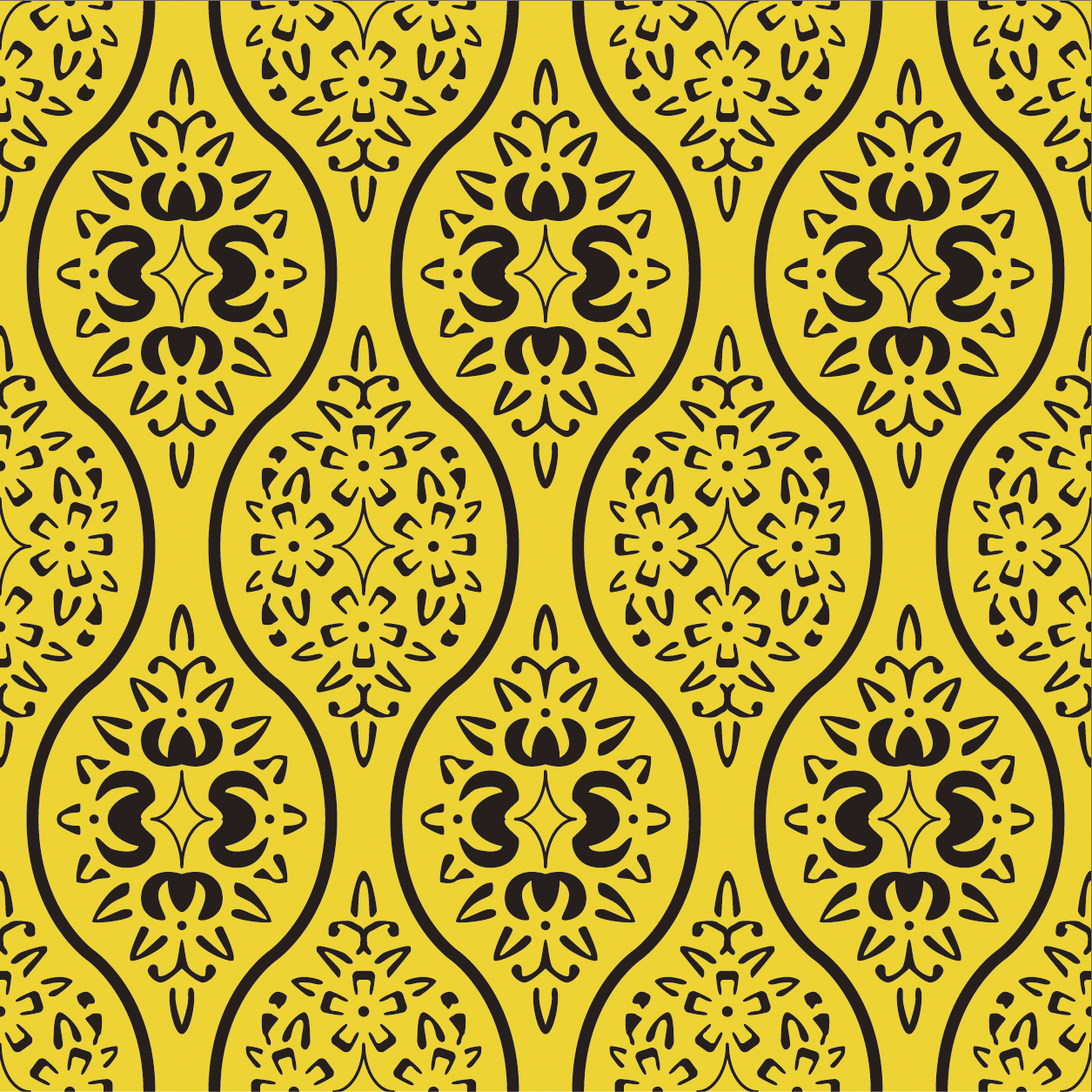 |
桜と橘を用いて立涌文にした,公家好みの京からかみです |
| 花筏 |  |
楓と流水で龍田川を表し,桜折枝が流れてゆく様の文様です |
| 雪華文 |  |
さまざまな種類の雪の結晶を花のように描いた文様です |
| 雷文 | 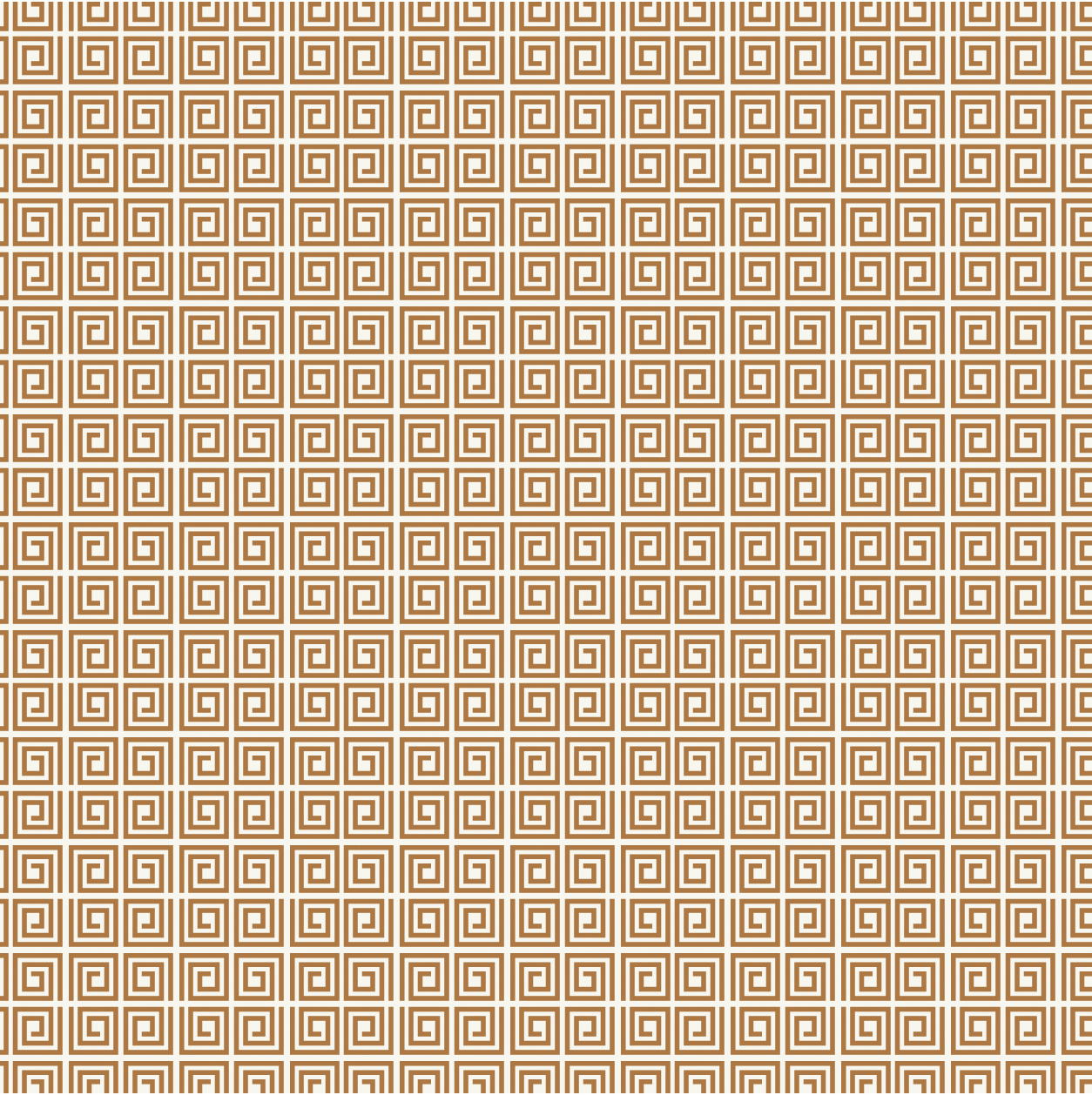 |
渦巻形が幾何学的に方形になった,代表的な雷文です |
| 厚板の蔦 |  |
厚板に描かれた唐草文様のように連続した蔦を表わしたものです |
| 染型の唐草 | 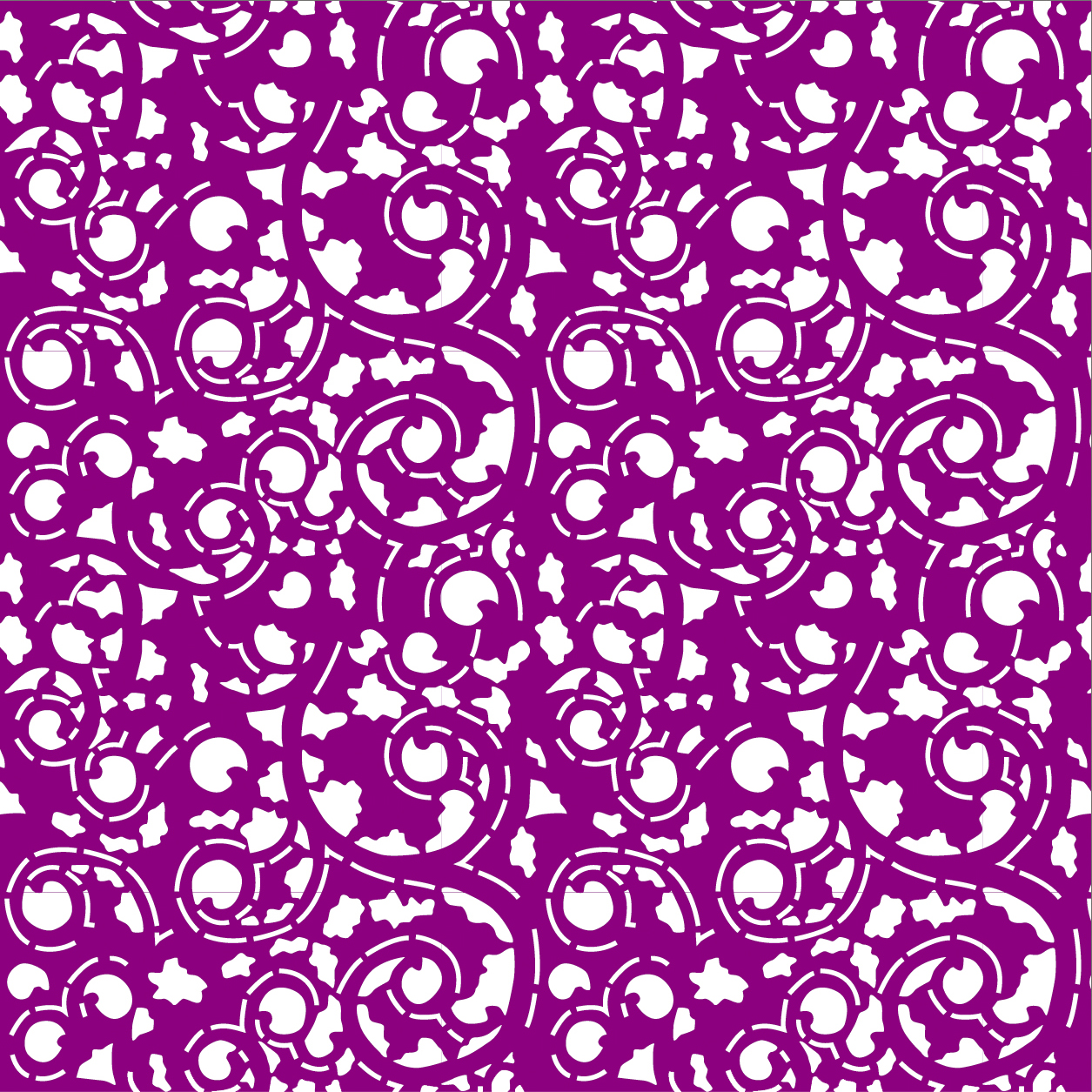 |
染型とは着物の柄を染める際の型紙のことです.この文様は唐草の染型から抜粋したものです |
| 唐草 |  |
現代でもよく使用される,言わば唐草の代表的な文様です |
| 唐花唐草 | 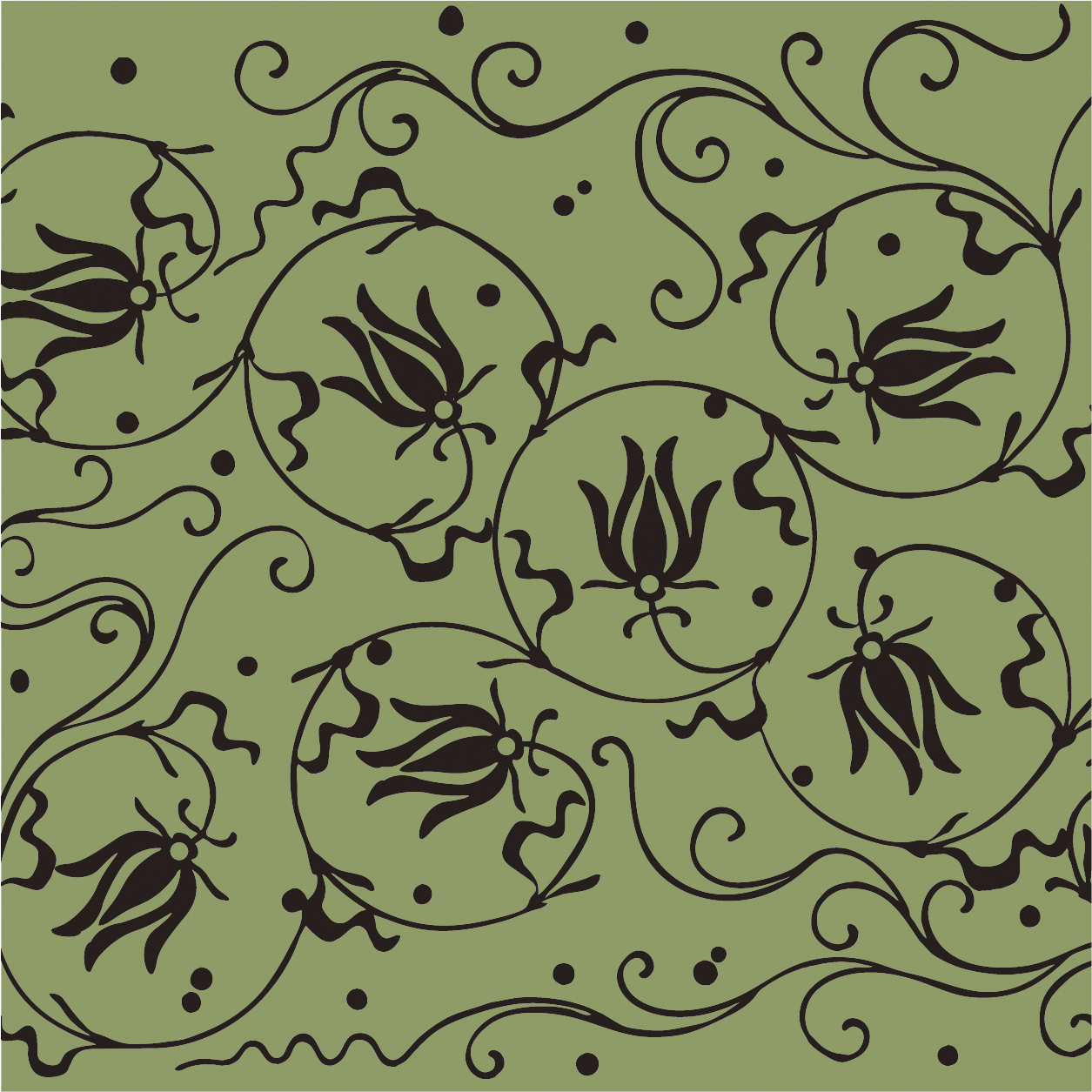 |
想像上で理想化され創造した花を唐花と呼んだそうです |
| 牡丹唐草 |  |
蔓性ではない牡丹と,唐草をあわせて文様にしたものです |
| 千代紙の金魚 | 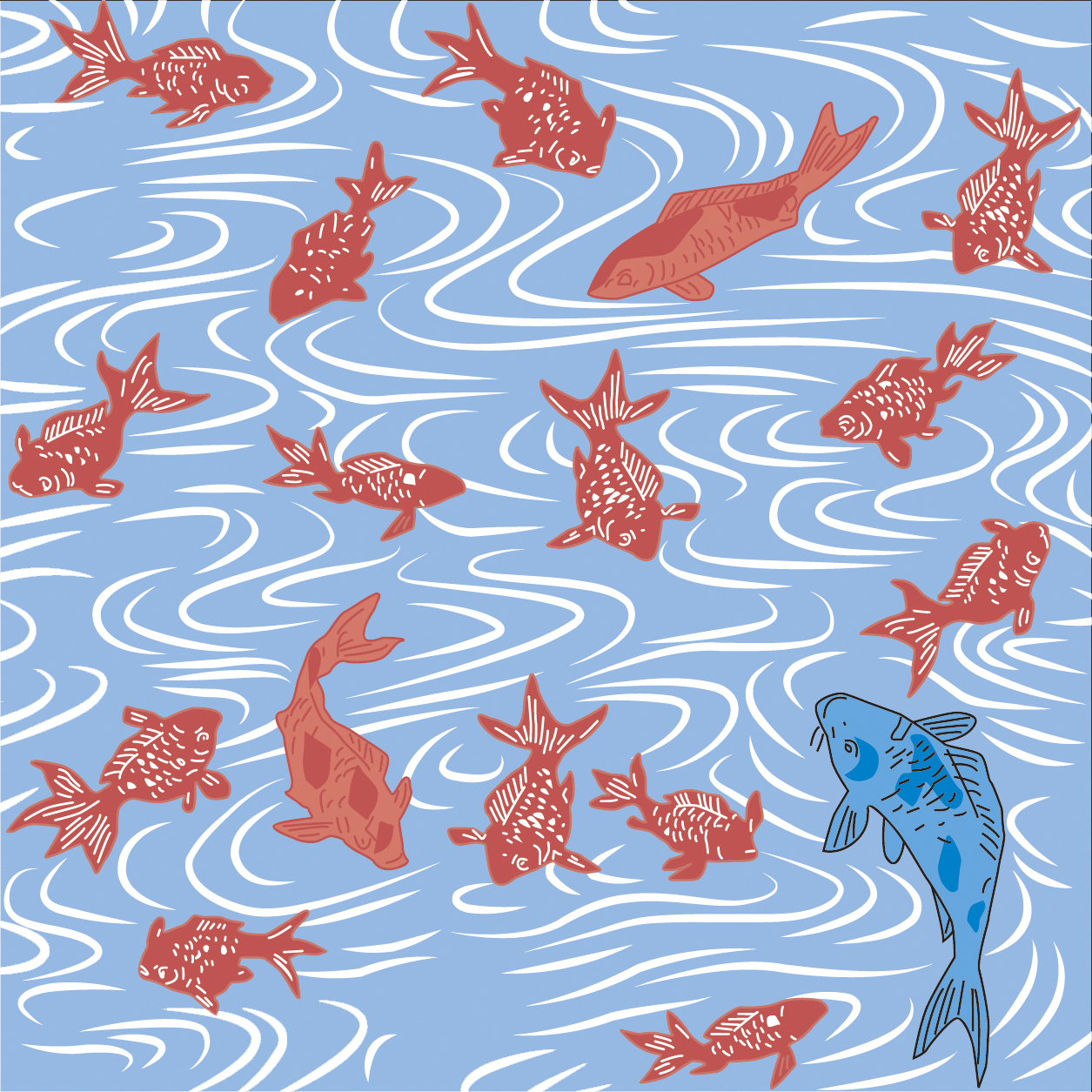 |
水にたゆたう様子を様々に描いた,千代紙名物柄の金魚です |
| 亀甲花菱 | 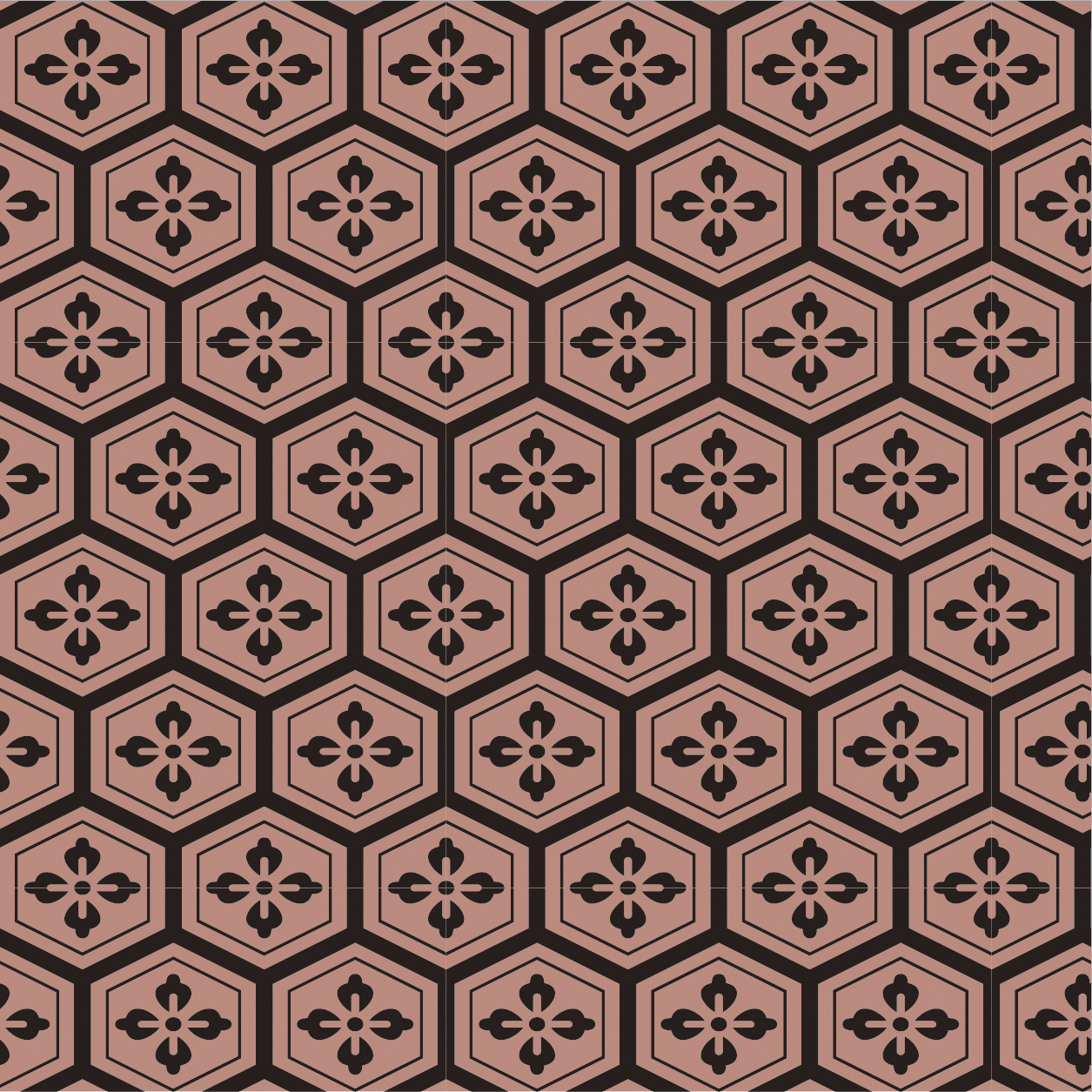 |
亀甲文の中に花菱を入れて用いられた文様です |
| 子持亀甲 | 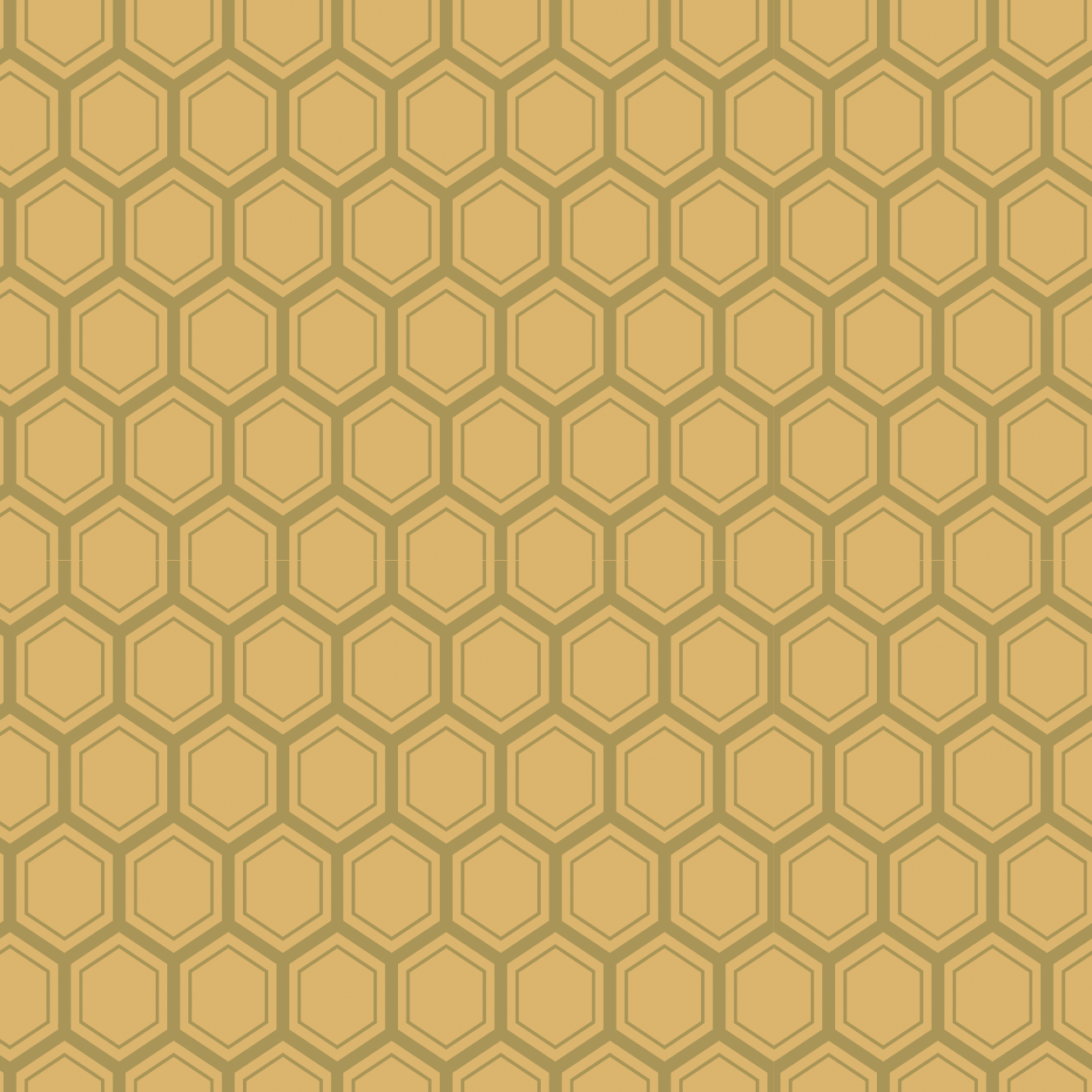 |
亀甲文の中に亀甲文を入れた,入れ子になっている文様です |
| 霰七宝 | 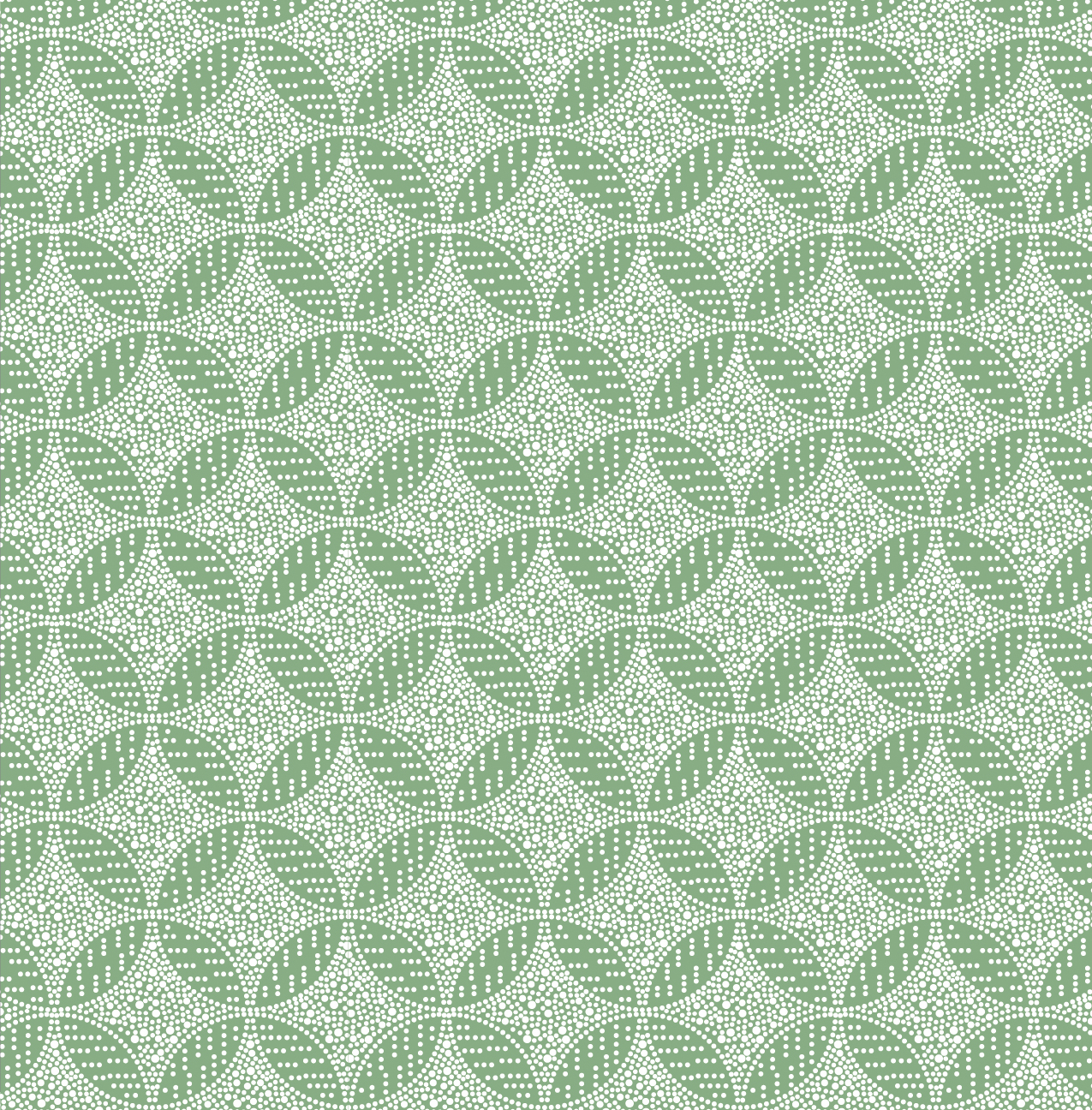 |
円を四分の一ずつ重ねて繋いだ,霞文の文様です |
| 鮫青海波 | 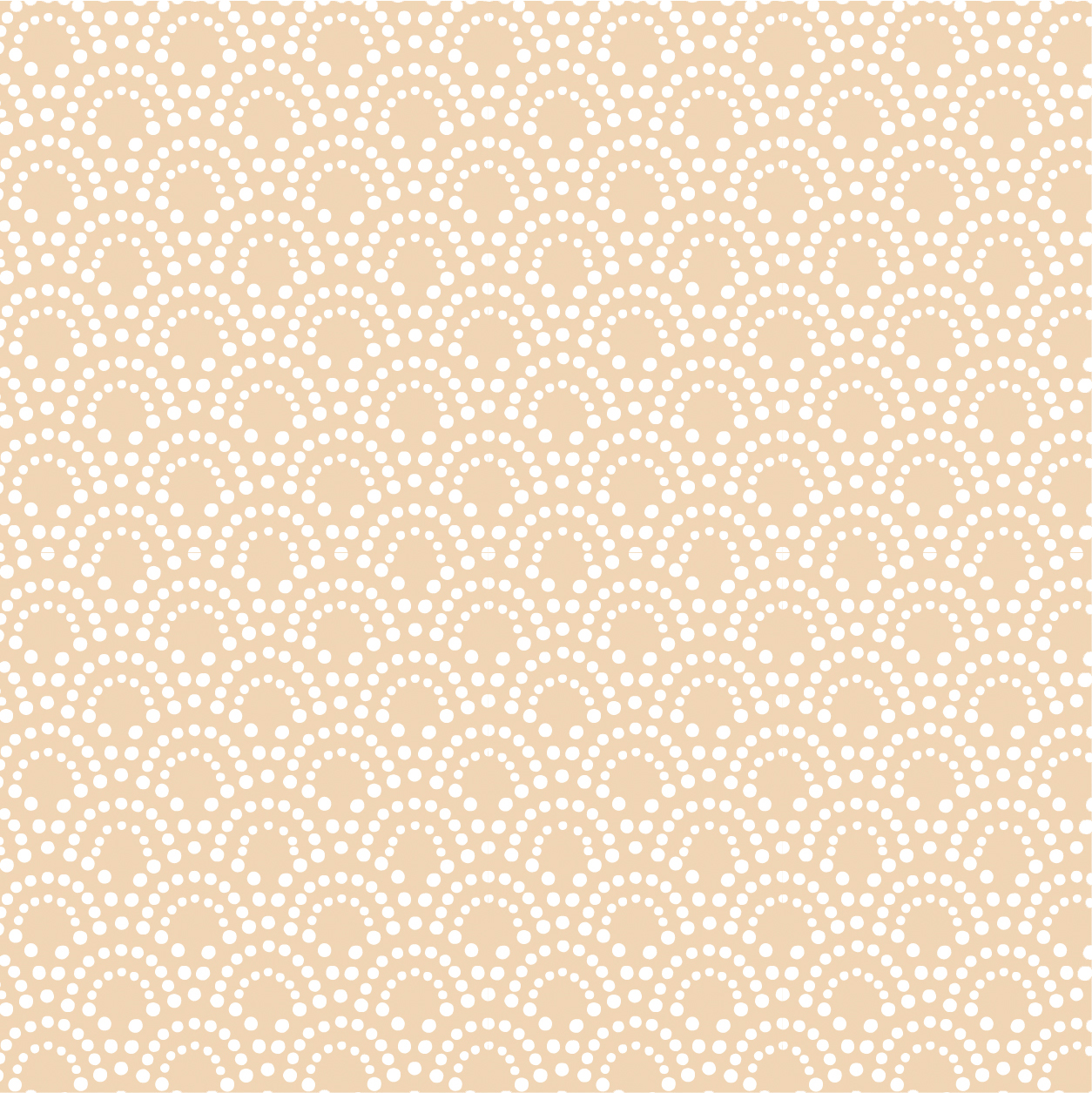 |
鮫小紋で青海波を表わしている文様です |
| 菊青海波 | 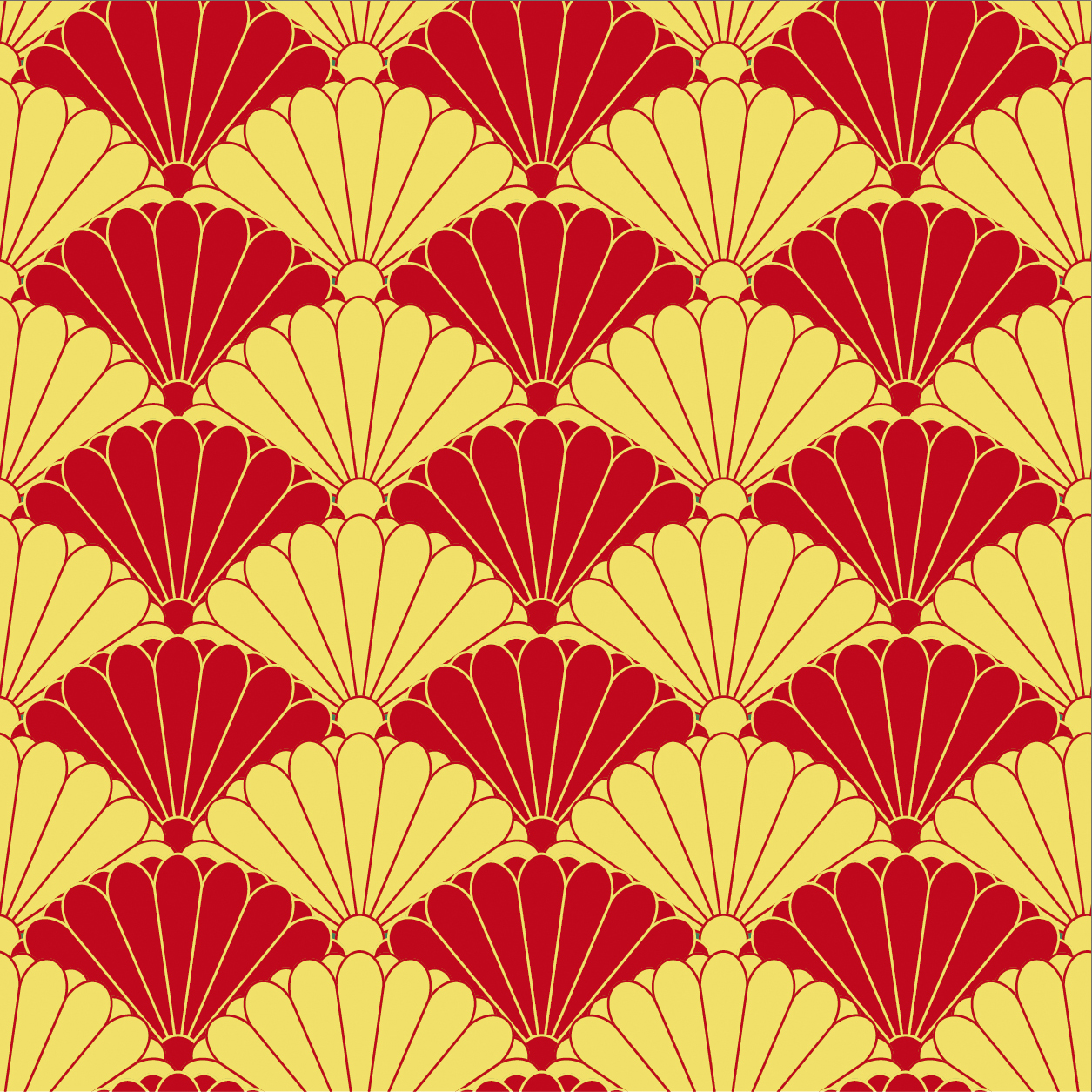 |
菊の花を規則正しく並べ,青海波に見立てて創られた文様です |
| 入子菱 | 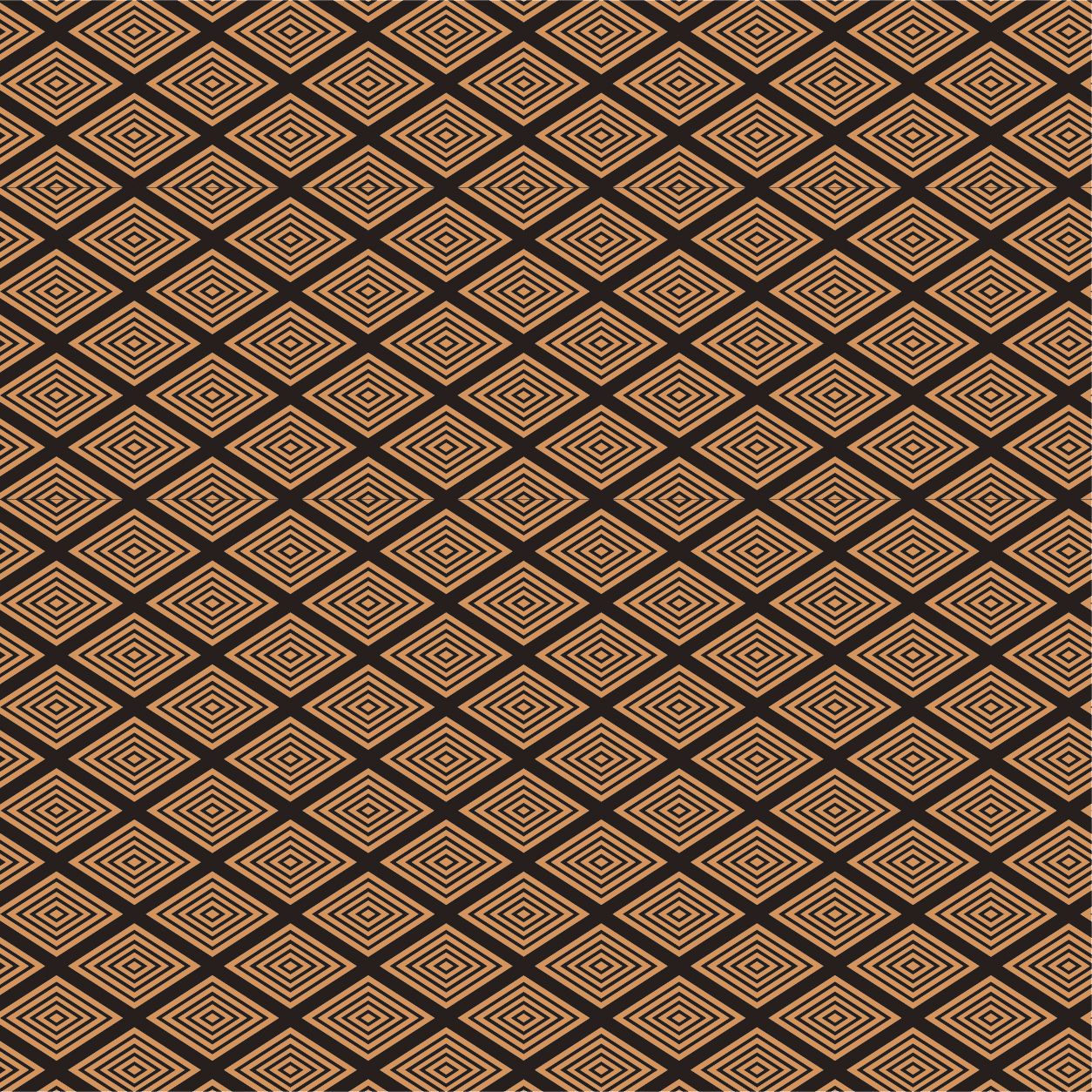 |
菱形の中にさらに菱形を入れて,入れ子にしたものです |
| 四花菱 | 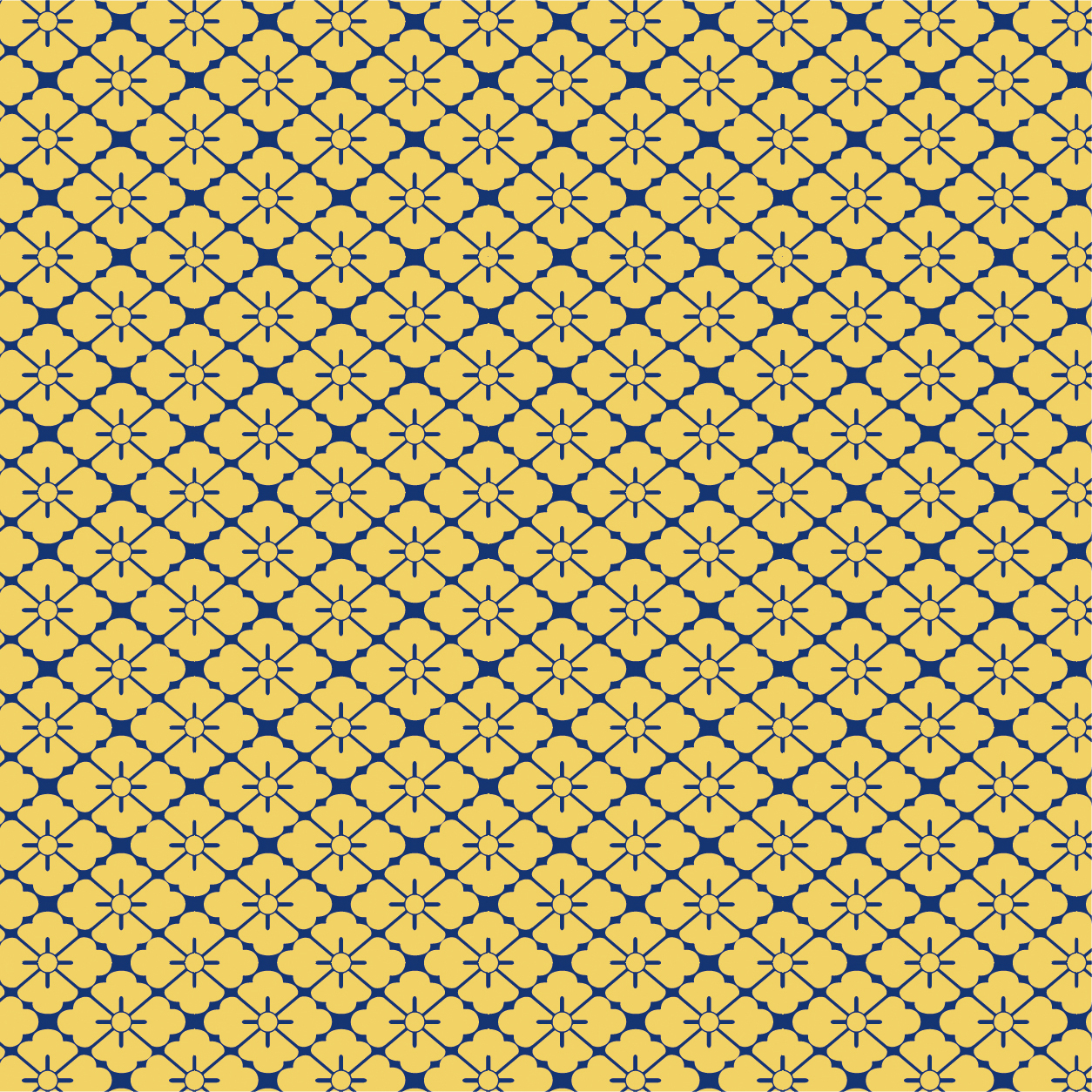 |
花菱を四つ集めて一つの菱にした文様です |
| 葡萄立涌 | 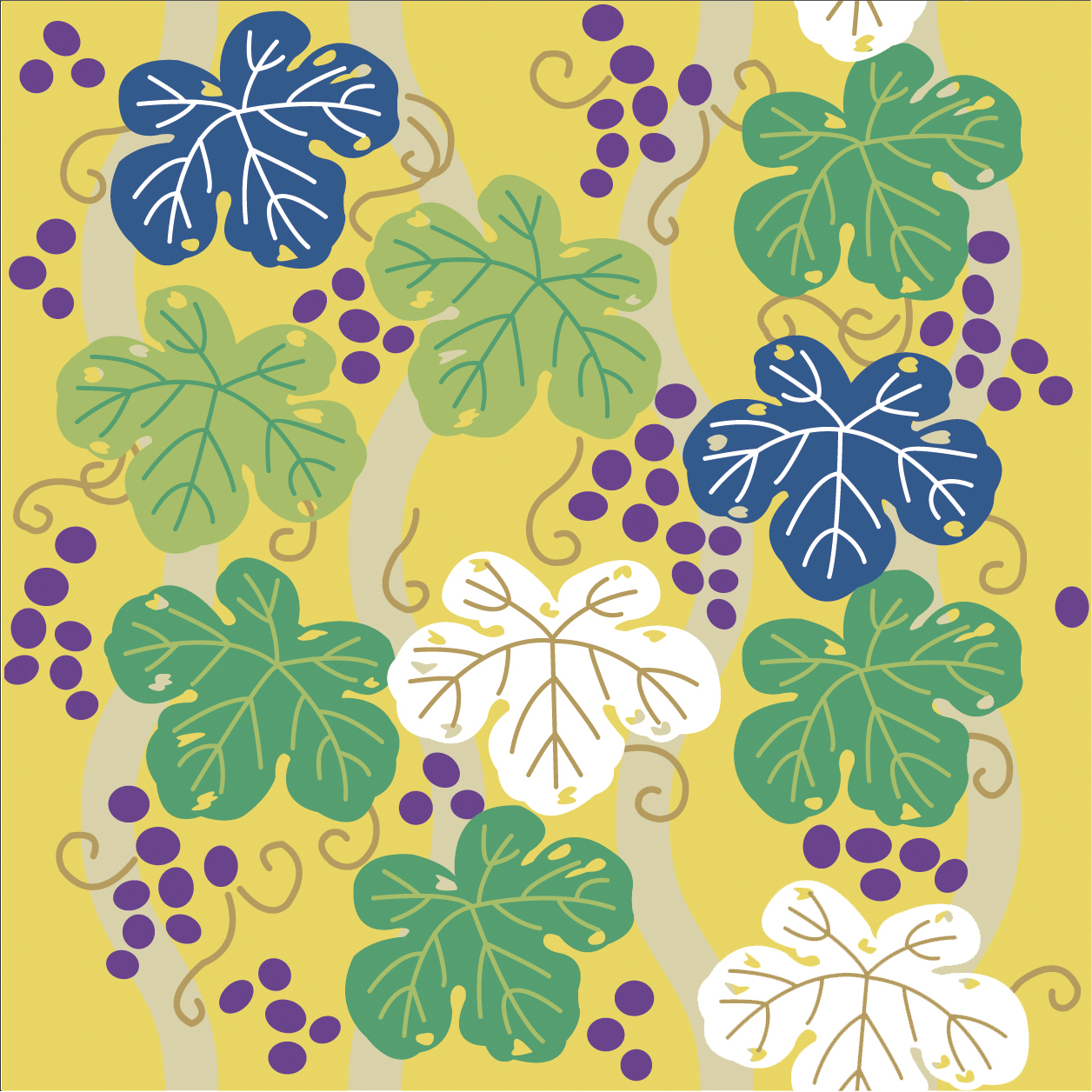 |
この文様は,立涌の中に葡萄の葉と実が描かれたものです |
| 波立涌 | 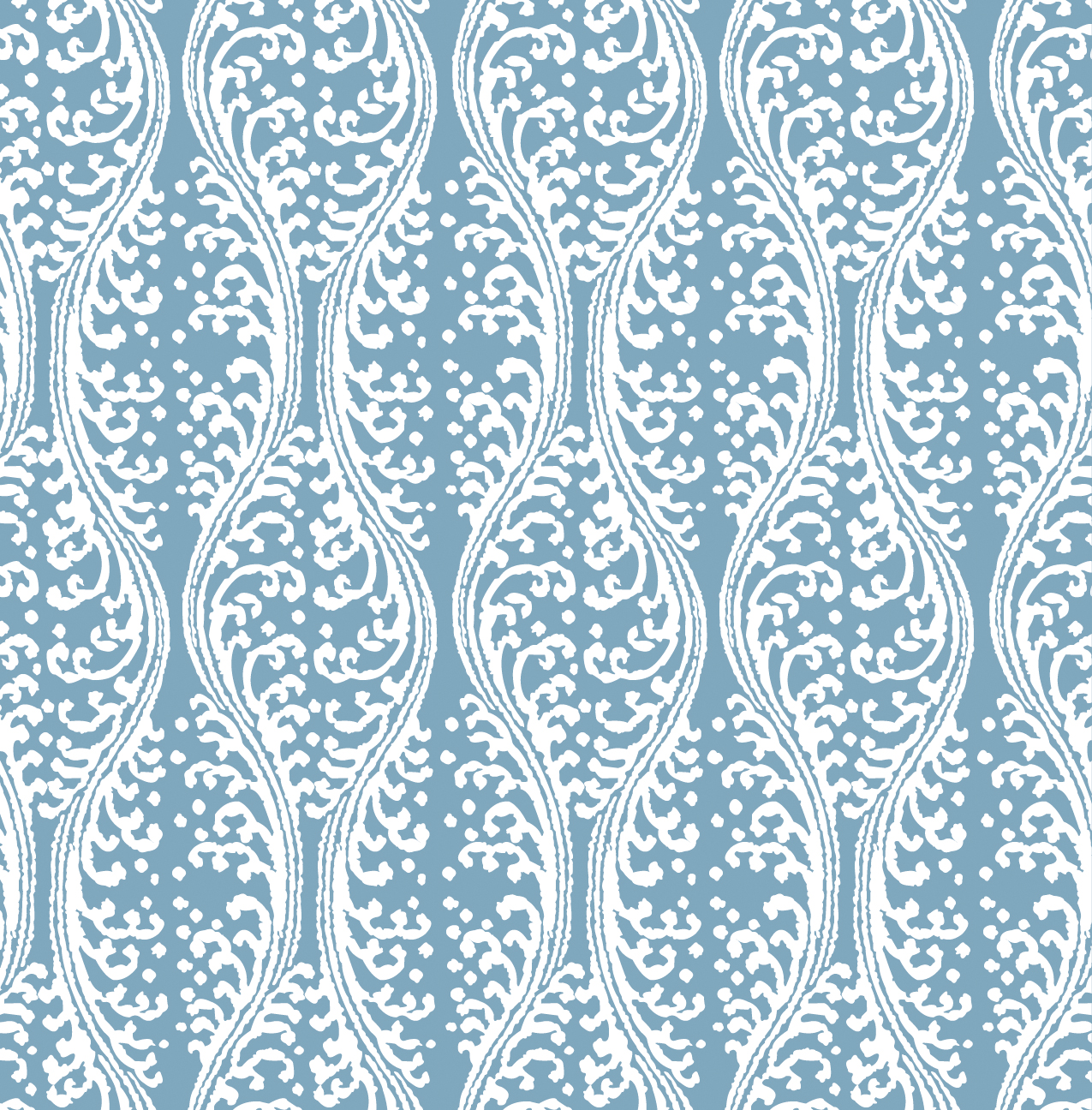 |
水しぶきの上がった波濤を,立涌にみたてて文様にしたものです |
| 網目 | 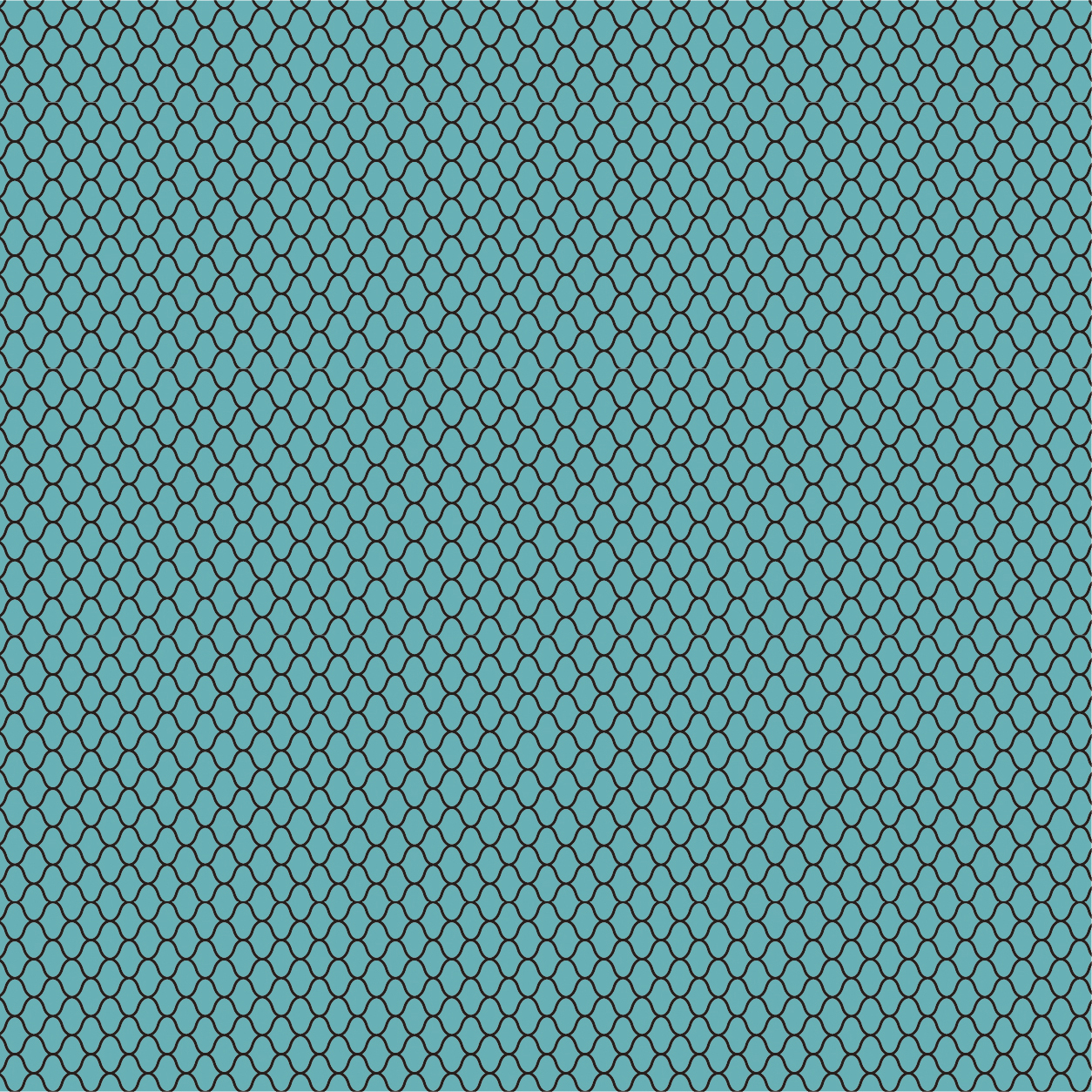 |
漁網の目の文様で,海老や蛸,魚とともに,大漁文としても用いられました |
| 桧垣・網代 | 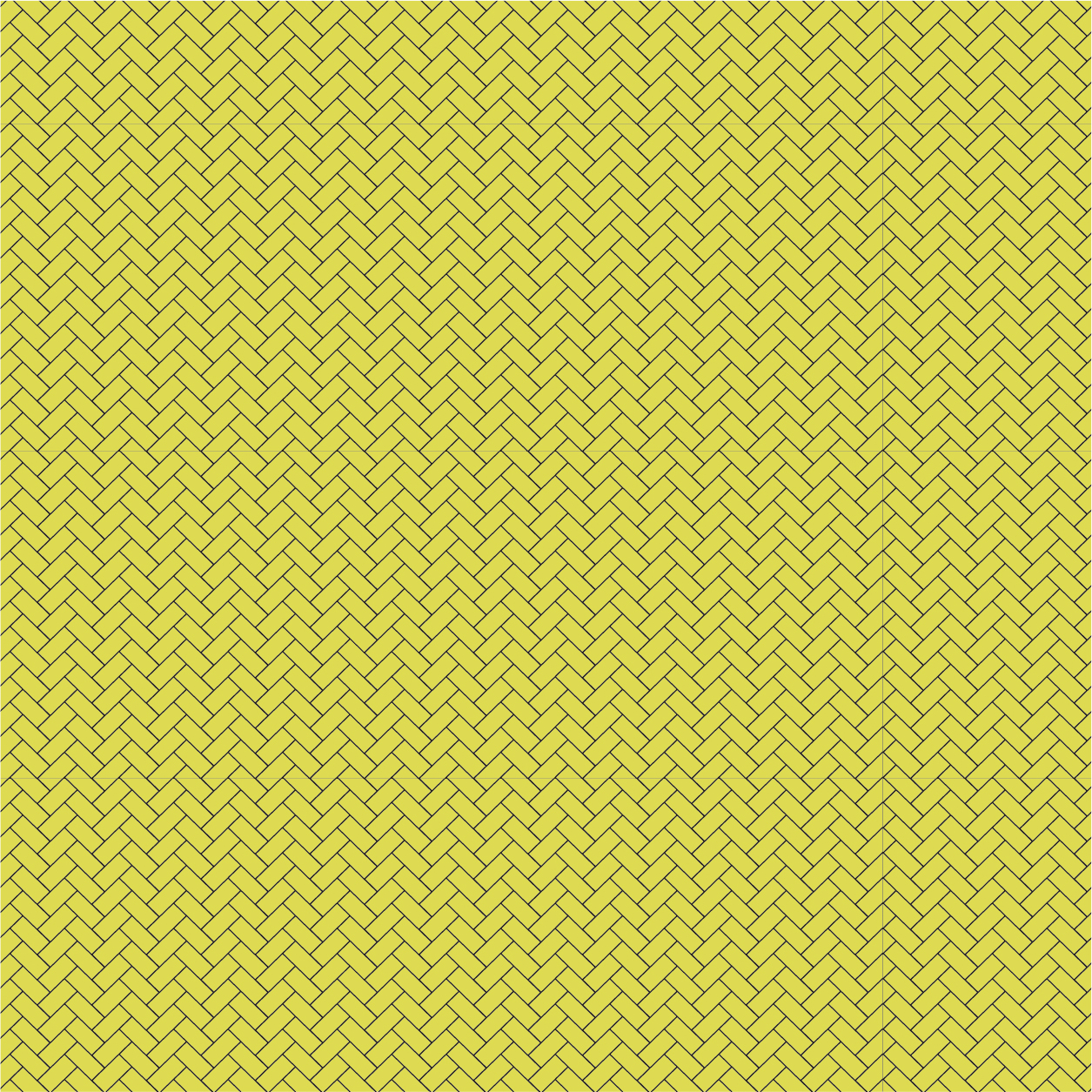 |
檜などの薄板で組まれた垣根や羽目板を文様にしたものです |
| 立涌の小紋 | 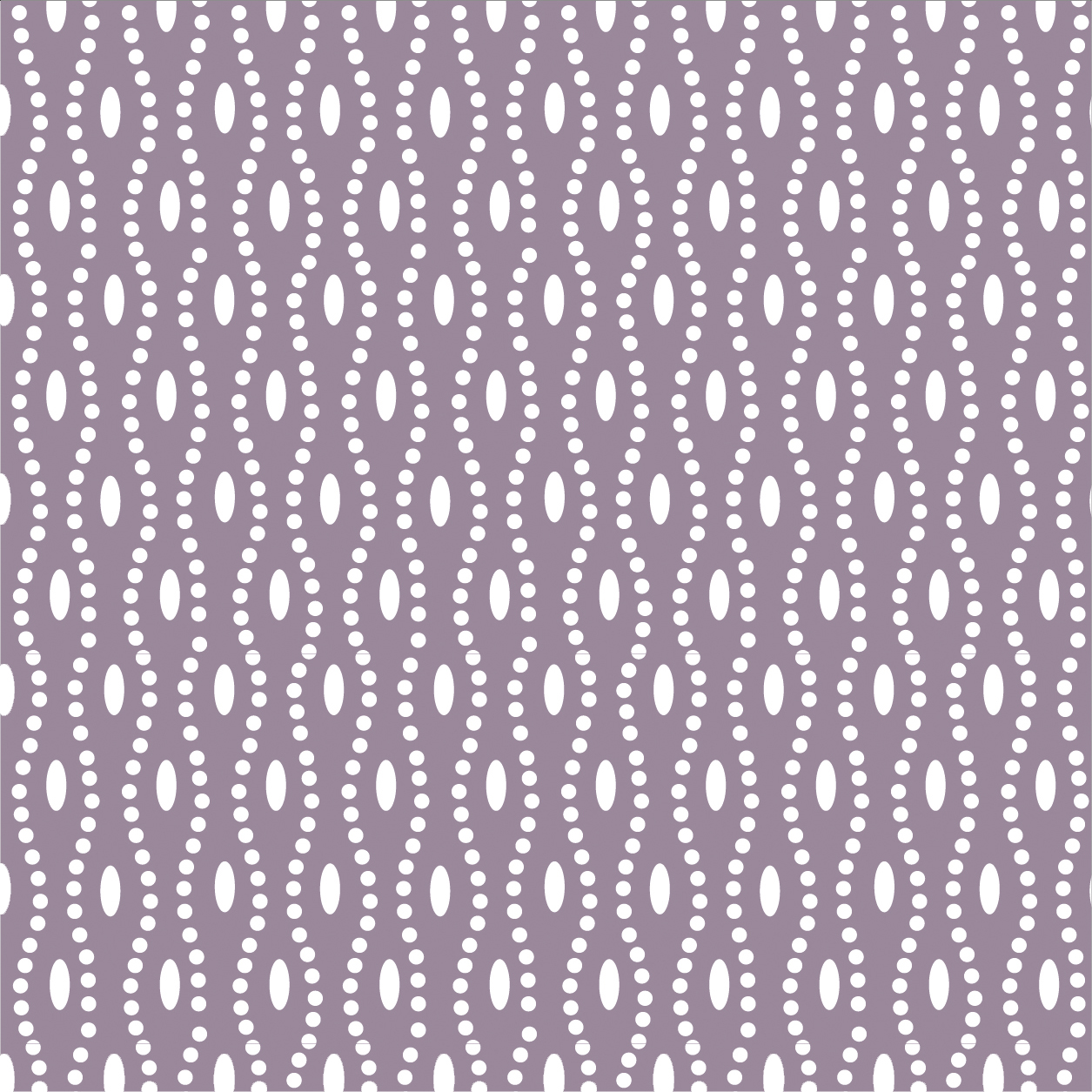 |
立涌を小紋で表わしたものです |
| 鮫小紋 | 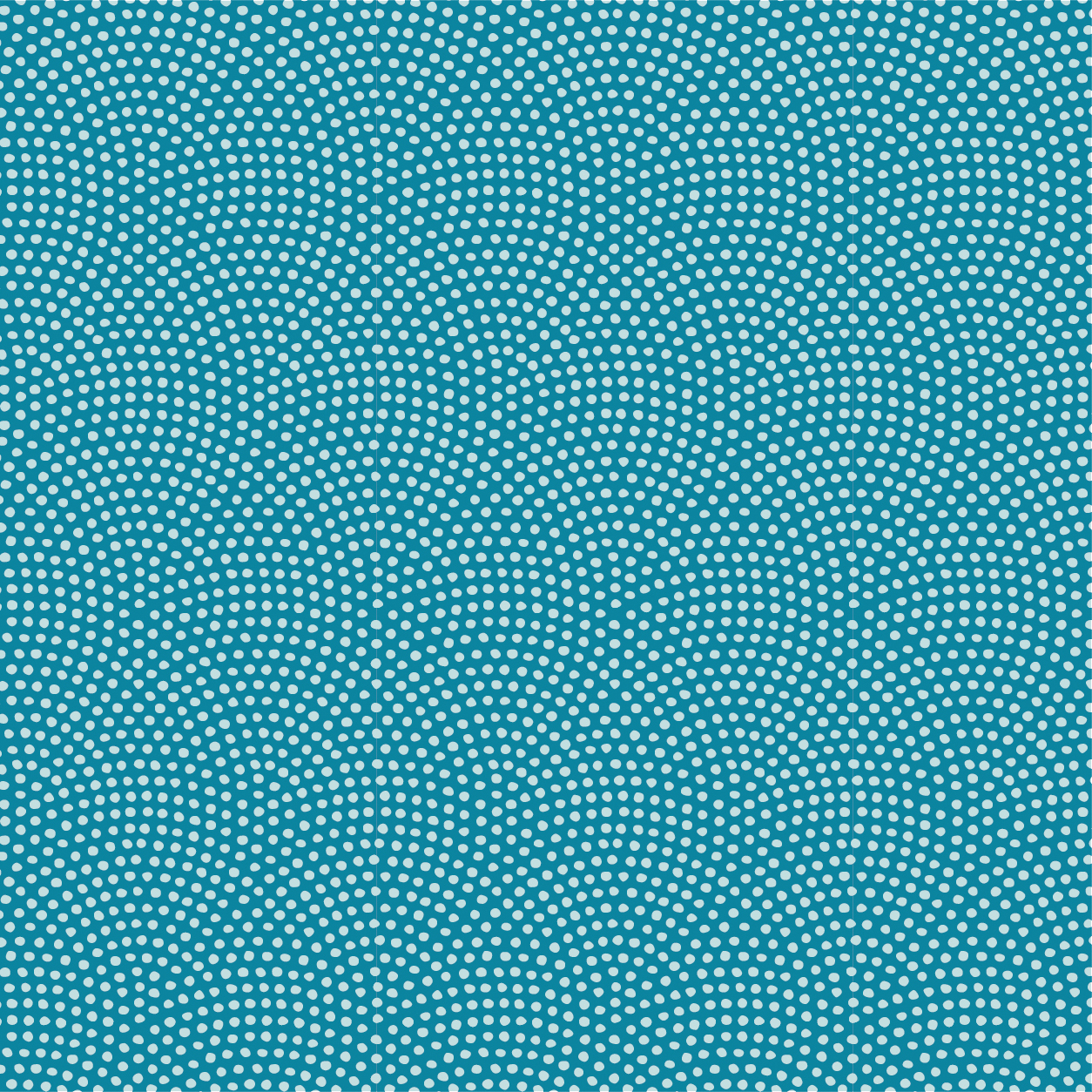 |
鮫の肌に似ていることより名がついた,江戸小紋の代表的なものです |
| 豆絞り | 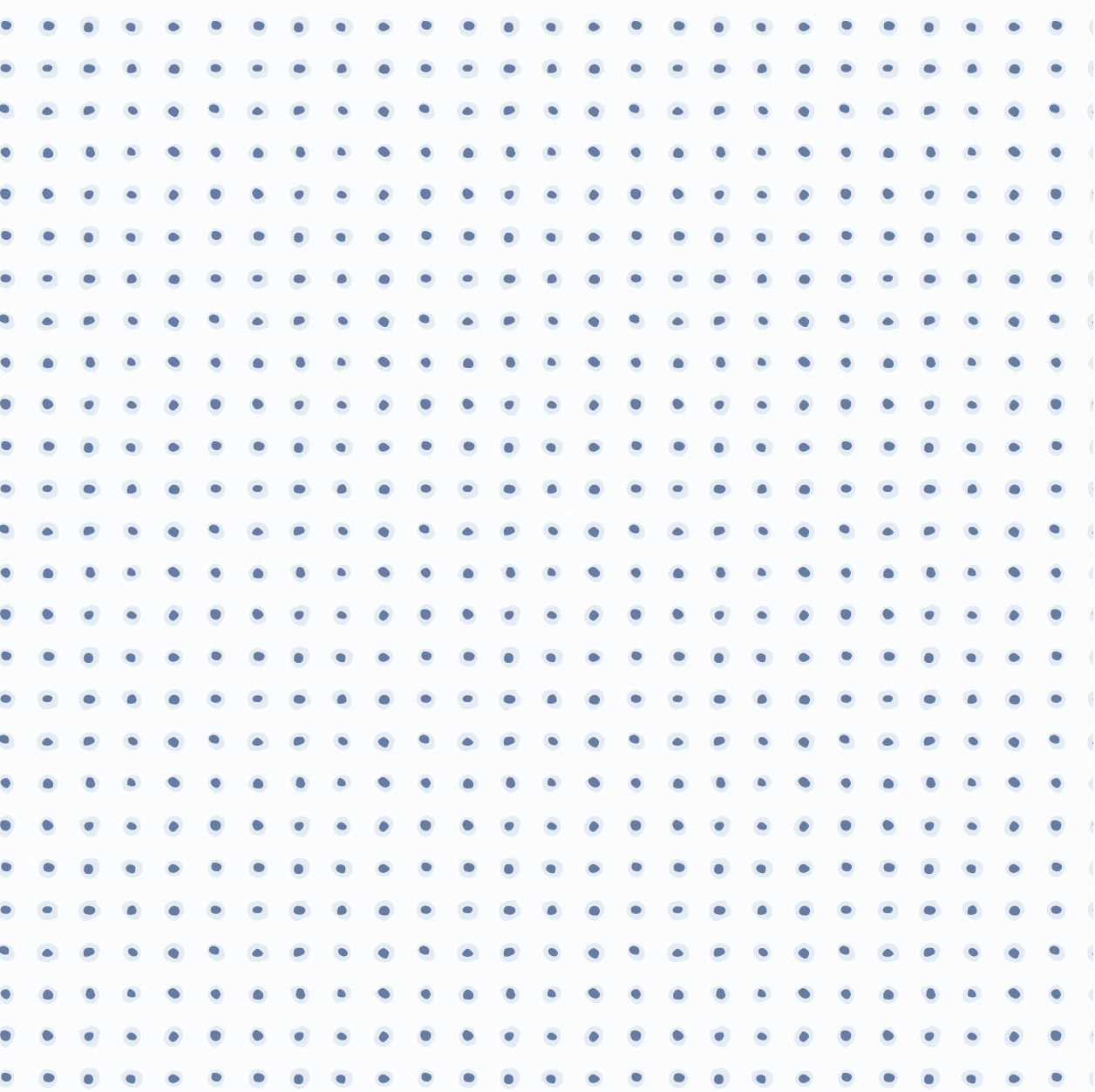 |
豆粒ほどの小さい円を一面に染めだした絞り染めで,手拭などに使います |
| 小紋 | 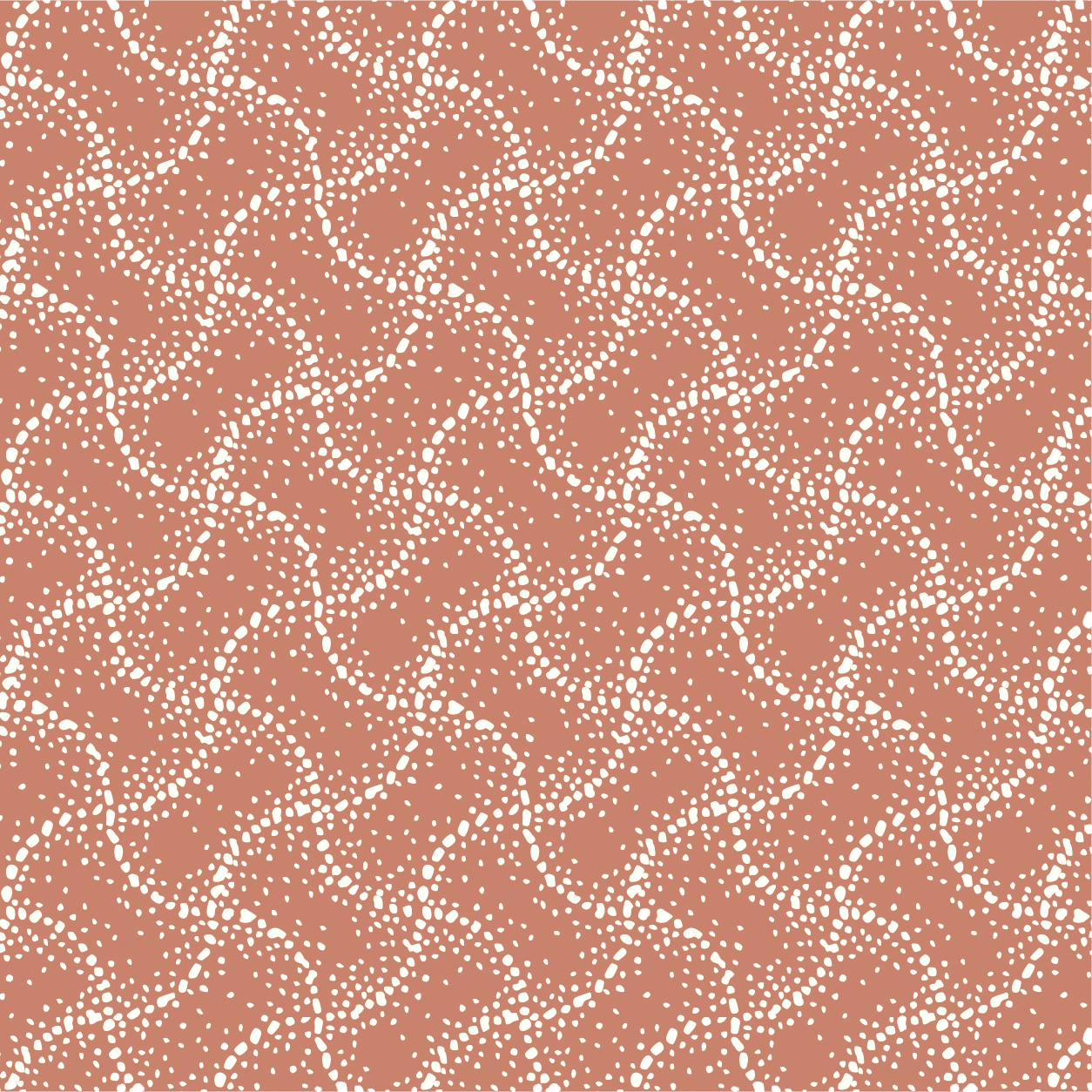 |
|
| 翁格子 | 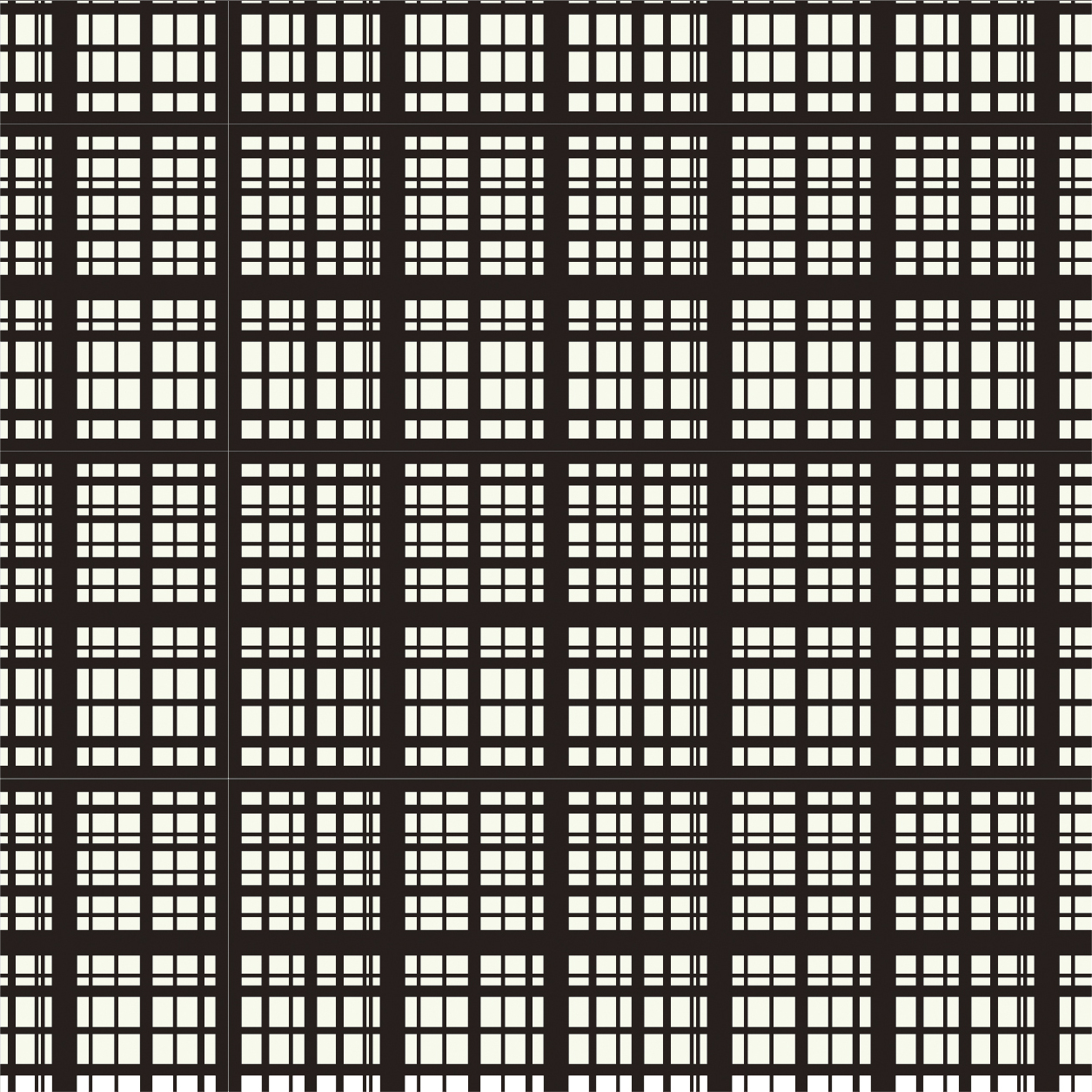 |
大きな格子の中に小さな格子を抱えた様を,翁と大勢の孫に見立てた格子です |
| 一崩し | 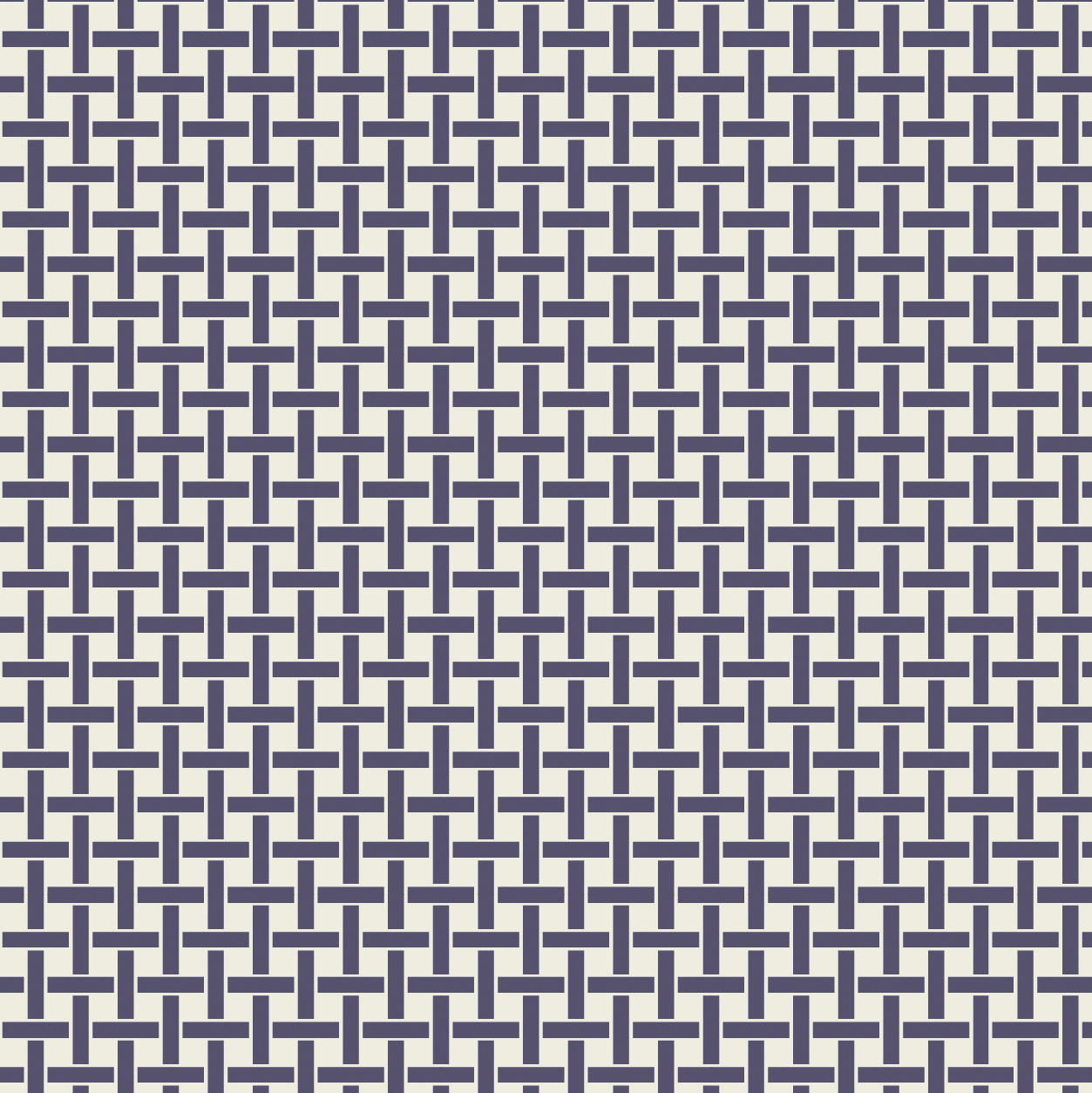 |
これは割付文様の一種で,網代組とも言われています |
| 絣の縞 | 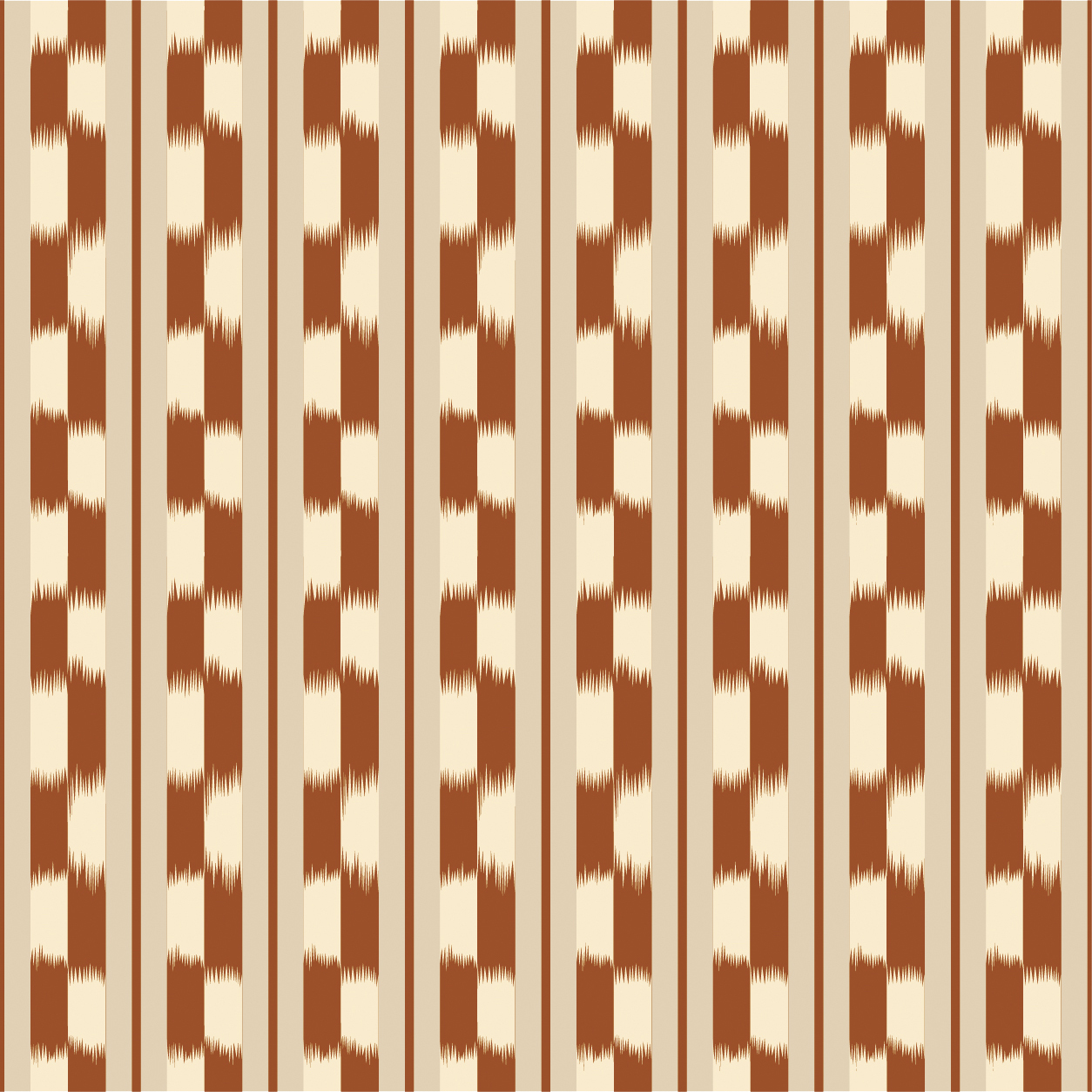 |
部分的に染色した糸を縦横に織り,染め残った部分との差で表わされ,織りのものもあります |
| 釘抜繋ぎ |  |
正方形の中央に小さく正方形を入れ釘抜きの座金を表わしています |
| 念じ麻の葉 | 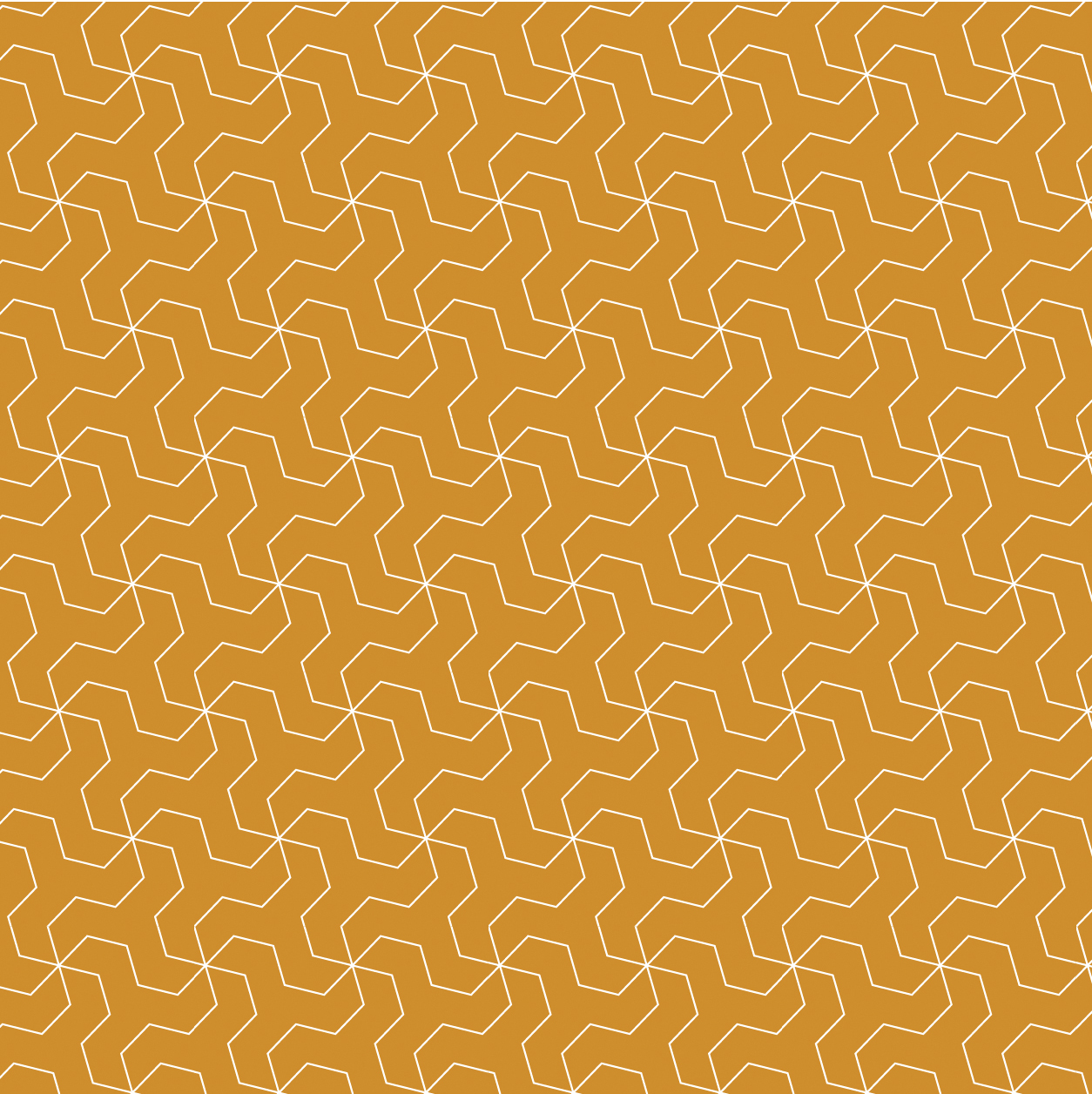 |
麻の葉の中心が捻じれたように表わされた麻の葉の文様です |
| 麻の葉 | 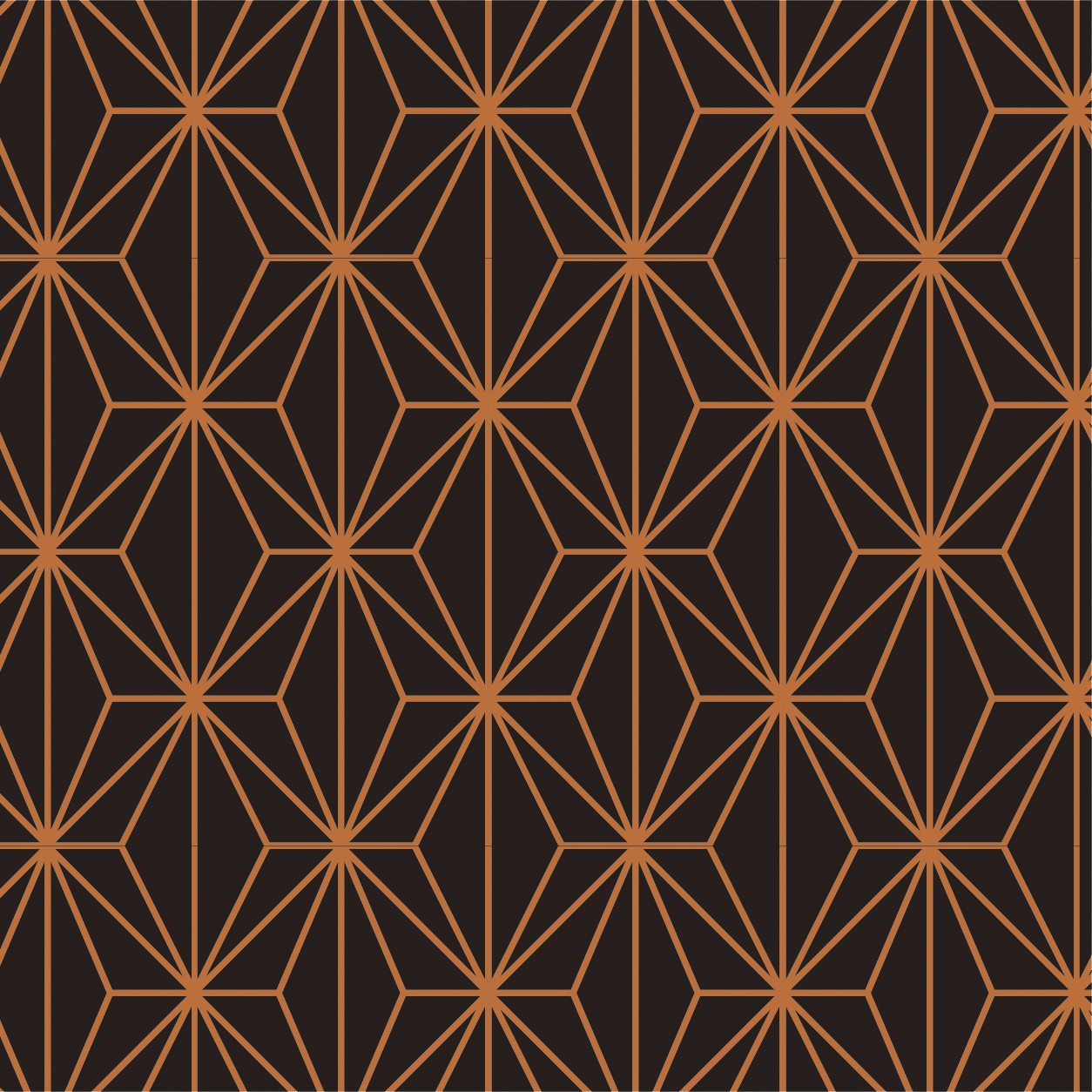 |
こちらも,現代でもよく見かけることのできる文様です |
| 石畳(市松) | 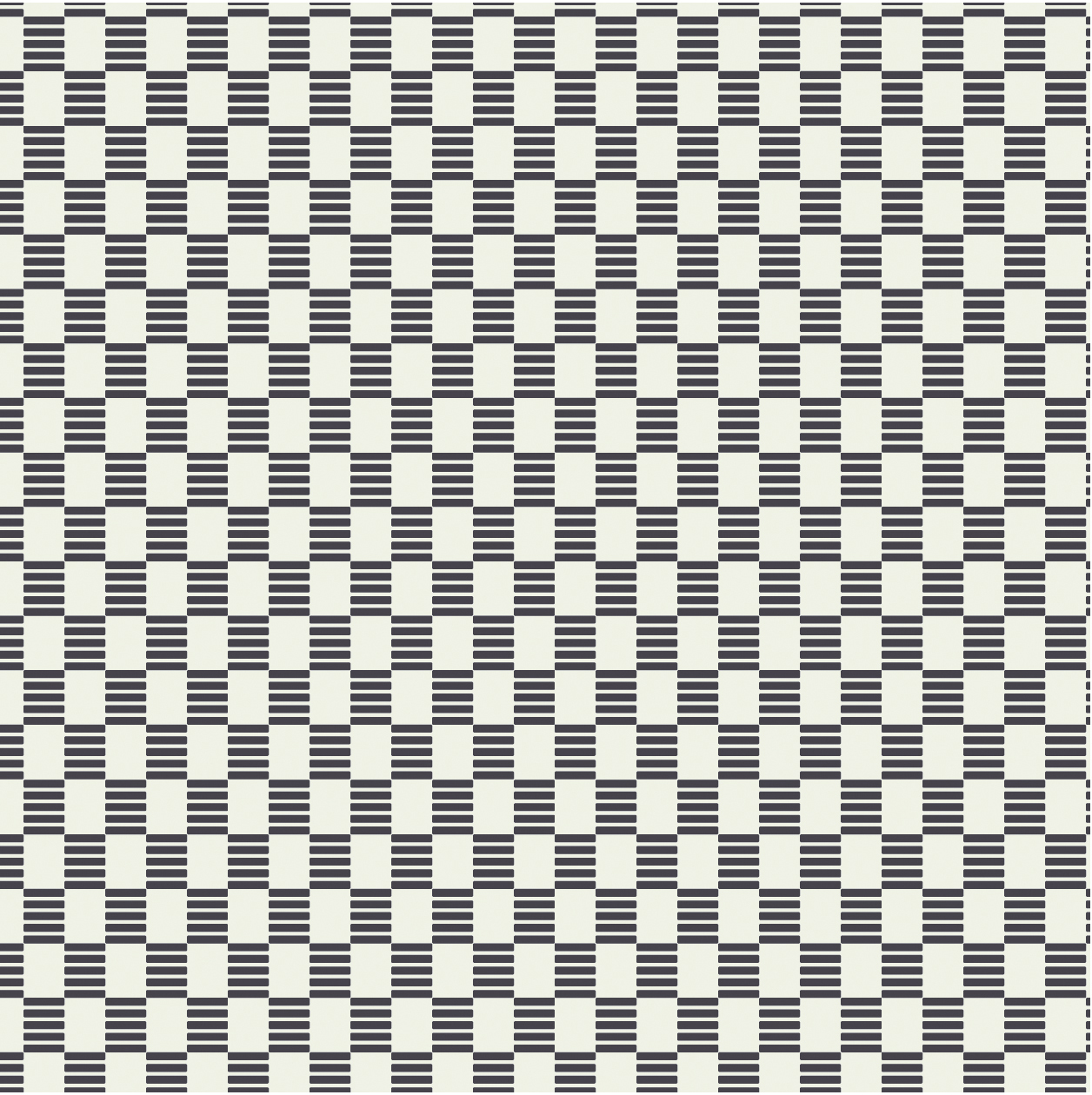 |
別名「市松文様」です.石畳の細かいものは霰と呼ばれています |
| 網代 | 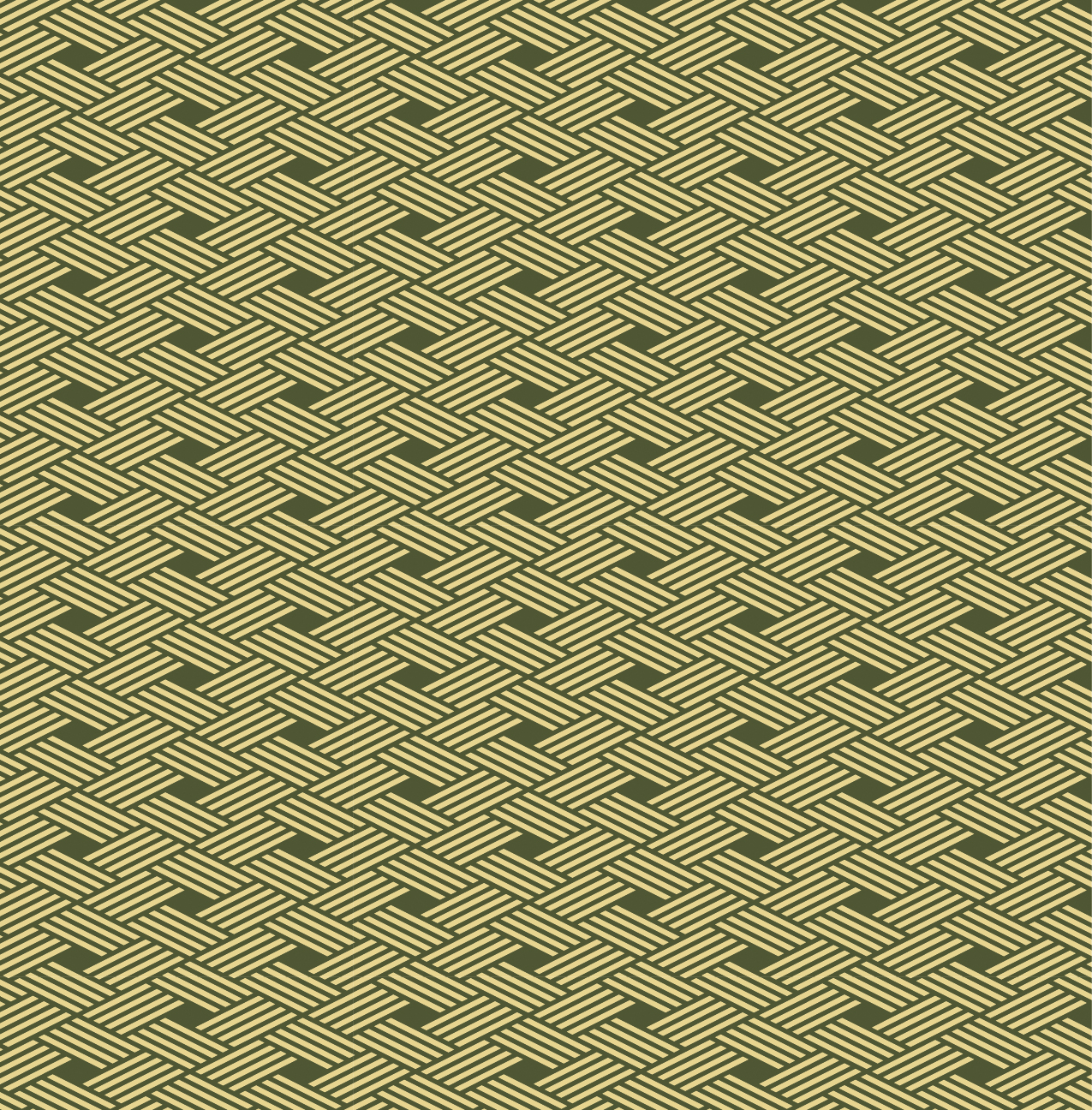 |
竹・葦・檜皮などを薄く削っ編んだ,網代に由来した文様です |
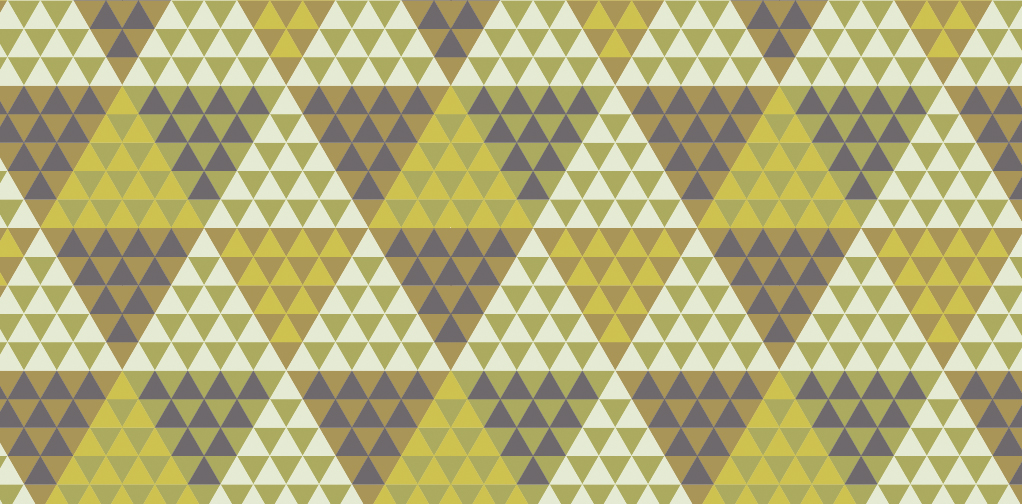 |
||
| 素襖の傘散らし | 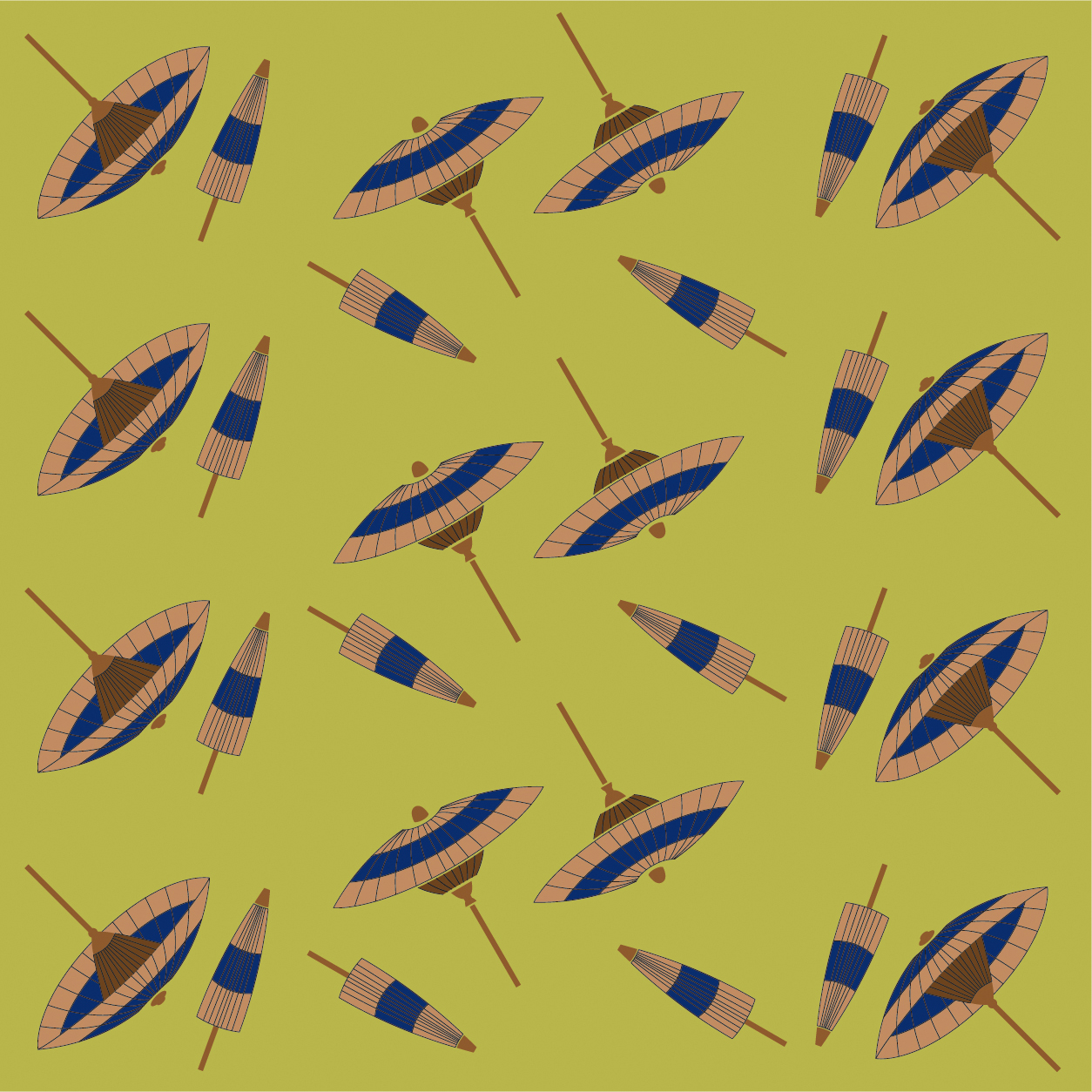 |
傘を一面に散らした文様で,これは,素襖に描かれたものです |
| 団扇散らし | 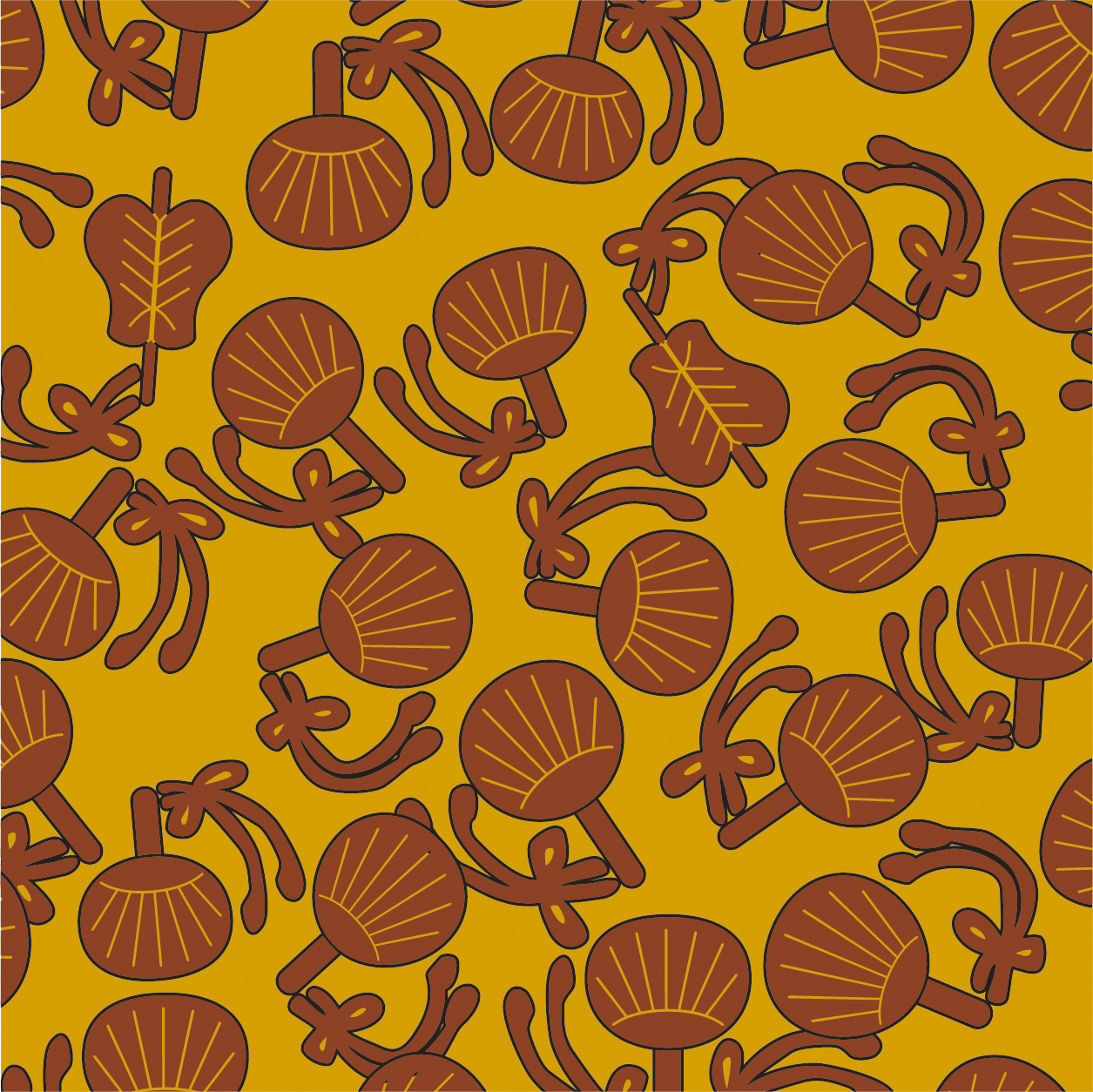 |
団扇を一面に散らした様子を文様にしたものです |