文様
名称
解説
コメント
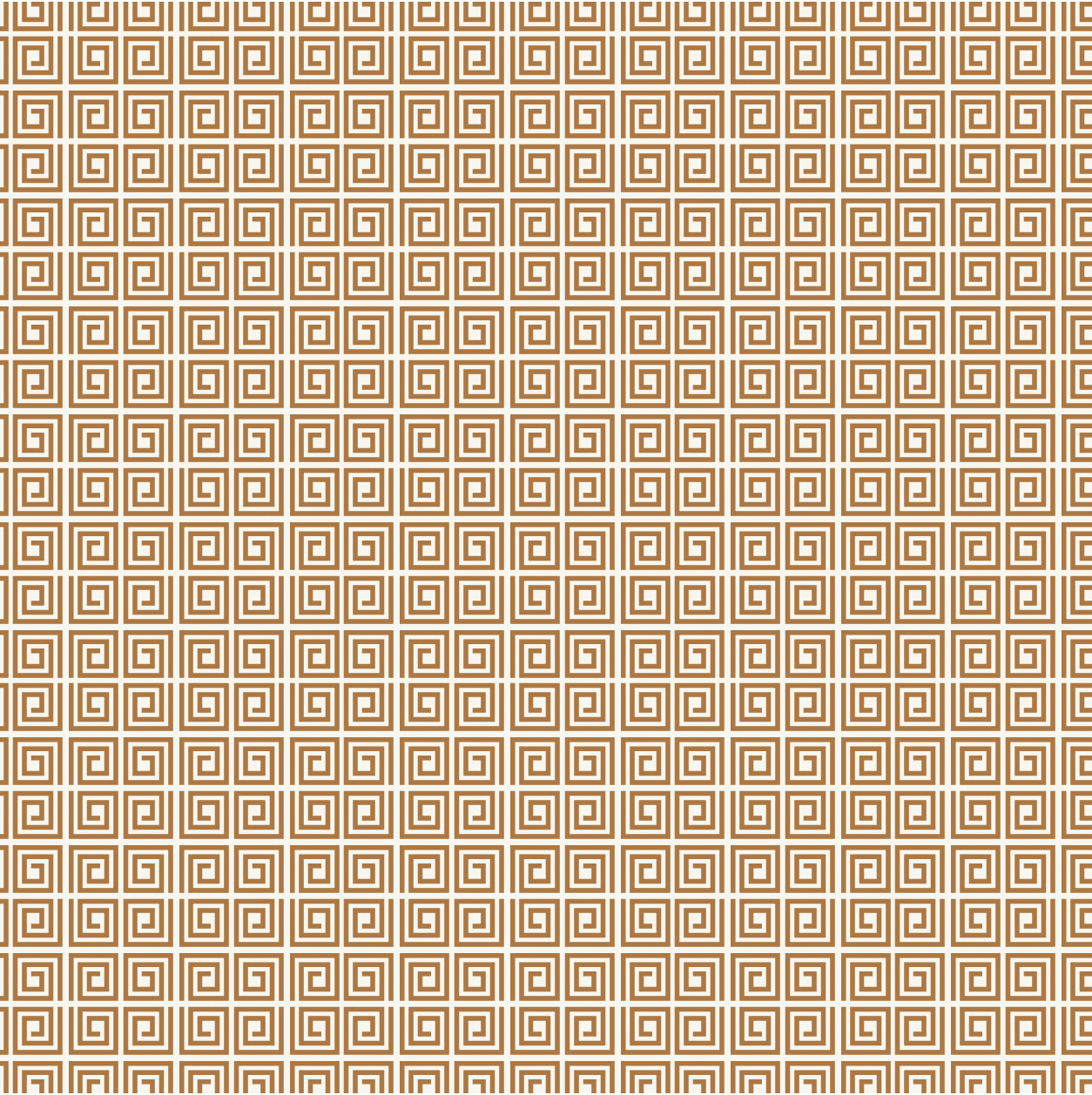
雷文
渦巻形が幾何学的な形になった雷文。
ラーメンの器に描かれていそうな文様がぎっしりと並んでいて、どこか中華的な印象をうけた。
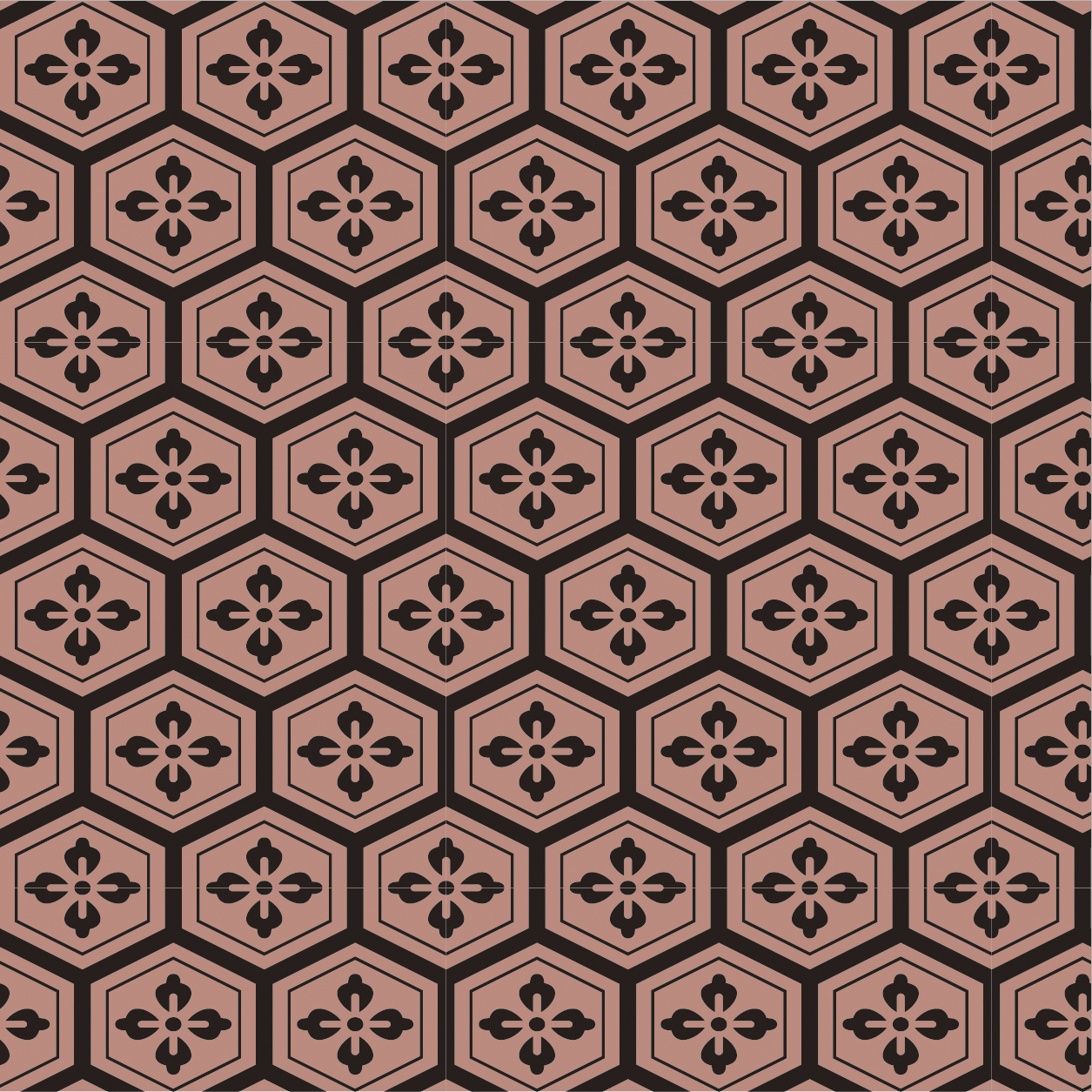
亀甲花菱
亀甲文の中に花菱を入れて用いられた文様。
花の描かれた亀甲文が並んでいる様に、豪華な印象を受けた。お弁当の重箱を包む風呂敷に合いそう。
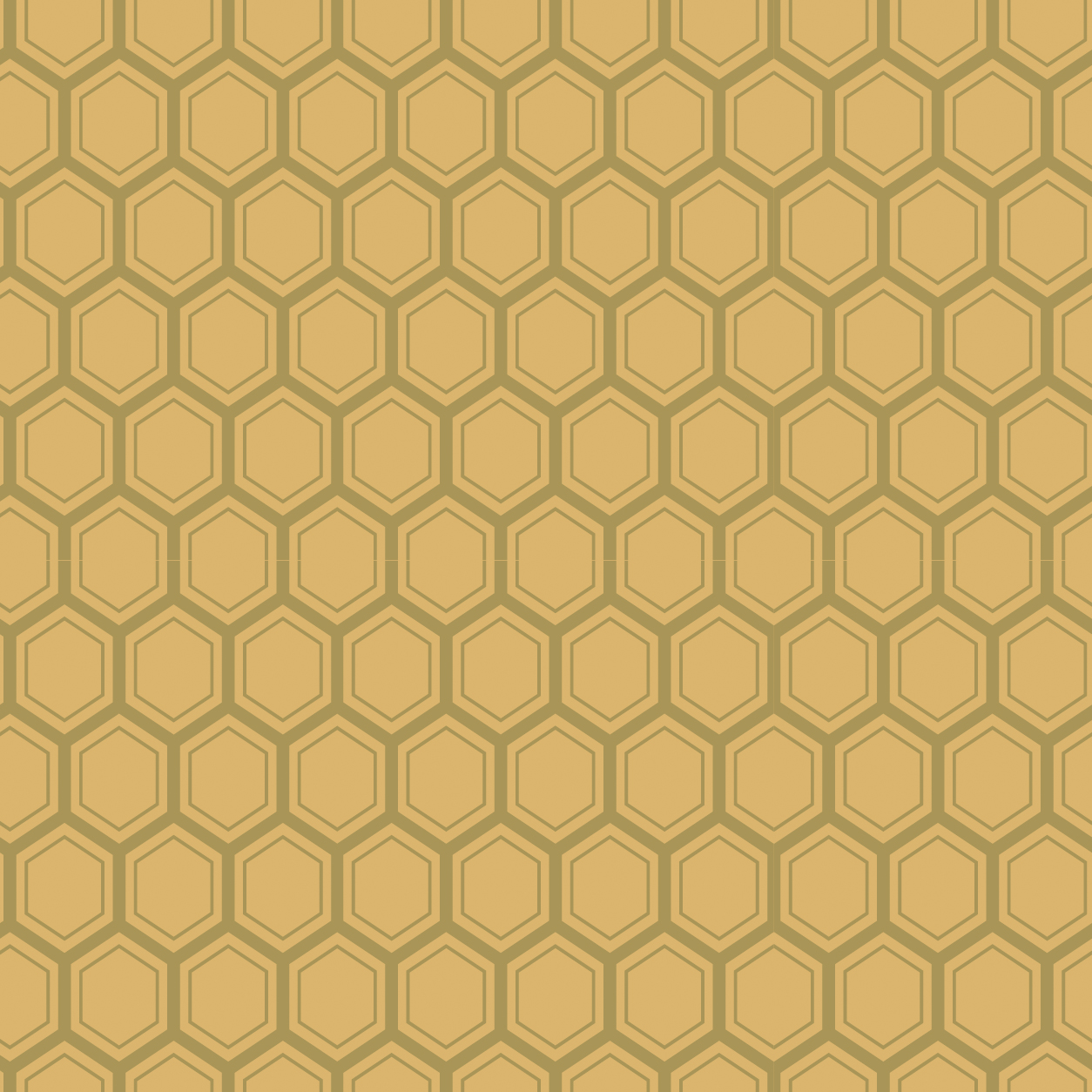
子持ち亀甲
亀甲文の中に亀甲文を入れた文様。
お金持ちが持っていそうなイメージがある。
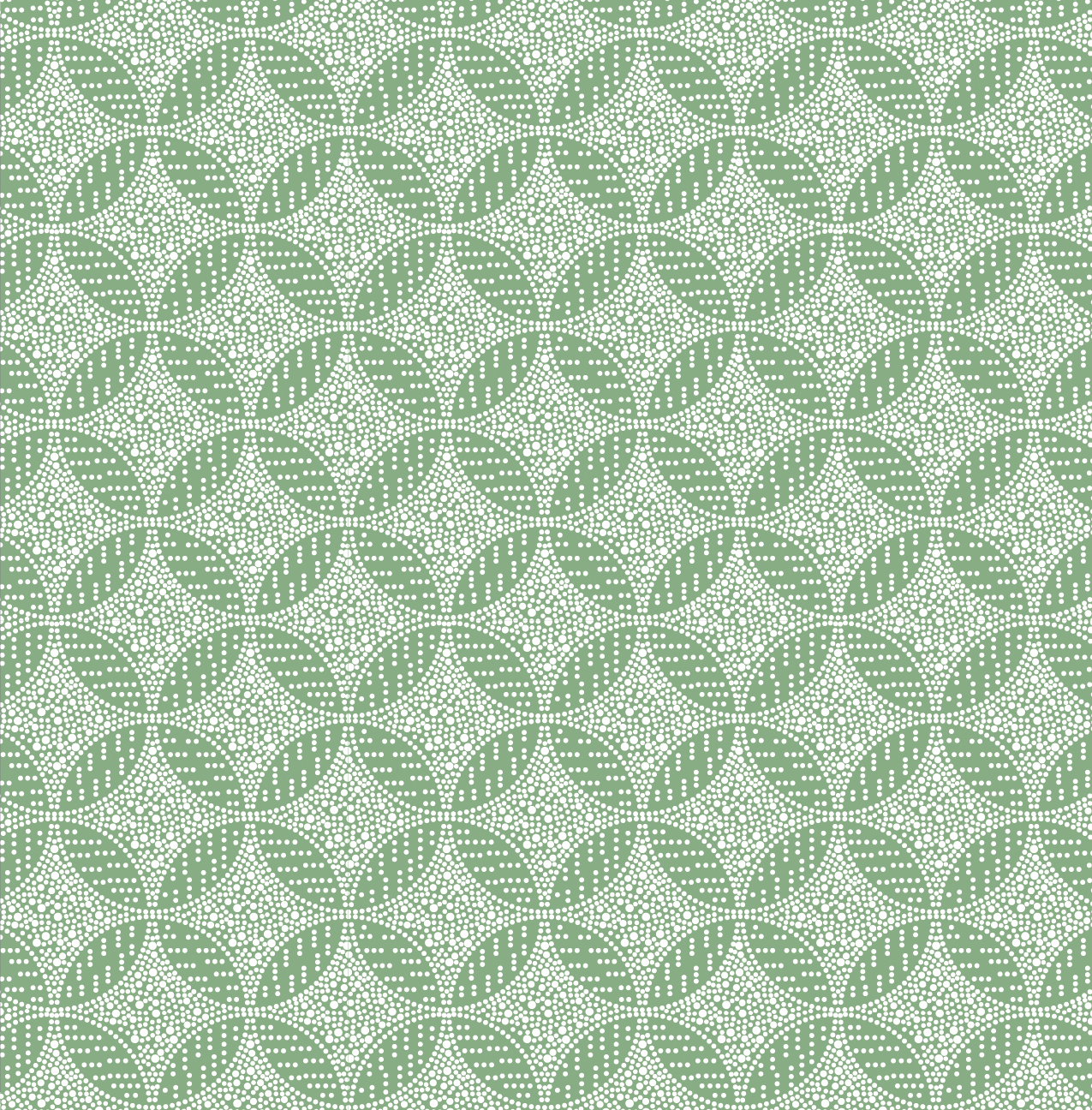
霰七宝
円を四分の一ずつ重ねて繋いだ、霞文の文様。
円が重なっていない部分の点模様が細かく、いかにも霞を模して描かれた文様だと思う。
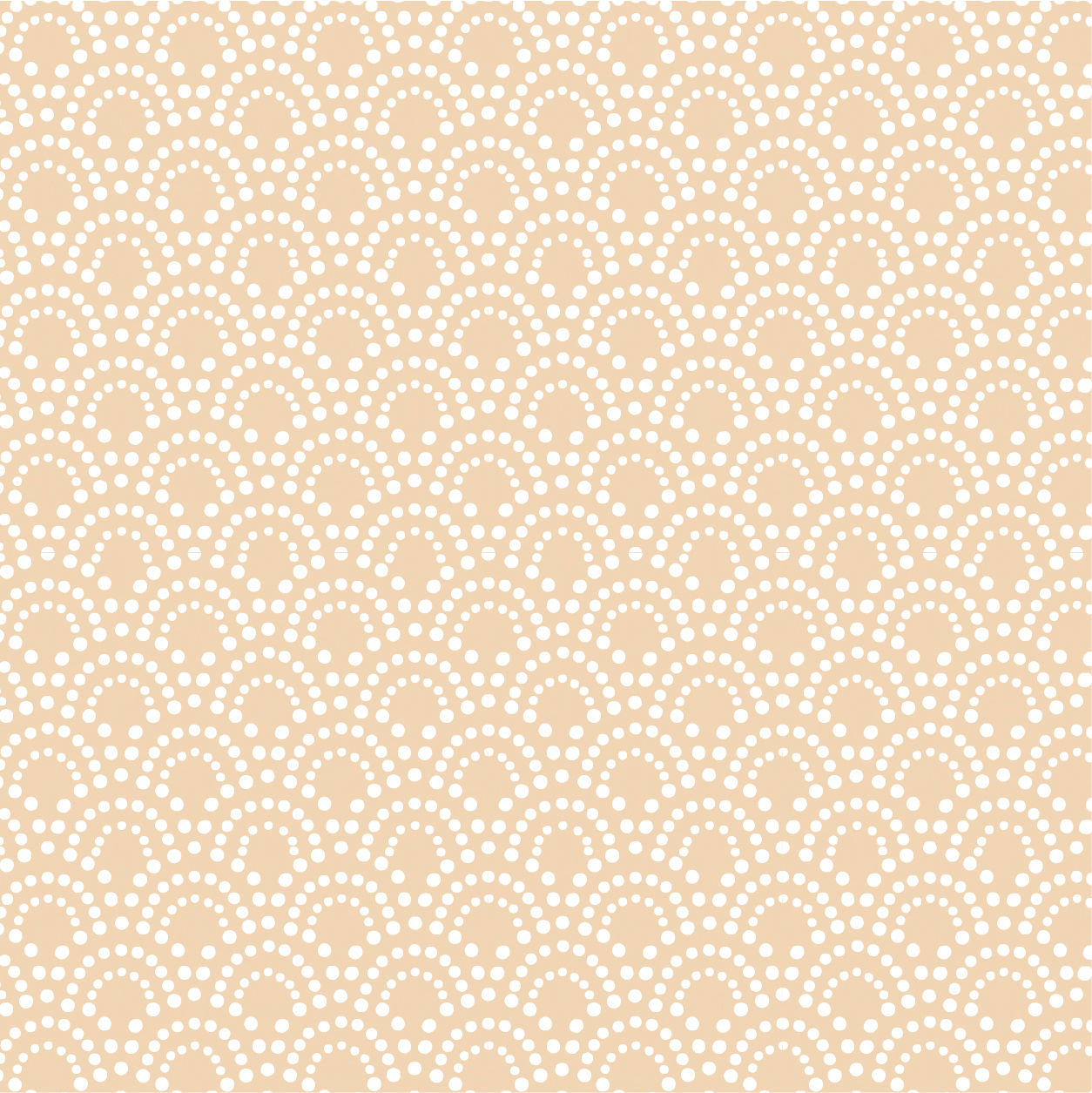
鮫青海波
鮫小紋で青海波を表している文様。
文様が点で描かれ、色彩と合わさって、やわらかな波を表現していると思う。
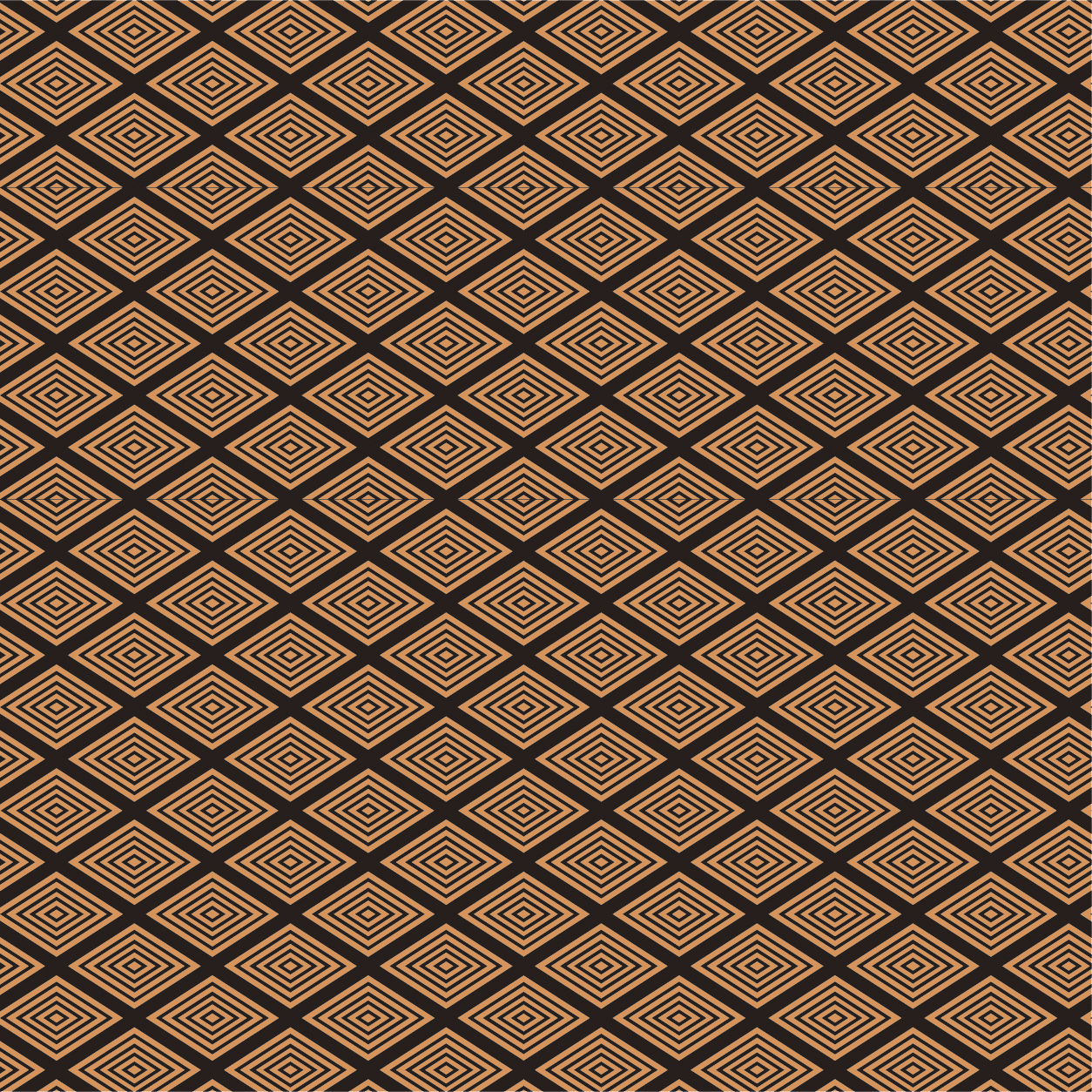
入子菱
菱形の中に菱形を入れて、入れ子にしたもの。
亀甲花菱と似たような印象を受ける。
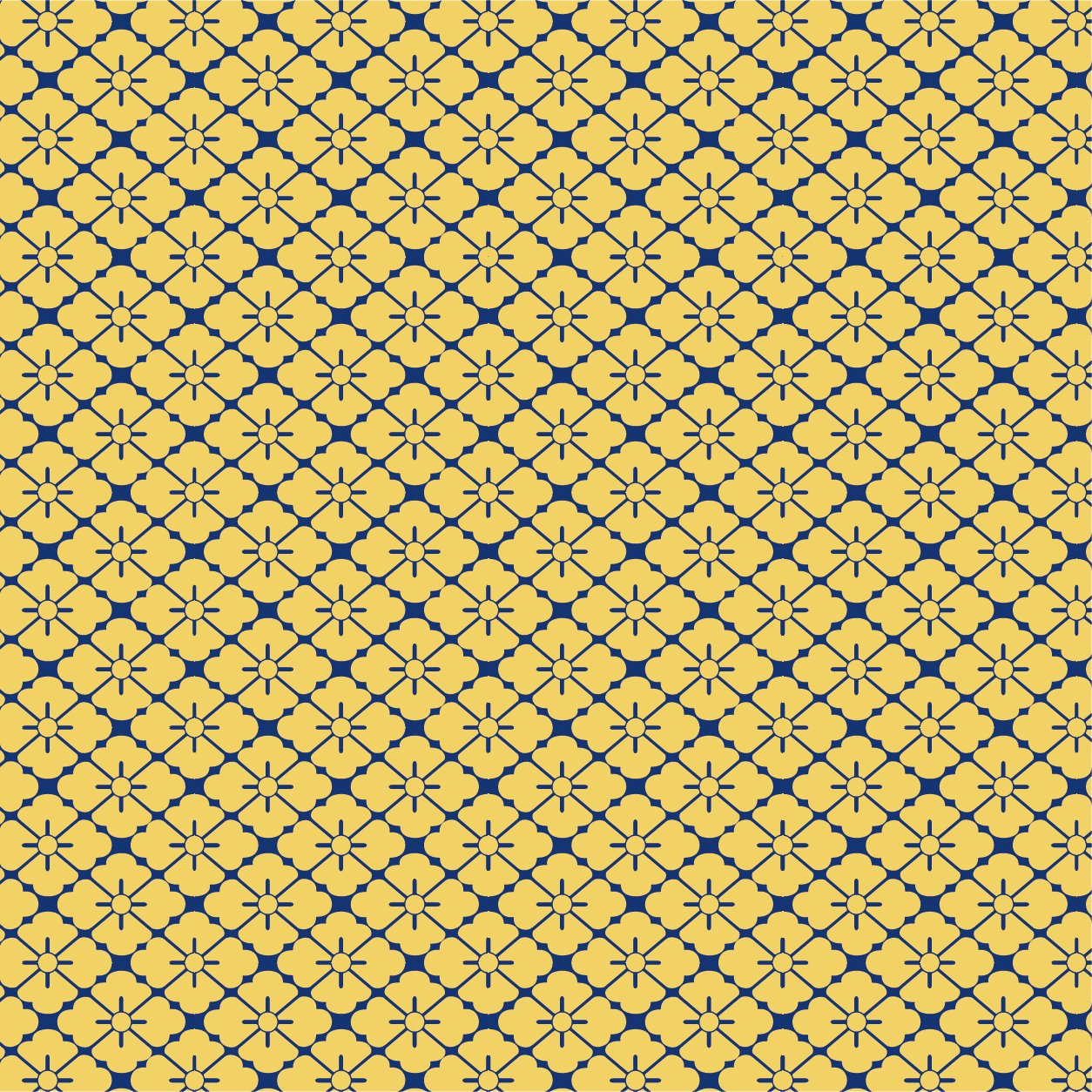
四花菱
四つの花菱を集めて一つの菱にした文様。
四つの菱でできた花がさらに集まって菱になる様が面白いと思った。
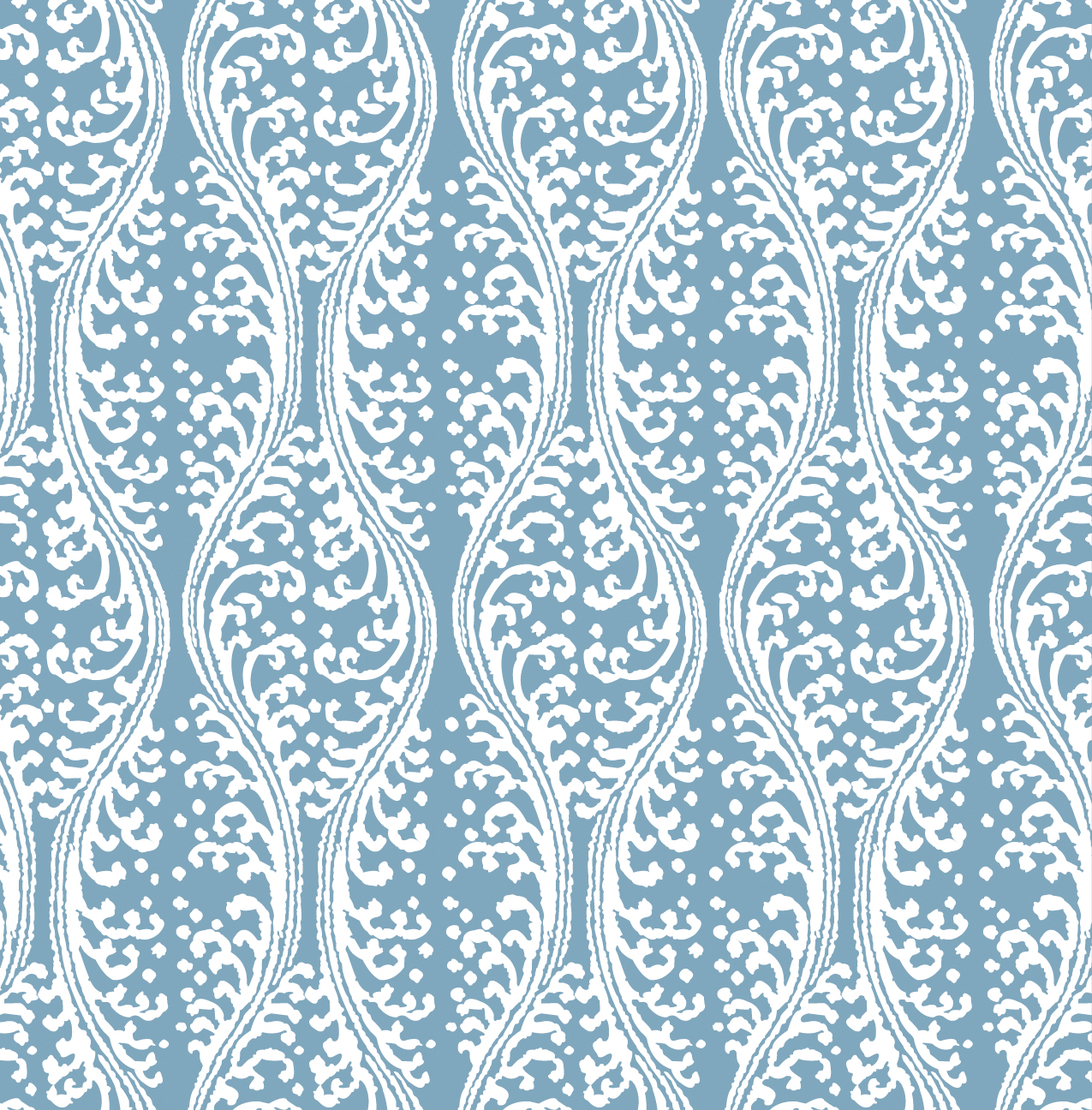
波立涌
立涌を、水しぶきの上がった波濤で見立てた
文様。
連なった波に躍動感があり、どこか清涼感があるように感じた。
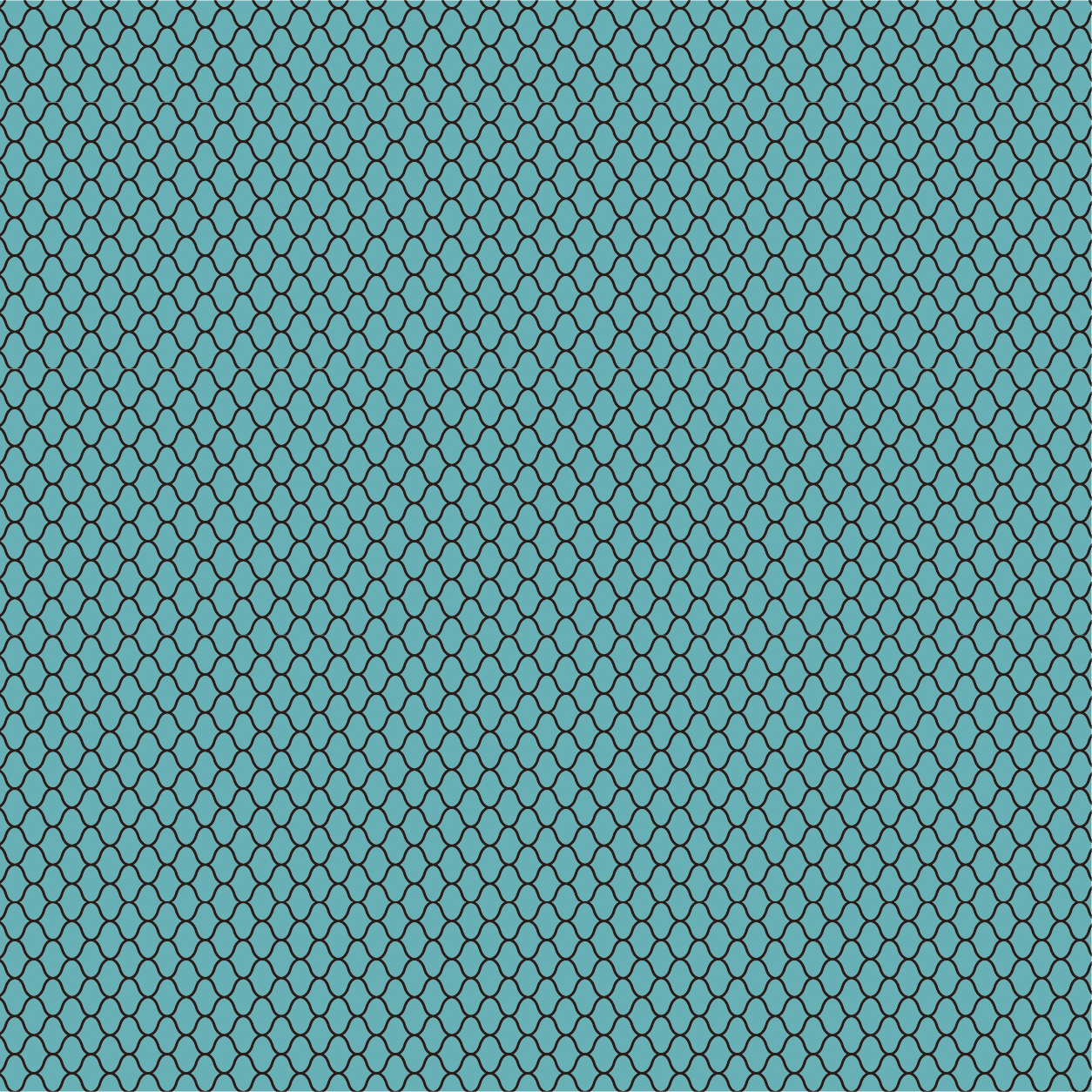
網目
漁網の目の文様。
海老や魚とともに大漁文としても用いられた。
単純な文様に見えるが、漁師の人たちはこの文様に大漁の願い
を託していたとわかった。
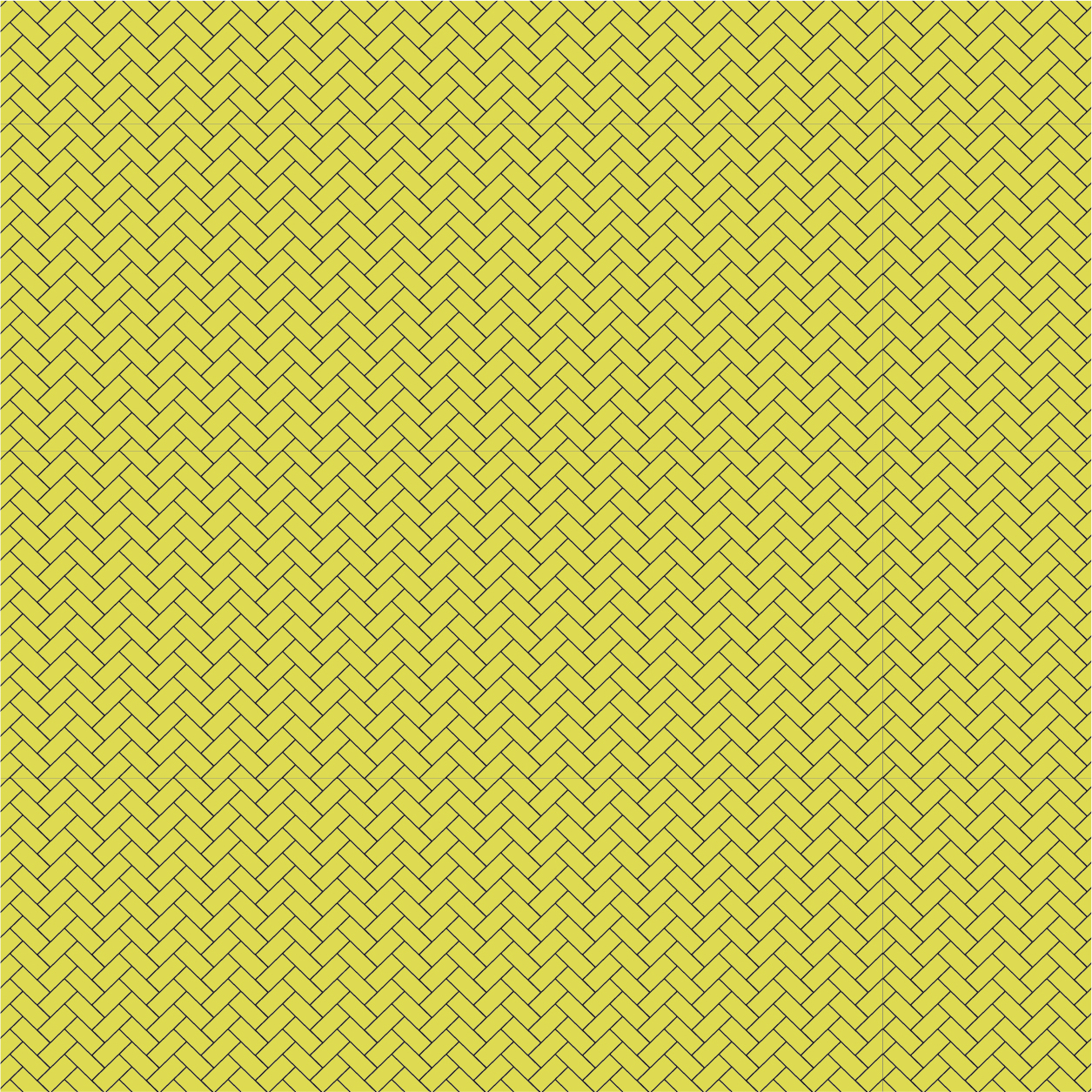
桧垣・網代
檜などの薄板で組まれた垣根や羽目板を文様にしたもの。
身の回りの規則性のある形は、文様にしやすいのかもしれない。
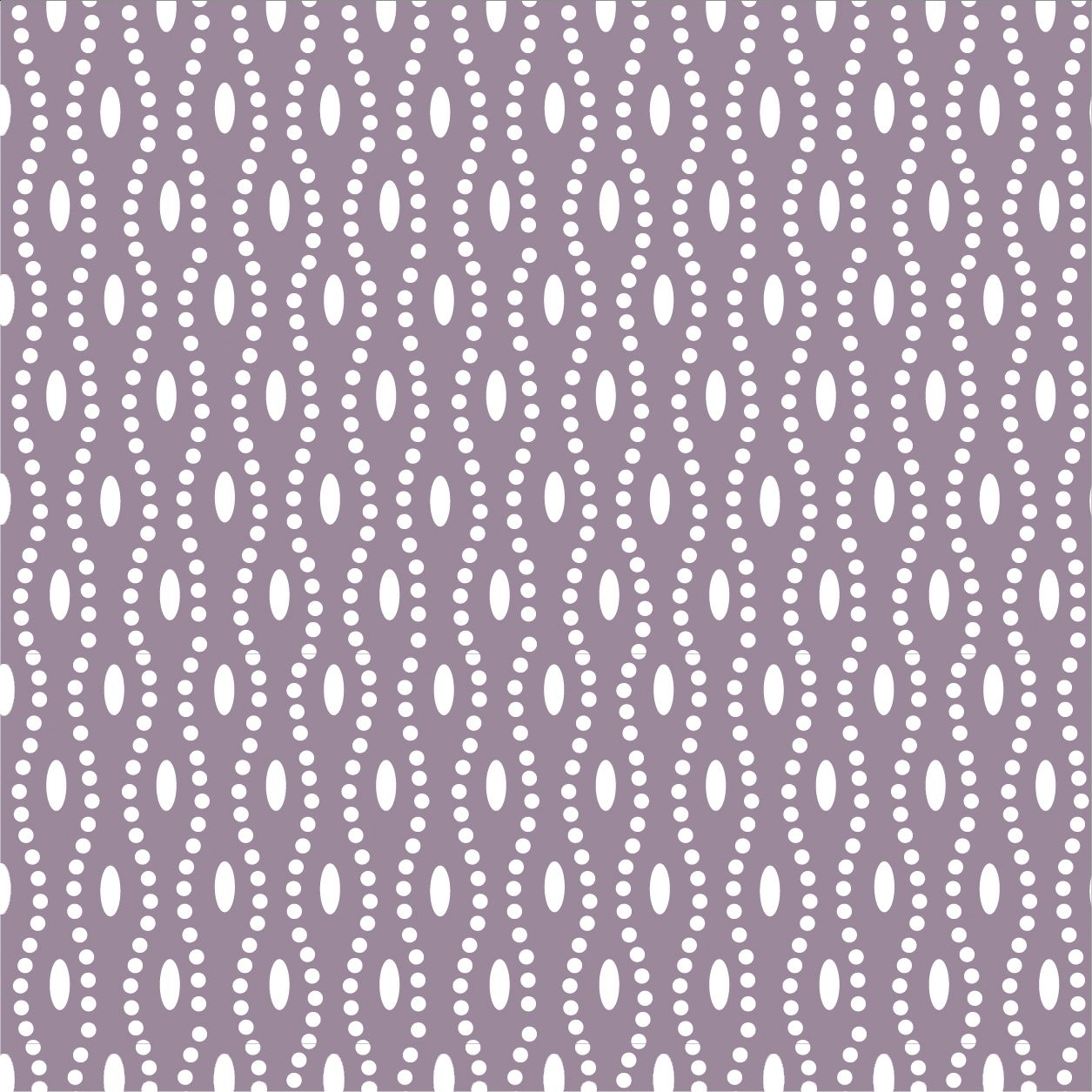
立涌の小紋
立涌を小紋で表したもの。
お婆ちゃんの風呂敷包みに似合う文様だと思う。
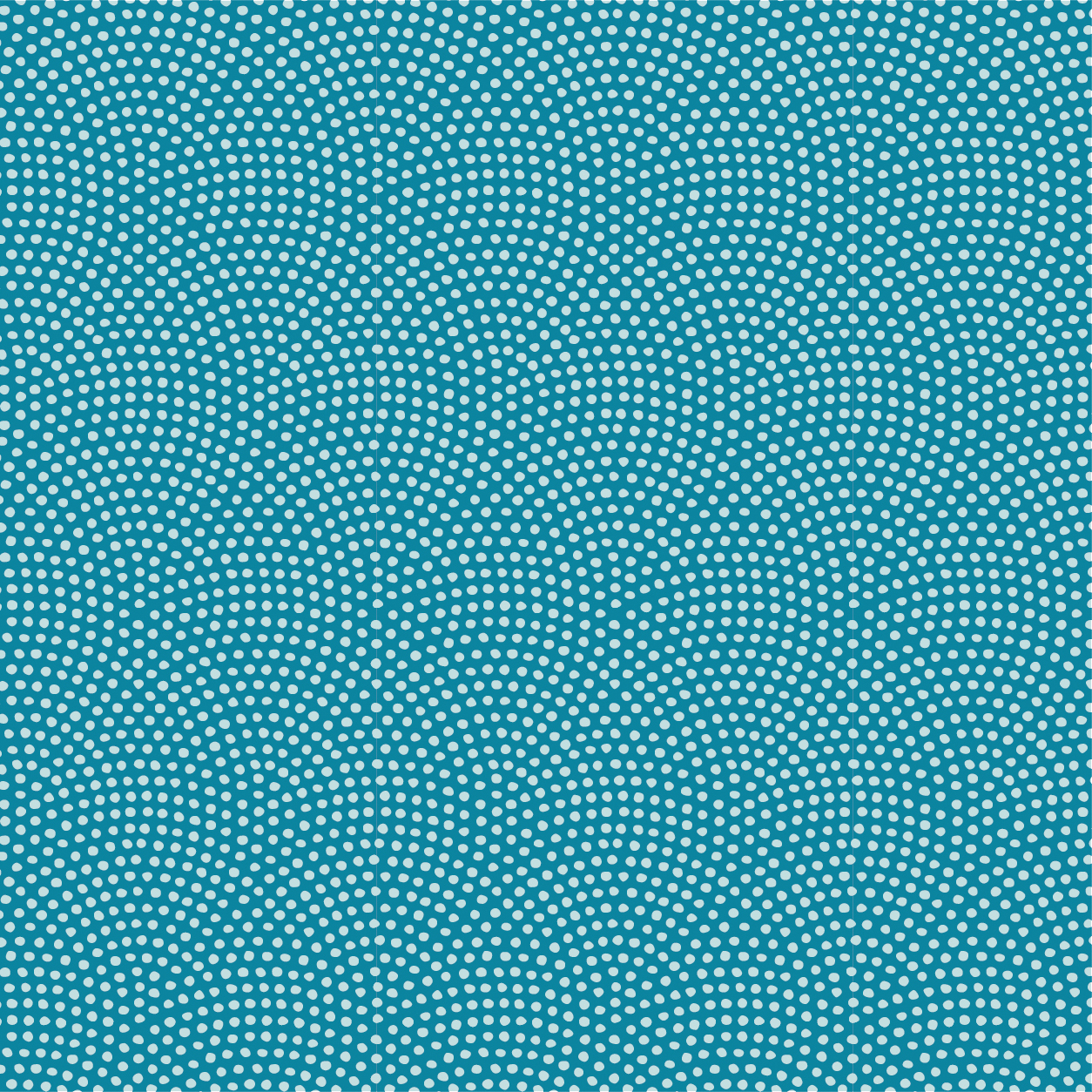
鮫小紋
江戸小紋の代表的な、鮫肌に似ている文様。
某時代劇の名奉行がこのような文様の衣装を着ていた気がする。
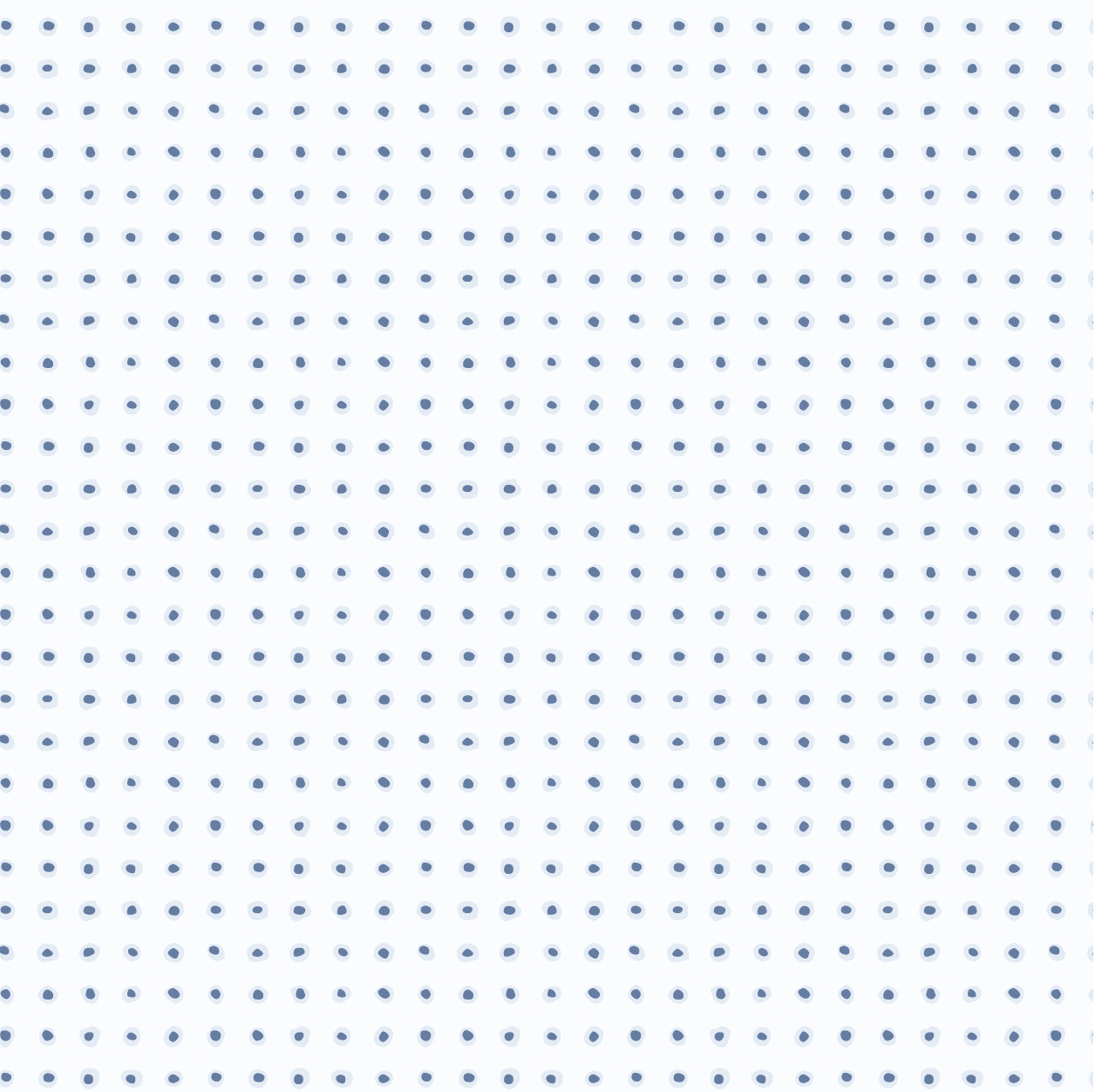
豆絞り
手拭いなどに使われた、豆粒ほどの小さい円を
一面に染め出した絞り染め。
いろんな時代劇の手拭いに見られる文様だと思う。
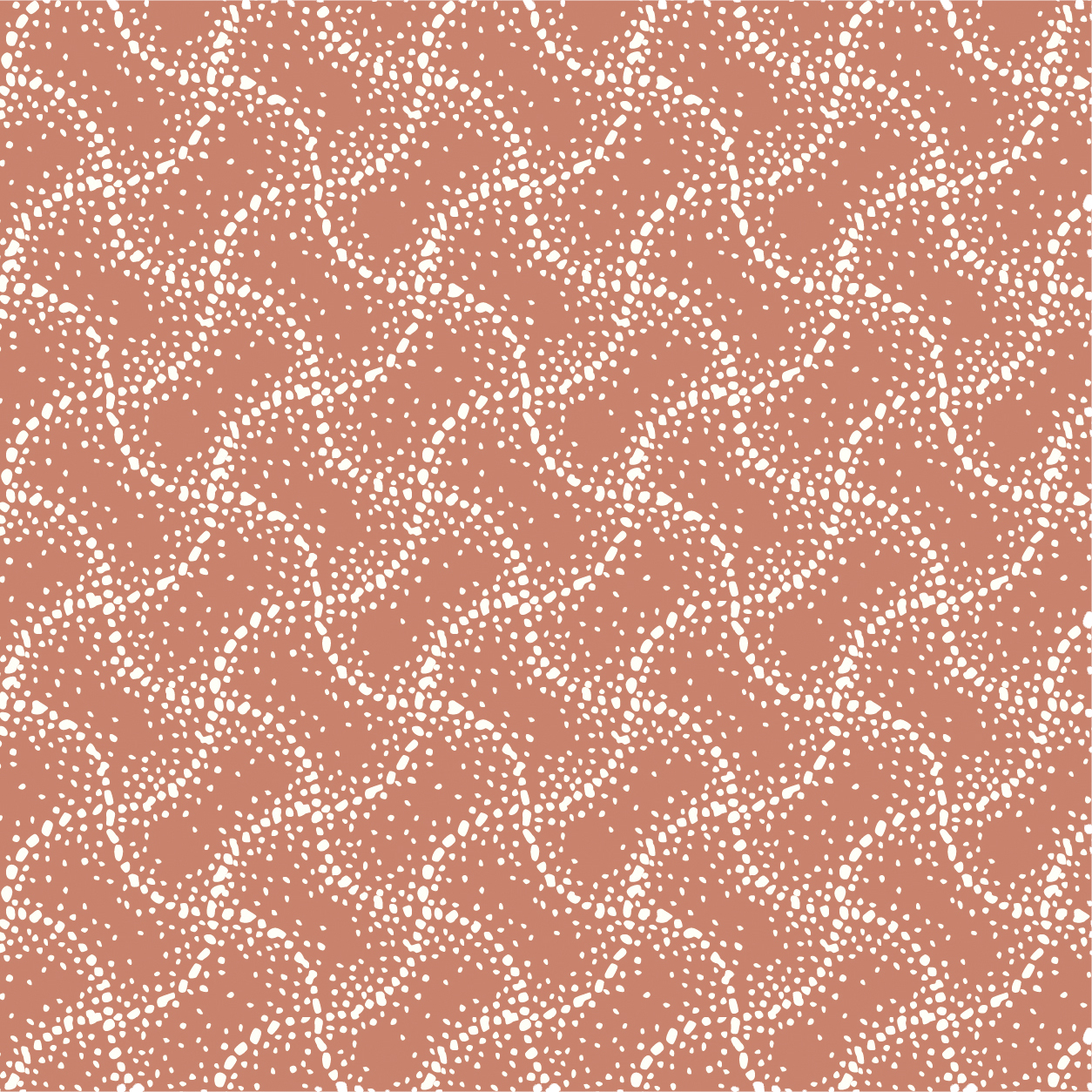
小紋
女性的な文様だと思う。
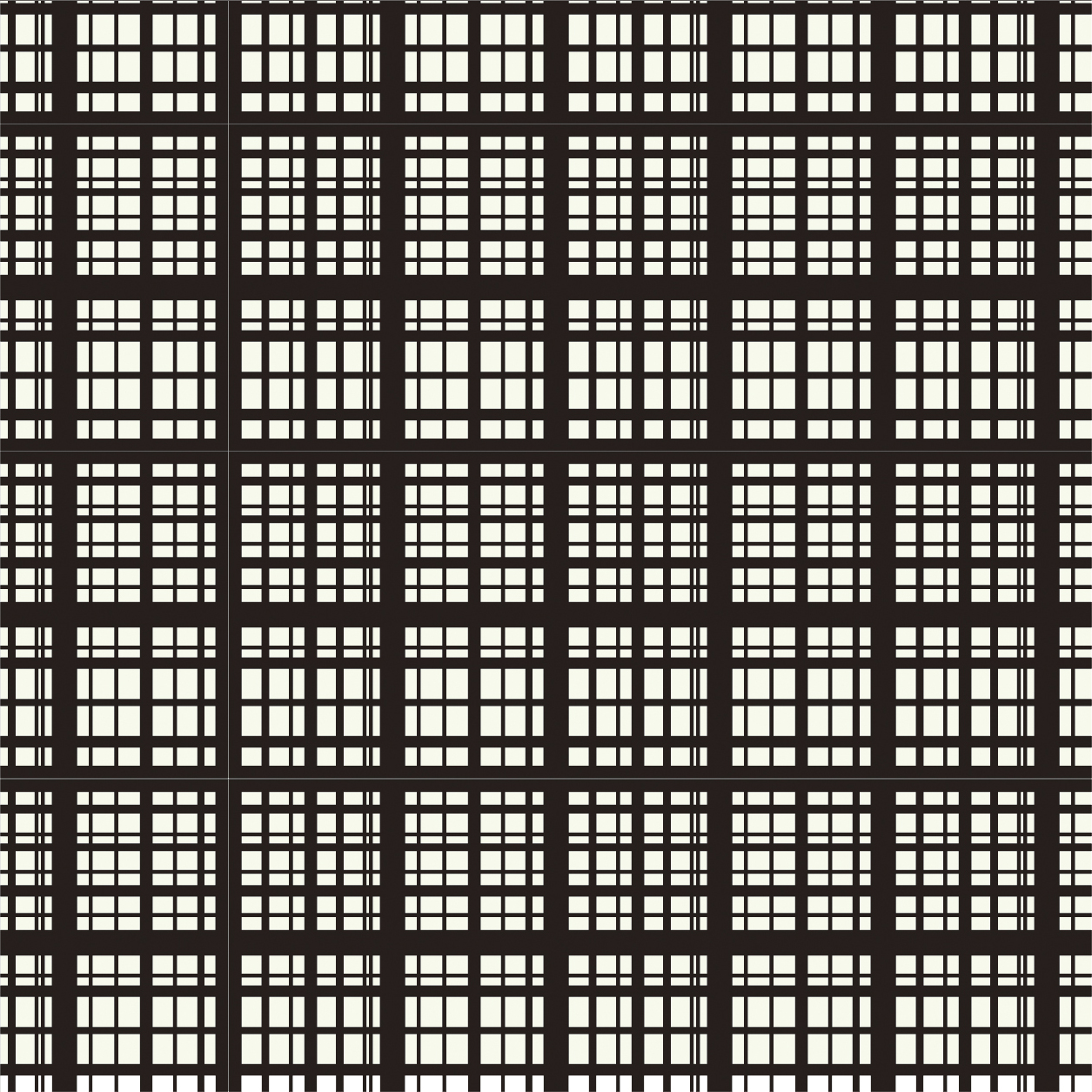
翁格子
大きな格子の中に小さな格子を抱えた様を、翁と
大勢の孫に見立てた格子。
線の太さの違いに、翁と孫の関係が表現されているとは思わなかった。
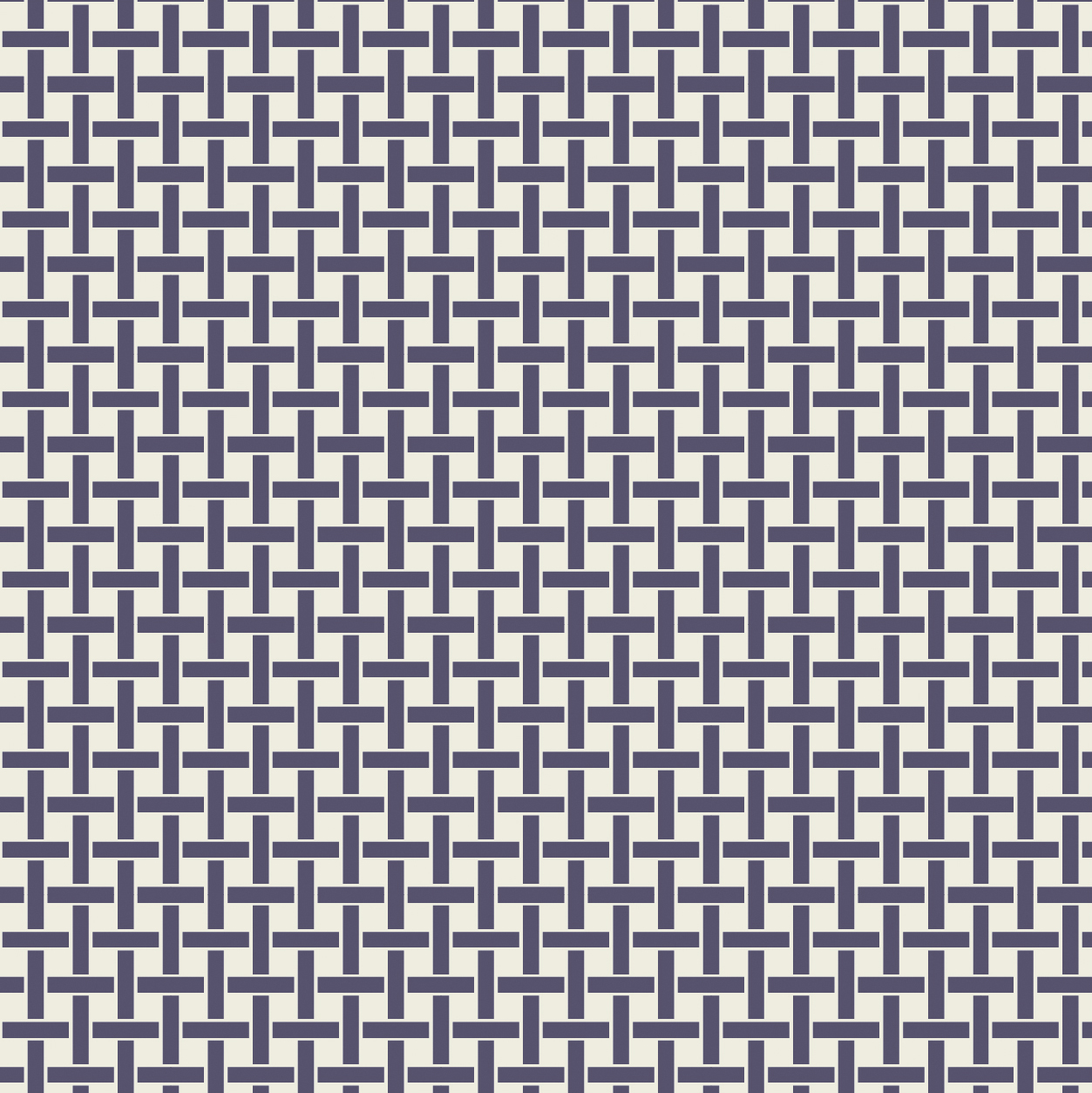
一崩し
割付文様の一種。
網代組とも言われる。
網代組は建築用語でもあるそうだ。
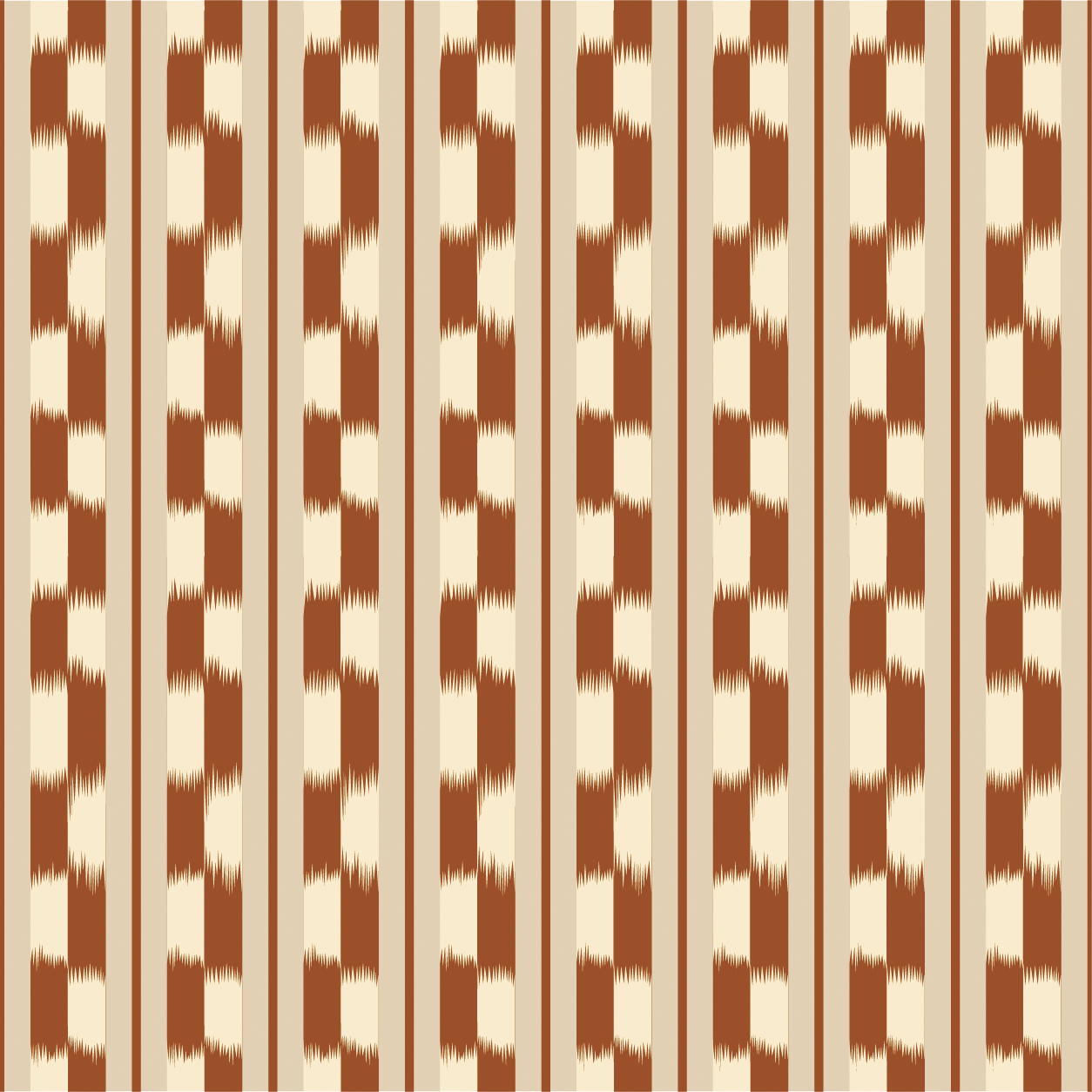
絣の縞
部分的に染色した糸を縦横に織り、染め残った
部分との差で表された織物の文様。
時代劇に出てくる女将さんなどが身につけている衣装に、似たような文様があったと思う。

釘抜繋ぎ
正方形の中央に小さく正方形を入れ、釘抜きの
座金を表している。
そろ盤の文様にも見える気がする。
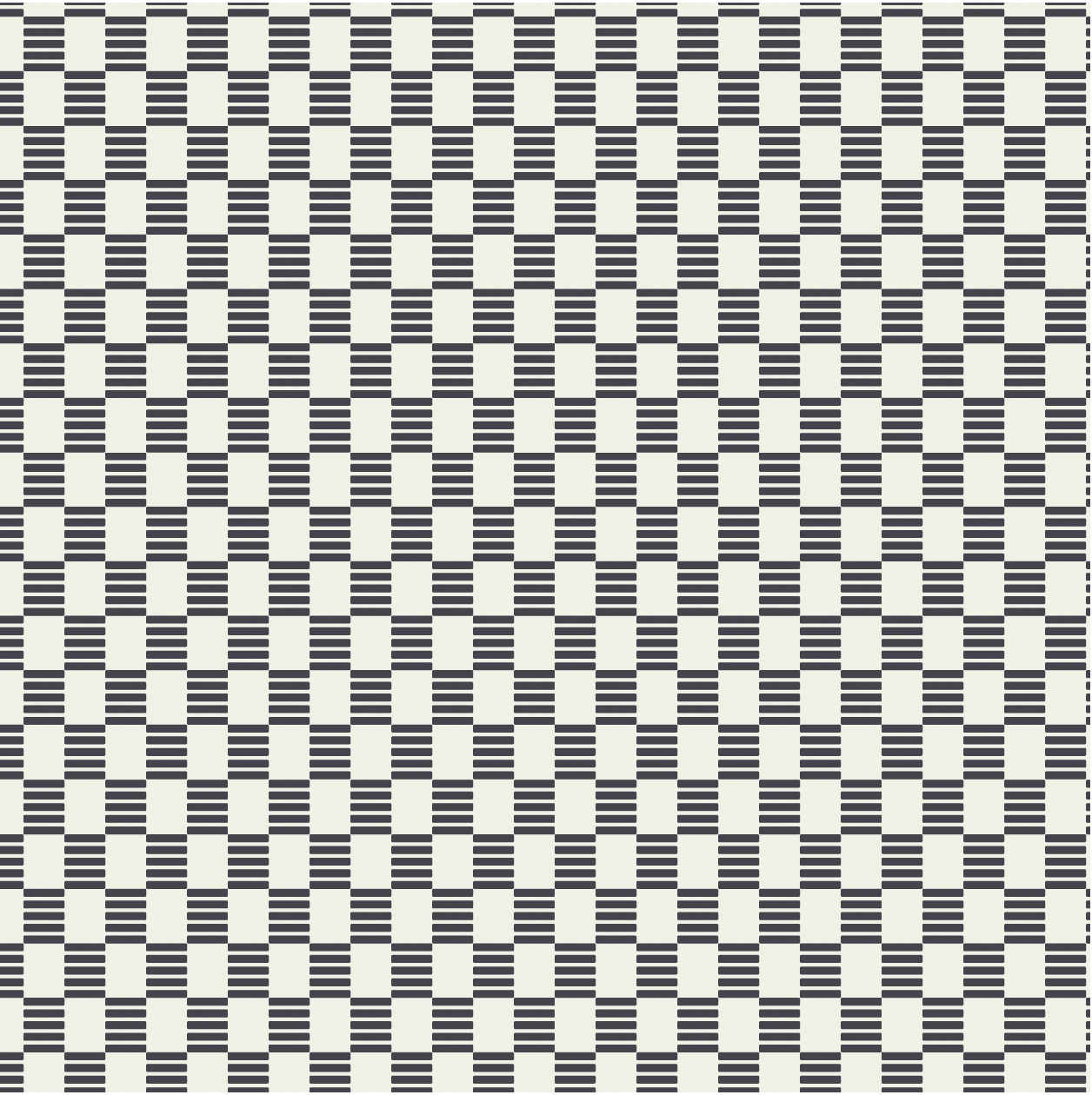
石畳(市松)
別名、市松文様。
石畳の細かいものは霰と呼ばれる。
人気歌舞伎役者がこの文様の衣装で舞台にでたことで、一躍人気の文様になったらしい。
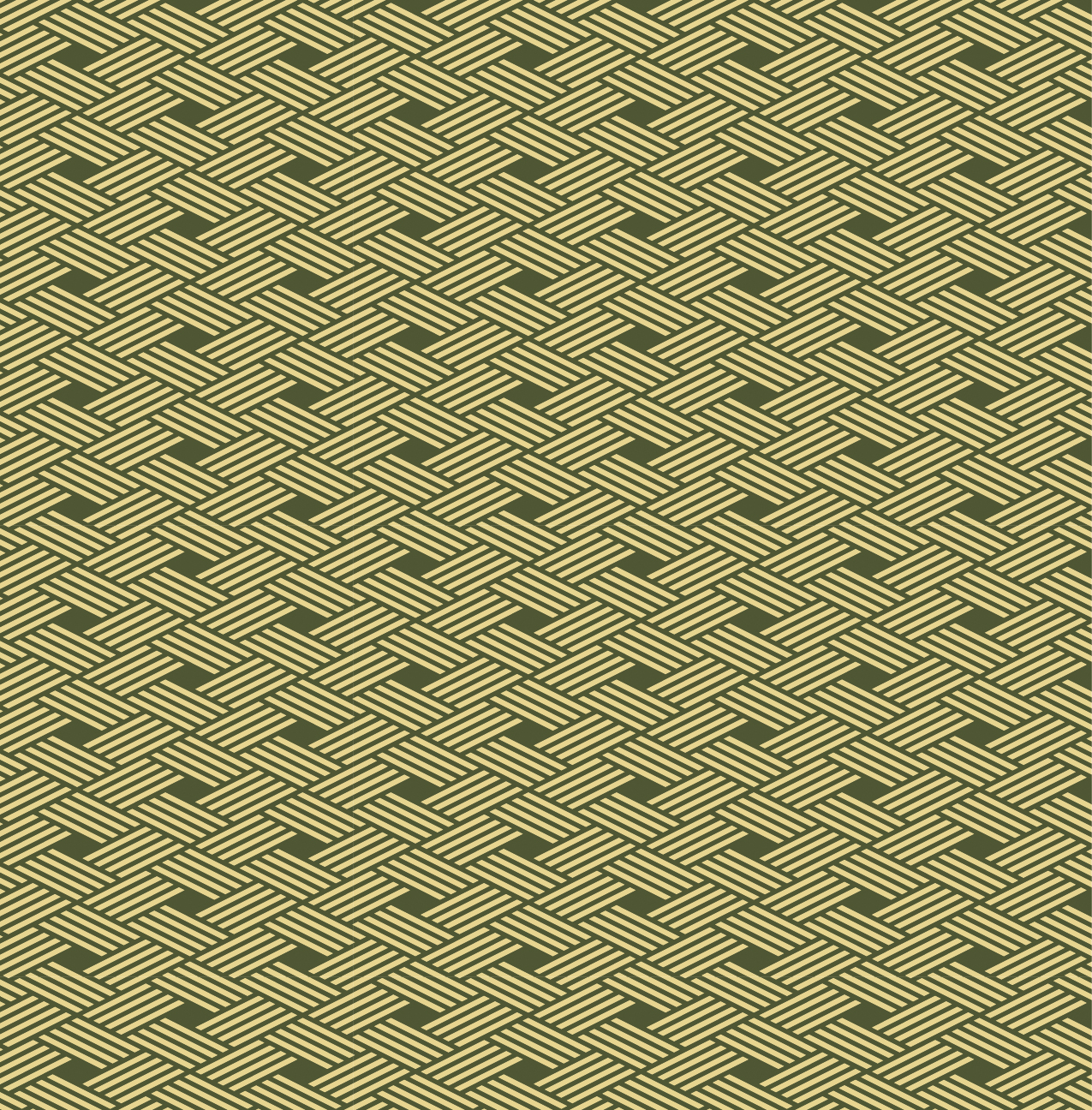
網代
竹・葦・檜皮などを薄く削って編んだ網代に由来した文様。
身近なものを文様にしていて、庶民性に溢れた文様だと思う。
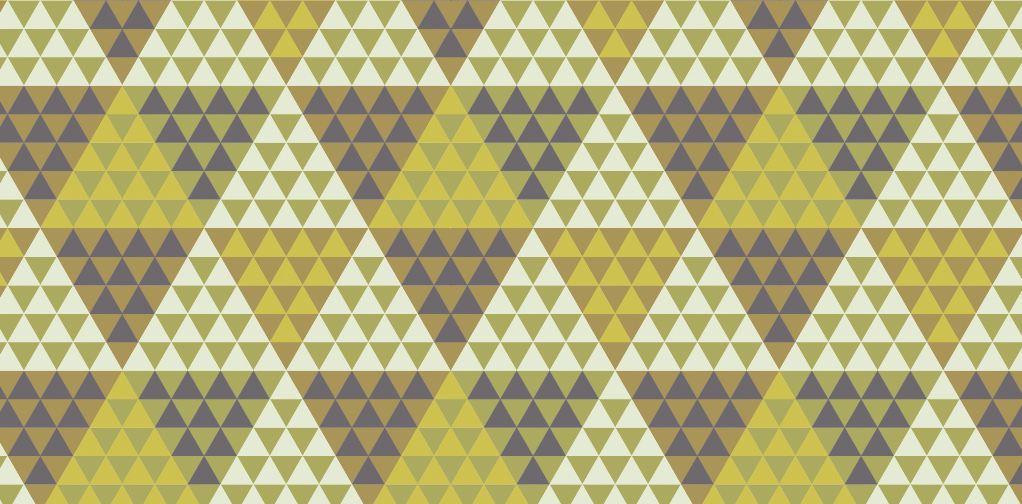
鱗
三角形のみで構成されているが、色彩によって鱗のように見える。

染型の唐草
染型は、着物の柄を染める際の型紙のこと。
この文様は唐草の染型から抜粋したもの。
植物のつるが絡み合ったような文様が、唐草と呼ばれるのだろうか。

唐草
唐草の代表的な文様。
泥棒が使う風呂敷のような、渋さの濃い文様だと思う。
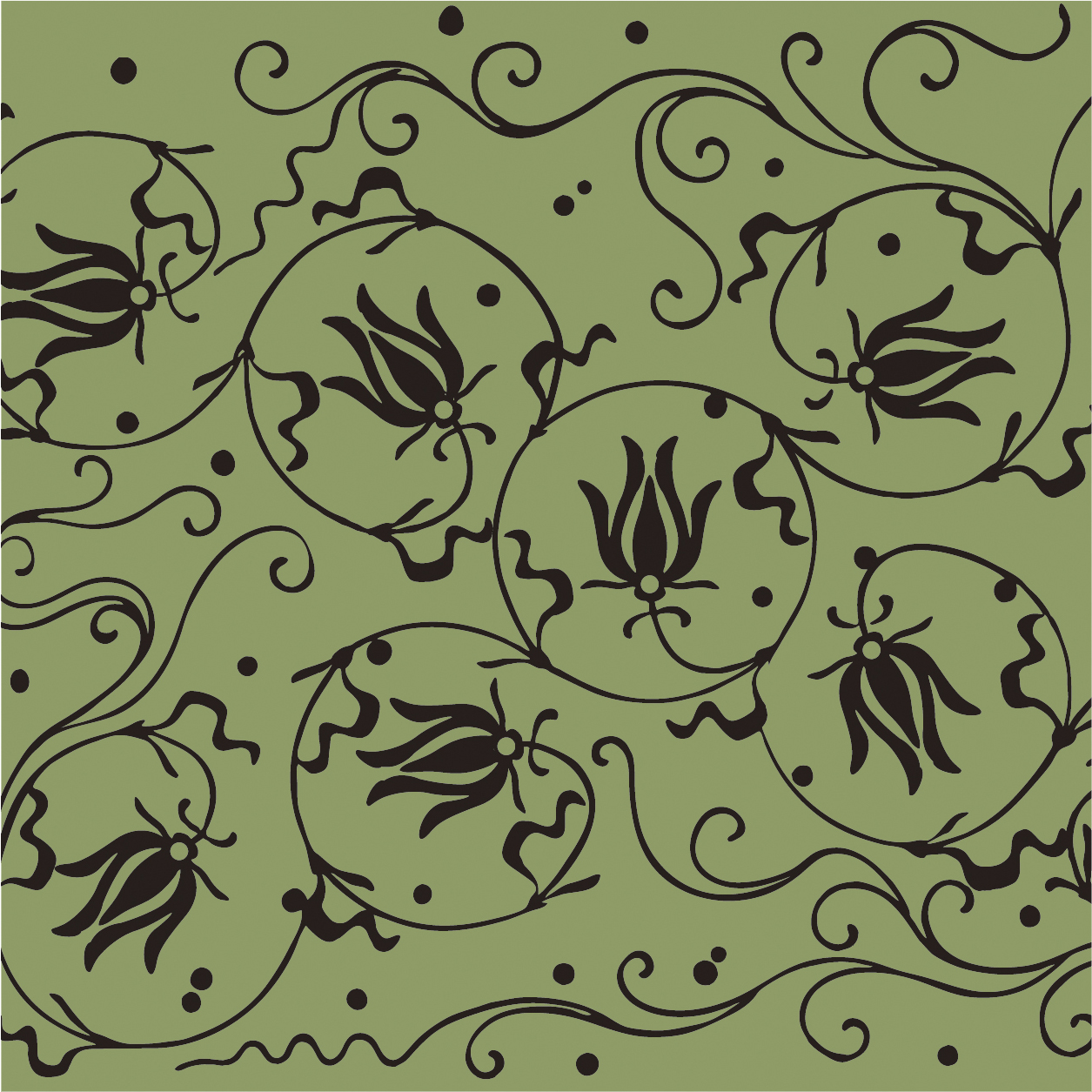
唐花唐草
唐花は想像上で理想化され、創造された花のこと。
製作者のセンスが最も出るもんようなのだと思う。
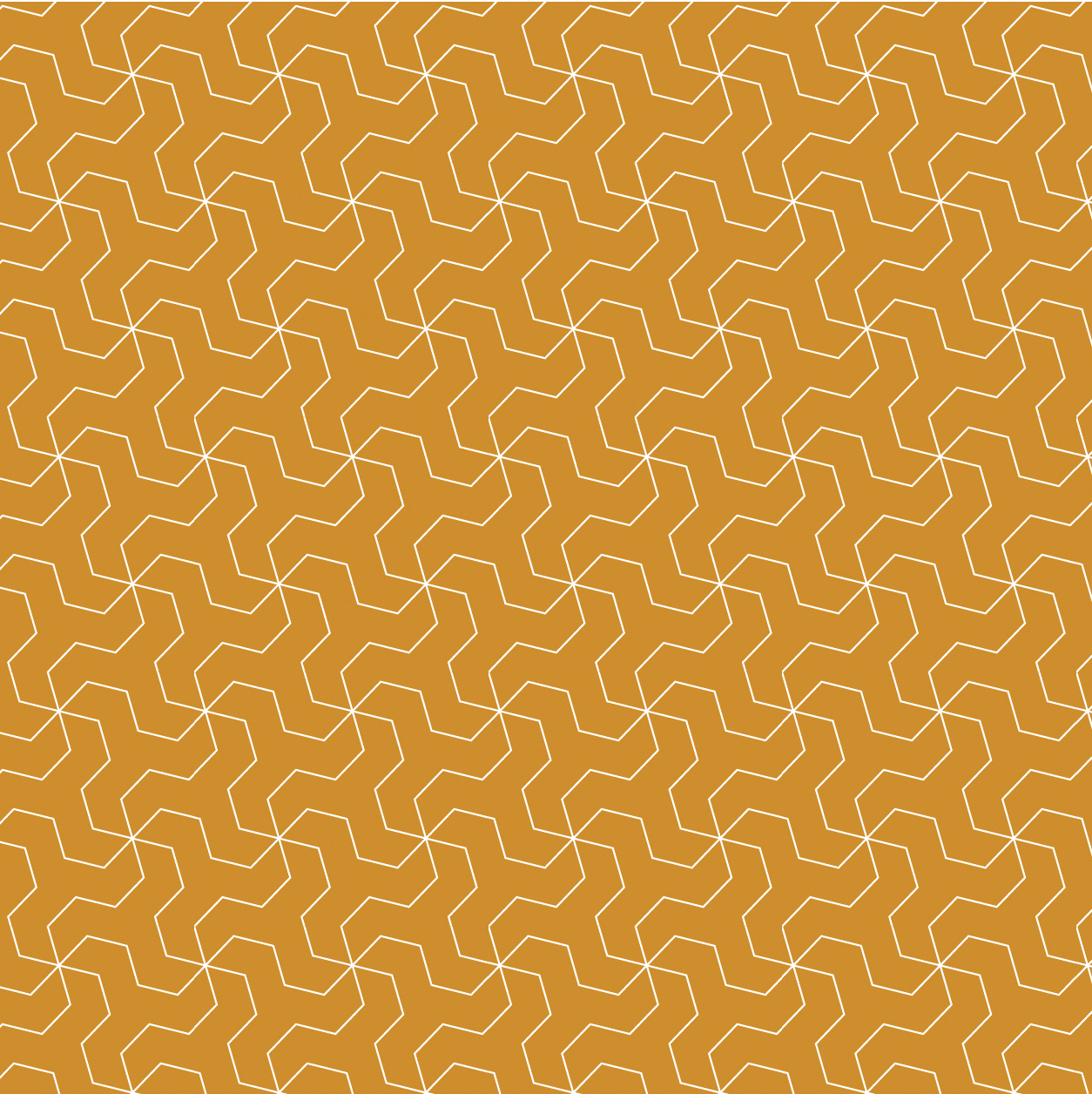
念じ麻の葉
麻の葉の中心が捻じられたように表現された文様。
手裏剣か風車のような文様がパズルのように並んでいるのが面白い。
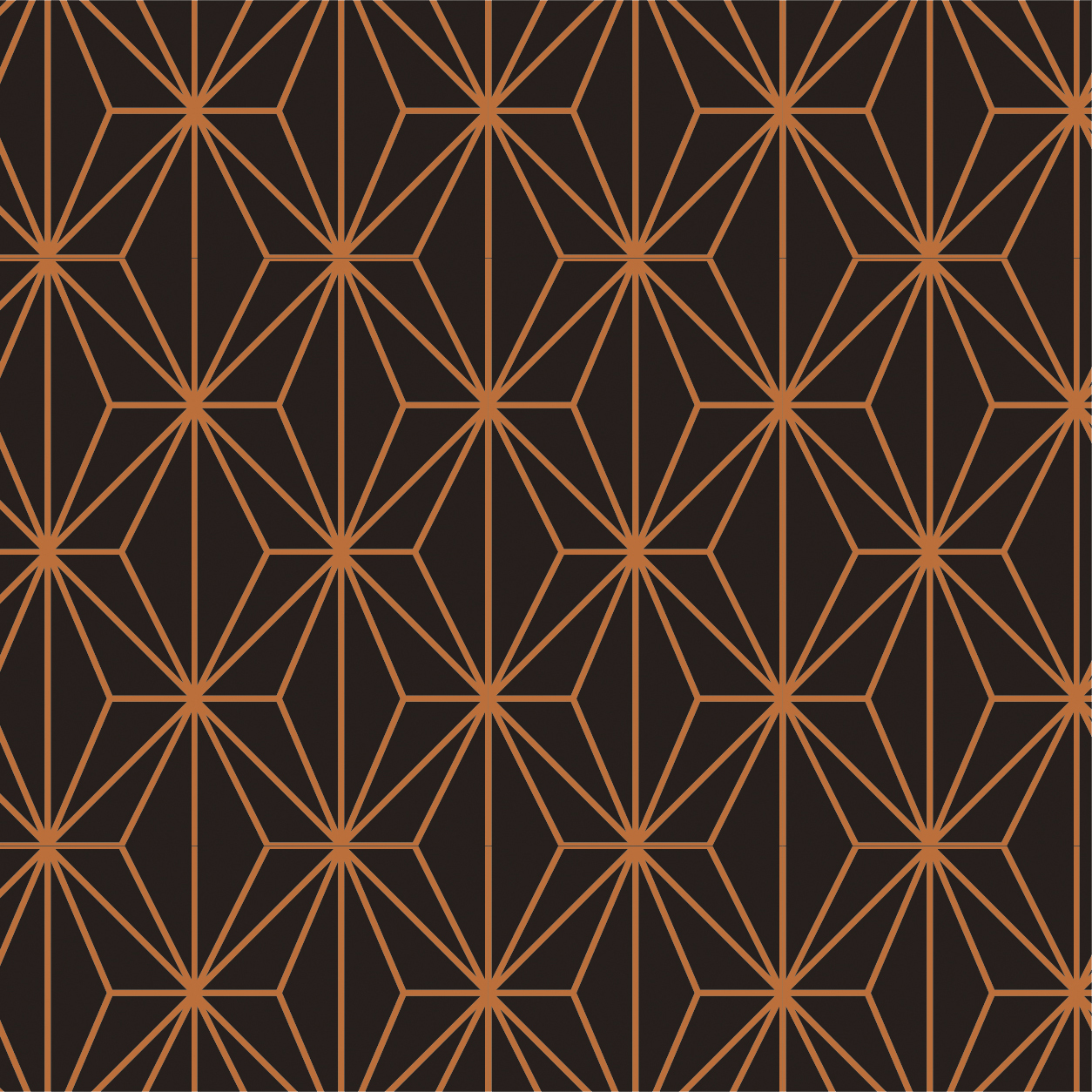
麻の葉
現代でもよく見かけることのできる、麻の葉の文様。
現代では、重箱などでよく見かける文様だ。