文様
名称
解説
コメント
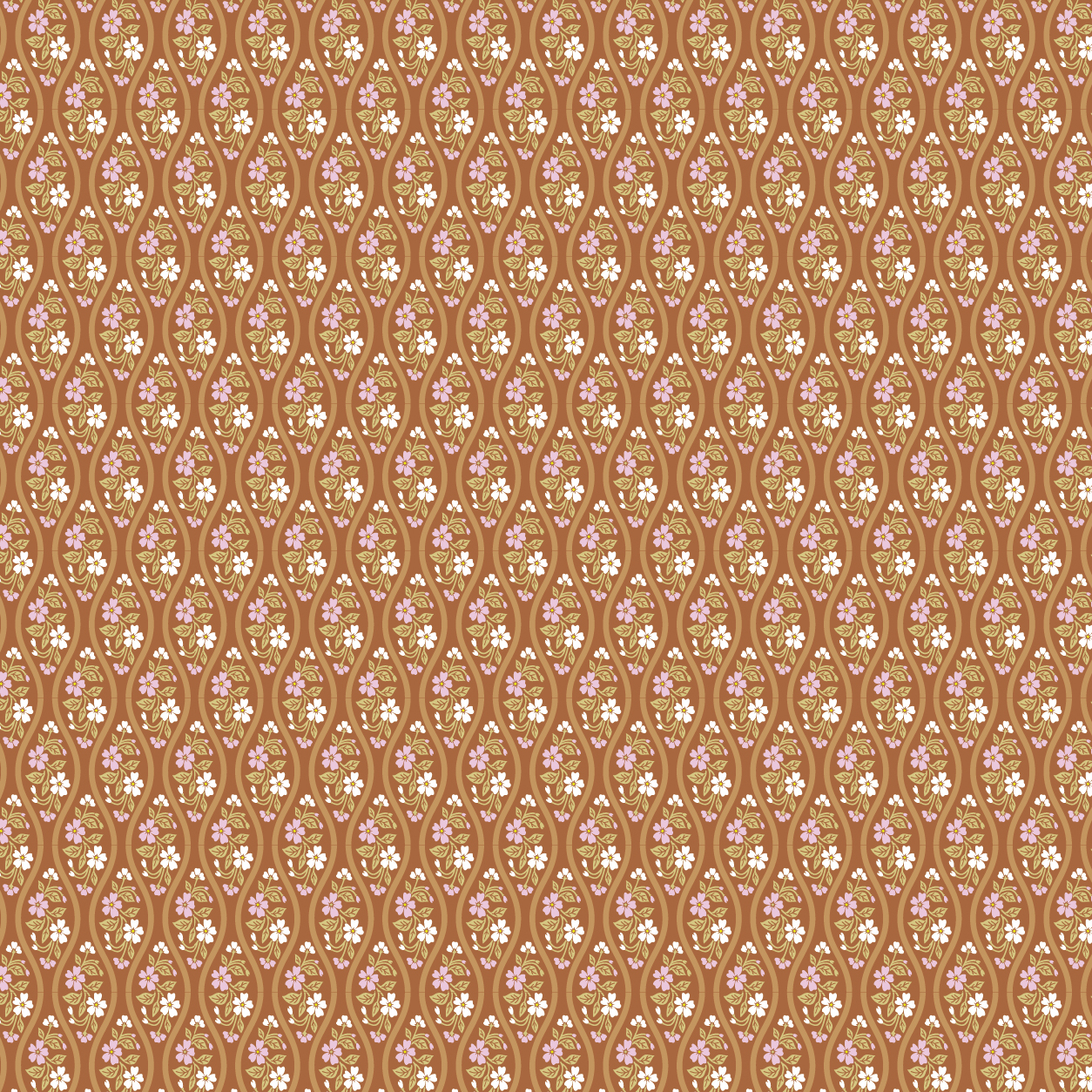
指貫の桜
桜の花を立涌文様化した、指貫の文様。
この文様の指貫を身につけていた男性は、さぞかし身分が高かったのだろう。

友禅染の桜
振袖の背部分に染め分けられた、写実的な桜の文様。
桜の白さが、背景色によってさらに引き立ち、その写実性が際立って見える。
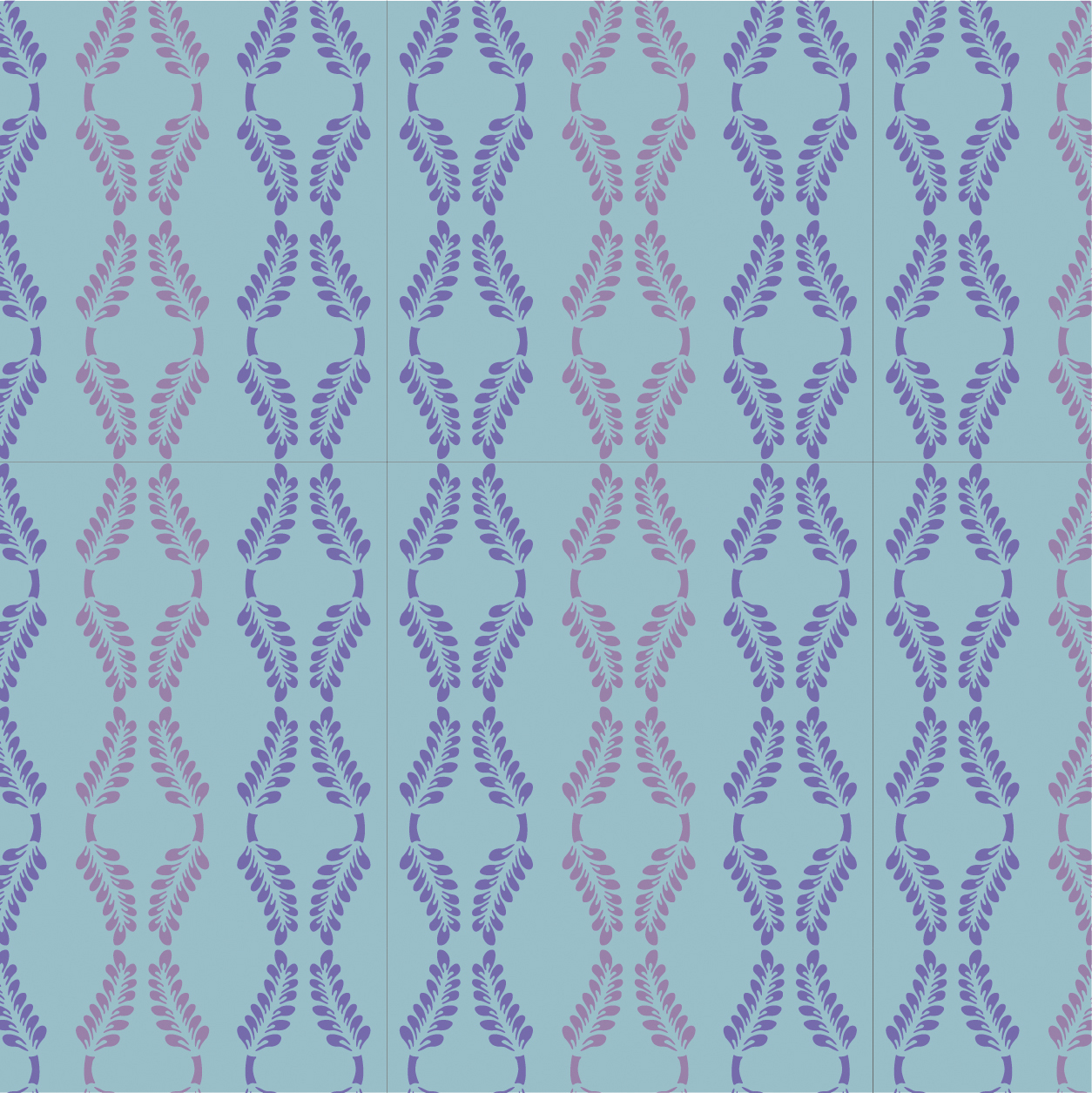
藤立涌
藤の花を立涌に見立ててデフォルメしたもの。
膨らんだ部分に、ほかの花を入れてもいいと思う。

蒔絵の藤
枝から垂れ下がる藤の花を、写実的に表現したもの。
藤の花の色がとても鮮やかで、生命力に満ちている。

蒔絵太鼓胴の牡丹
蒔絵の太鼓胴に意匠を施した、牡丹の文様。
実際に使用する太鼓ではなく、飾り用の太鼓に用いられたのだろうか。

重箱の水仙
重箱の蓋の表に表現された、水仙の丸文。
水仙の清らかなイメージが伝わってくる。

梅唐草
梅鉢の唐草文様。
中心円の周りに5つの円で梅の花を表現している。
朱に金色という、いかにも豪華な文様だと思う。

梅垣
なめらかな白地に映える文様が、見たものに繊細な印象を与える。
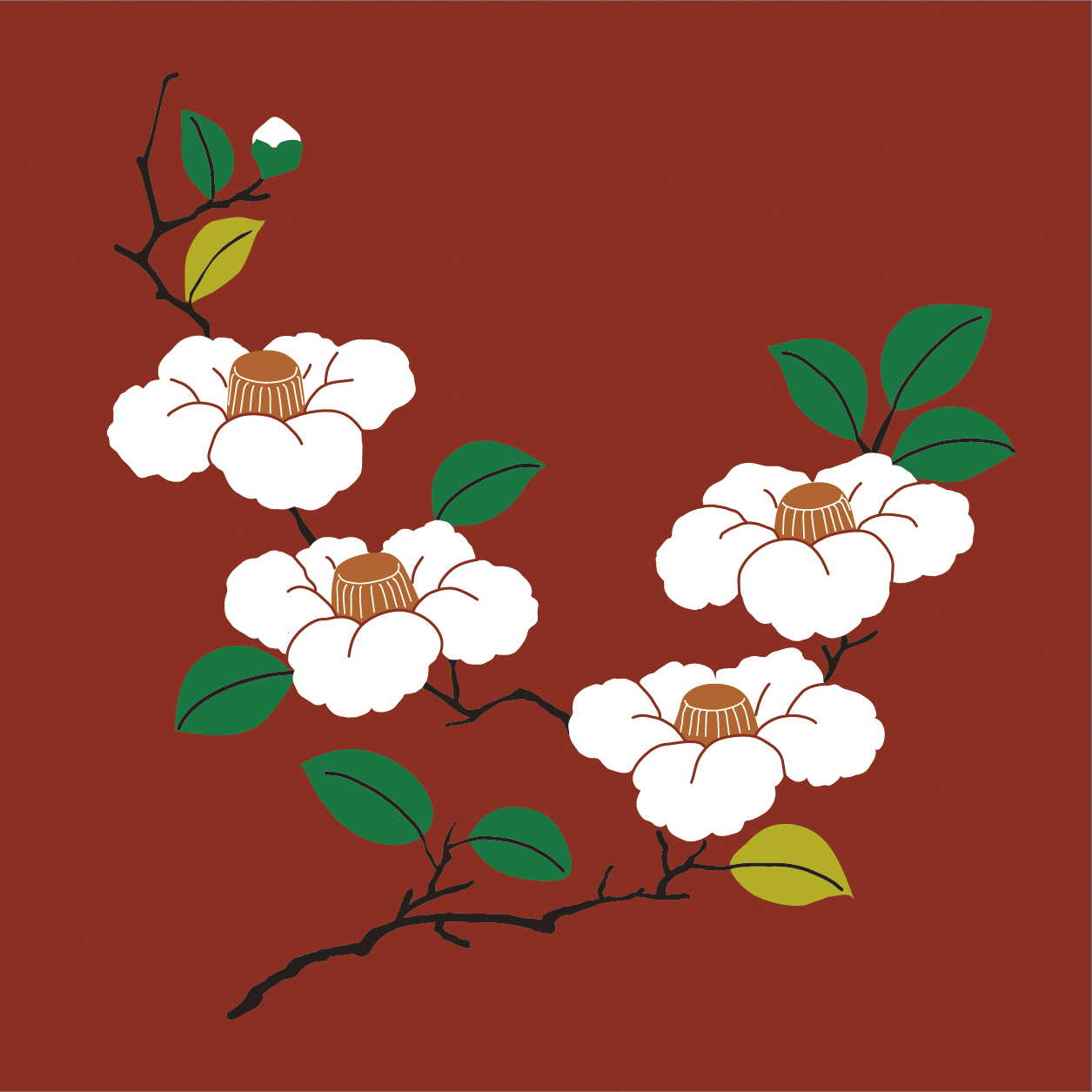
縫箔の椿
椿の花の純白色が、地の鮮やかな朱色に映える折枝文。
朱色に映える、雪のような白さの花が印象的だ。

牡丹唐草
蔓性でない牡丹と、唐草を合わせて文様にしたもの。
実際の牡丹の花にはない色も用いることで、この文様の良さが引き立っていると思う。

蒔絵の扉の牡丹
絵画的な意匠が流行していた頃の牡丹立木文様。
写実的な表現が文様を複雑化し、美しさを醸し出していると思う。

春草
春の柔らかな暖かさが伝わってきそうな色彩と構図である。

蒔絵螺鈿の椿樹
椿の花を随所に螺鈿で表した文様。
黒地に金色というシンプルな色彩で、おとなしく、丁寧な印象を受ける。

花筏
楓と流水で龍田川を表し,桜折枝が流れてゆく様子の文様。
一面花びらだらけになっている花筏も美しいが、この文様のように川の流れを感じることができるのも趣がある。

日本画の紫陽花
写実を超えた表現の、見事な紫陽花の絵。
非常に写実的な表現だが、従来の日本画の雰囲気を損ねていないと思う。

逢箔の杜若
籠目文を地に、色とりどりの花びらを表現した逢箔の杜若。
花の色を複数にすることで、飽きが来ない文様になっている。

友禅染の杜若
写実的な杜若、簡略化された流水を見事な色使いでまとめている。
写実的な表現と簡略的な表現が、互いを損なわせることなく、見事に両立している。

螺鈿の朝顔
櫃を覆いつくさんばかりに描かれた蒔絵螺鈿の朝顔。
夏祭りに着ていく浴衣に合う文様だと思う。
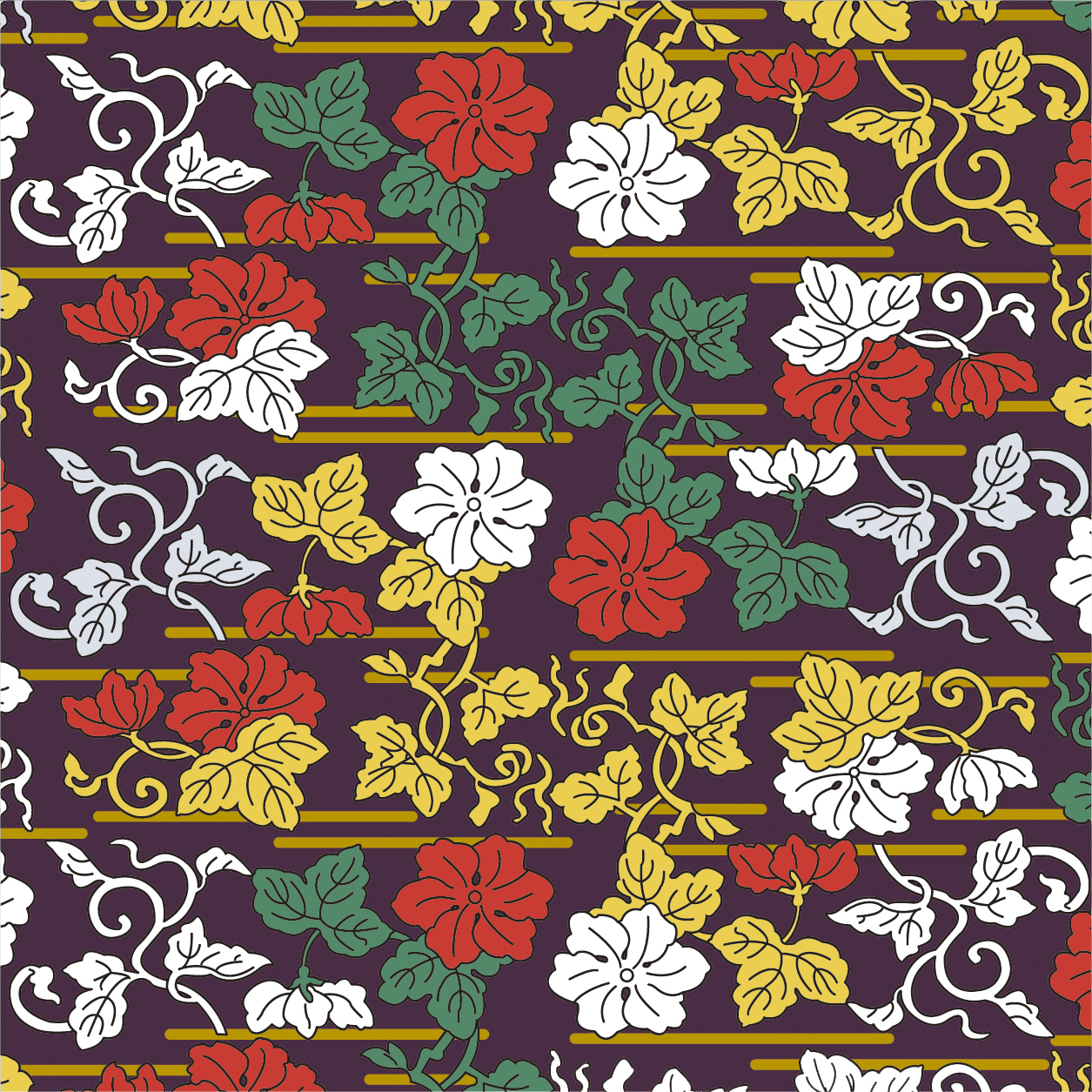
唐織の夕顔
色彩豊かな夕顔を、金糸の霞紋でまとめたもの。
色彩が多いのだが、ゴチャゴチャした印象を受けない。
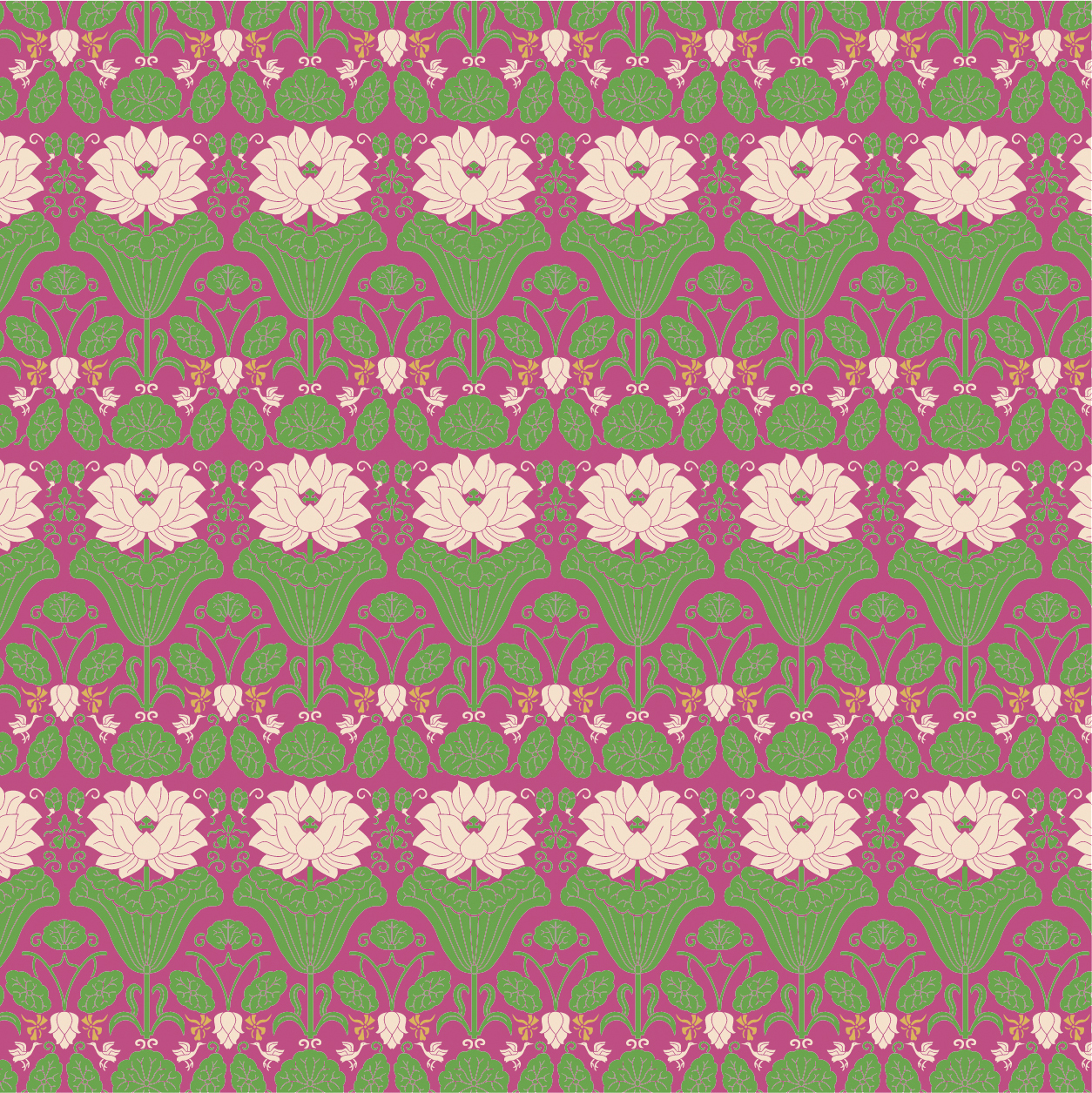
錦の蓮
荷花で構成され、水禽を配することで蓮池を表現している。
蕾かなにかだと思ったが、よく見ると蓮の花の下には水鳥がいることが分かる。

唐織の百合
唐織に見られる、写実的な百合の文様。
写実的だが、デフォルメした形態のような柔らかい感じが伝わる。

蓮池の蒔絵
厨子の扉に描かれた、迫力ある蓮池と散蓮花の文様。
迫力と同時に、やさしい色彩の使い方がその場の空気を優雅なものにしてくれると思う。

肩衣の紫陽花
肩衣の背部分に大胆に表現された、糊防染の紫陽花。
大胆かつ、渋いイメージの文様である。

菊水
花のし文として表現された、菊の花束を用いた文様。
花の鮮やかさを抑え、全体的に渋い雰囲気を出している。

八重菊
小袖に表現された、八重菊の文様。
やや寒色よりの色彩で、

枝紅葉
枝と紅葉を影絵のように表現した文様。
いかにも秋らしい色使いの文様だと思う。

流水紅葉
流水に紅葉が流れていく様子を模様にした文様。
秋の後の、冬の訪れを意識させるような雰囲気を感じる。

唐織の秋草
麻の葉文を地にした、七草の萩と薄の文様。
写実的な描写と、秋を代表する七草のやさしい色どりが魅力的。

芒
芒と夕暮れというベストマッチな組み合わせが、見事な秋の風景を演出している。

秋草
色彩豊かな秋を、様々な色の植物で表現している。

糸瓜
自生風情の糸瓜を肩衣に描いた文様。
やや地味なイメージがあるが、乾燥した糸瓜の実や葉には、秋の訪れを感じるものがある。

三階松
三段に重ねた松の枝葉の文様。
紋章として使用される。
縁起ものとされる松竹梅の内のひとつが三つもあるのだから、とても縁起がよい文様だと思う。
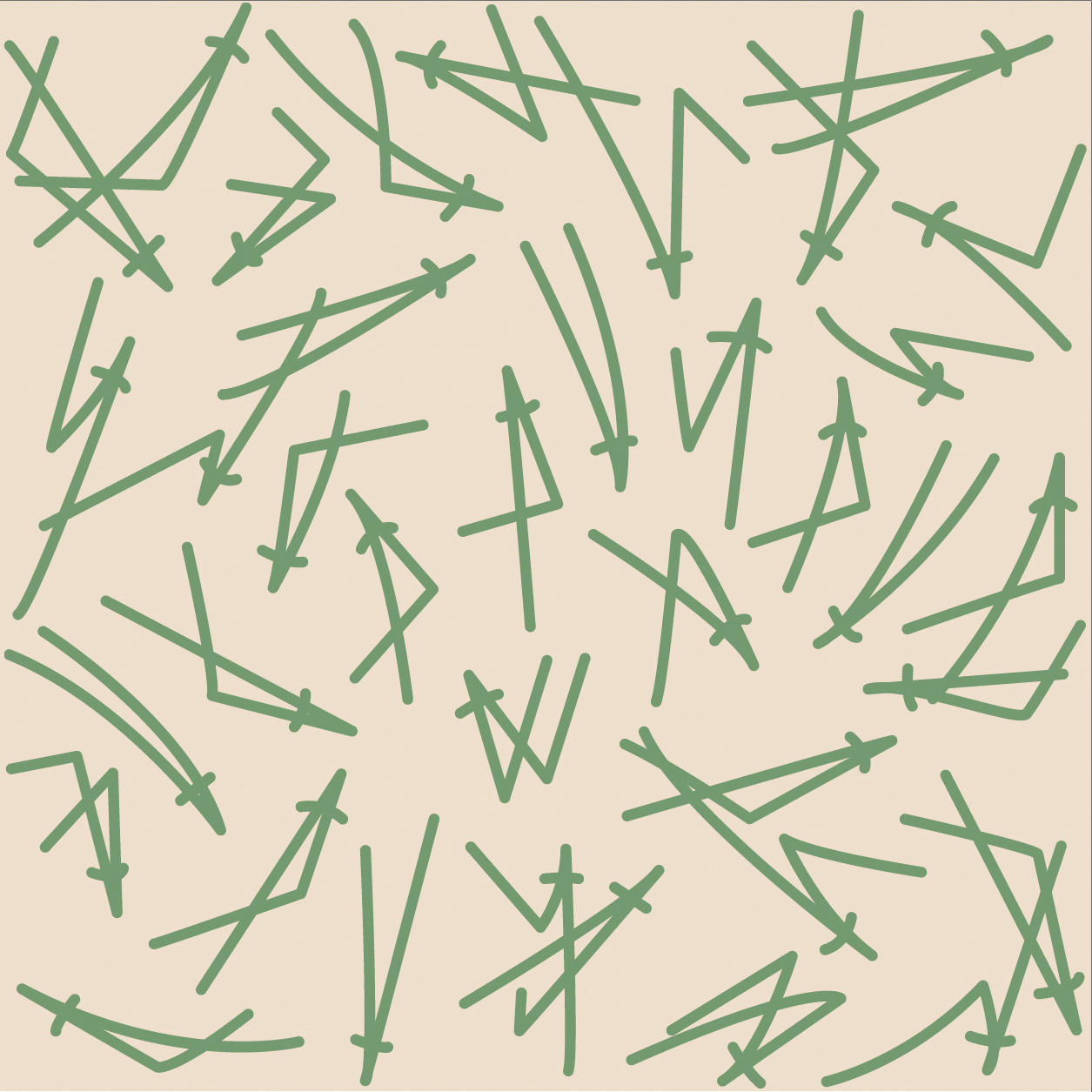
松葉散らし
松の葉を自然に任せて散ったようにあらわした文様。
シンプルだが、若々しさと、涼しげな感じがする。

笹と若竹
雲と組み合わせた笹と若竹の文様。
これは振袖に描かれたもの。
笹と竹は似ているから相性も良いと思うし、縁起ものでもある竹があるから、歓迎される文様だと思う。

笹と若竹
振袖に描かれた笹と若竹の文様。
竹と笹のすらりと伸びた様が、振袖を着ている人の印象も、すらりとした感じにすると思う。

箪笥の烏瓜
鮮やかな烏瓜の実と、蔦の堂々と伸びた様子が印象的な文様。
実の色と堂々としたツルの様子に、生命力を感じる。

桜橘立涌
桜と橘を用いて立涌文にした,公家好みの文様。
ほぼ金色で施された文様は、いかにも貴族が好みそうである。

夜着の橘
夜着の背面全体に、力強く大きな構図で描かれた橘の文様。
夜の背景に、橘の花の色がよく映えている。

蒔絵の大麦
台盤に大きく描かれた大麦の文様。
麦の穂の細い毛一本一本に、文様の丁寧さが伺える。

縫箔の稲
たわわに実る稲を写実的に、霞とともに表現した文様。
黒の背景に、金色の霞と写実的な稲が幻想的。

狩衣の桃
中国では、邪気を祓い悪鬼を退散させる仙木とされている。
桃がそのように神聖な果物とは思わなかった。

膳の葡萄
葡萄は豊ぎょうの印で、唐草として表現されることが多い。
葡萄の実がたわわに実る様は、確かに豊作を連想させる。

団栗
秋らしい雰囲気とともに、丸々と実っている団栗が愛らしい。

厚板の蔦
厚板に描かれた、唐草文様のように連続した蔦を表したもの。
つるの形が規則的でなく、デフォルメされたことで、幾何学的な感じになっている。

硯箱の蔦
斬新な構成で硯箱上に描かれた蔦の文様。
全体か中央に描かれることが多い文様だが、この文様は枠を作るかの様な形になっている。
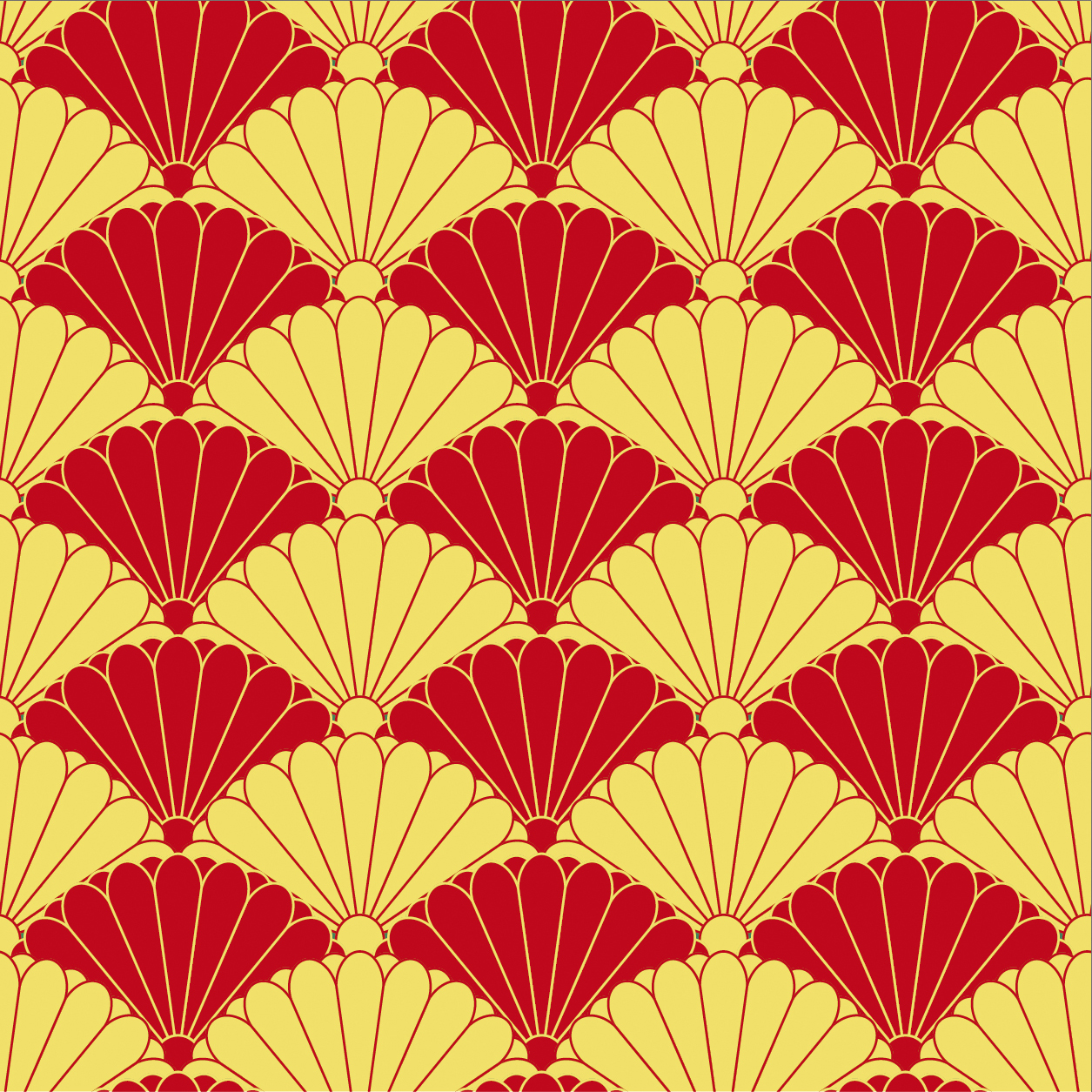
菊青海波
菊の花を規則正しく並べ、青海波に見立てた文様。
菊の文様の並びが、波にも見え、扇が並んでいるようにも見える。
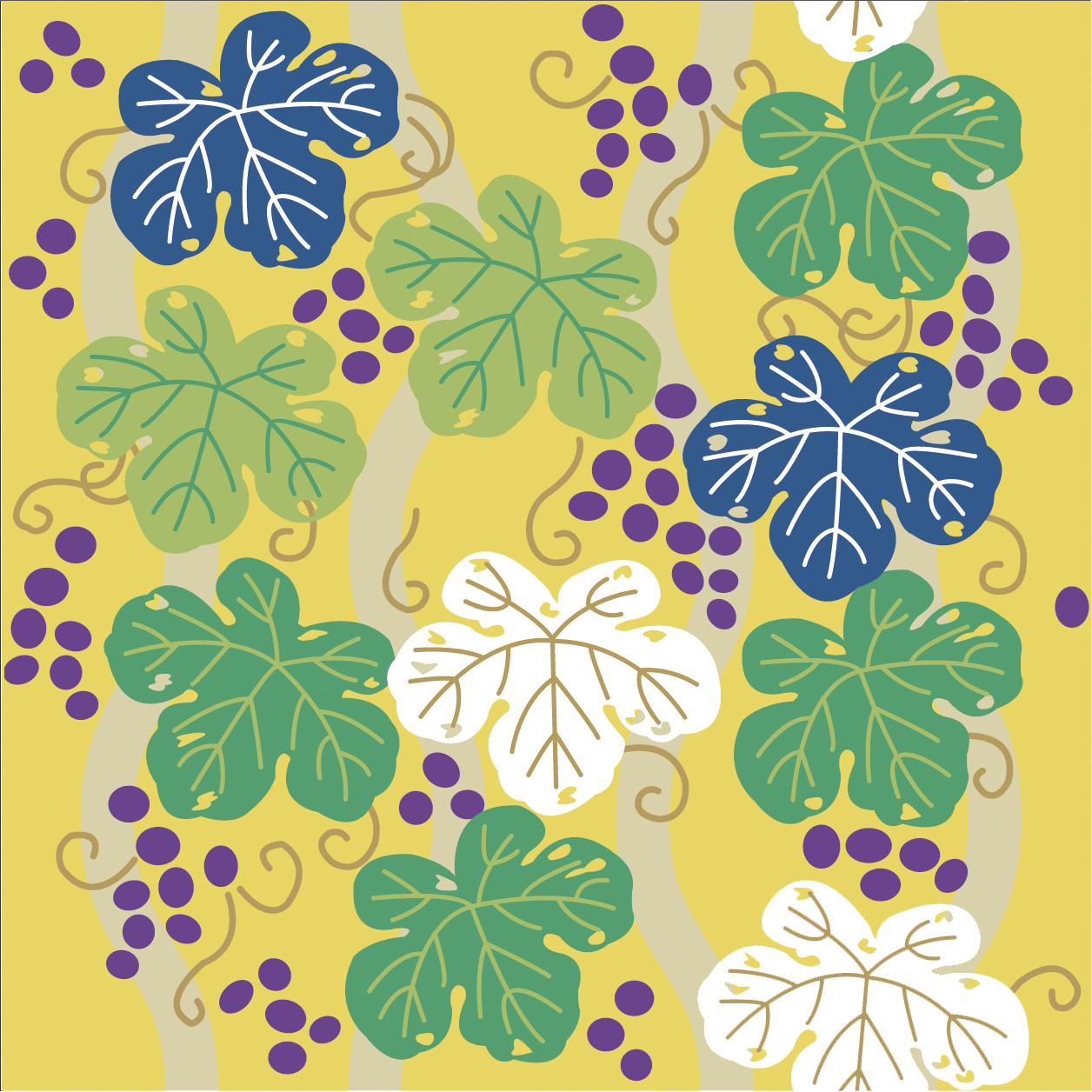
葡萄立涌
立涌の中に葡萄の葉と実が描かれた文様。
葉が虫に食われているところが細かく、実のデフォルメ具合がかわいい。