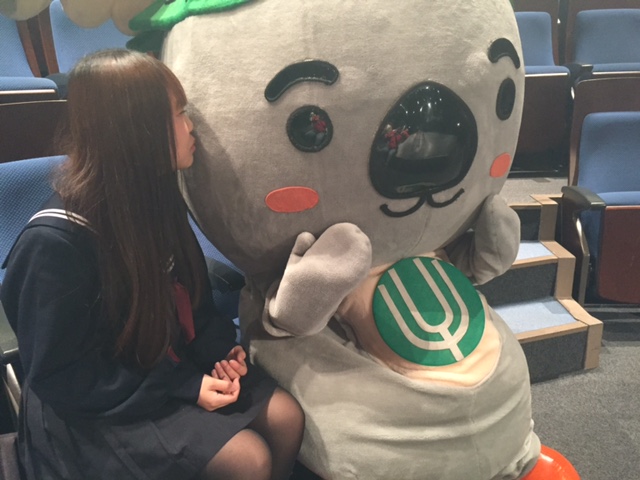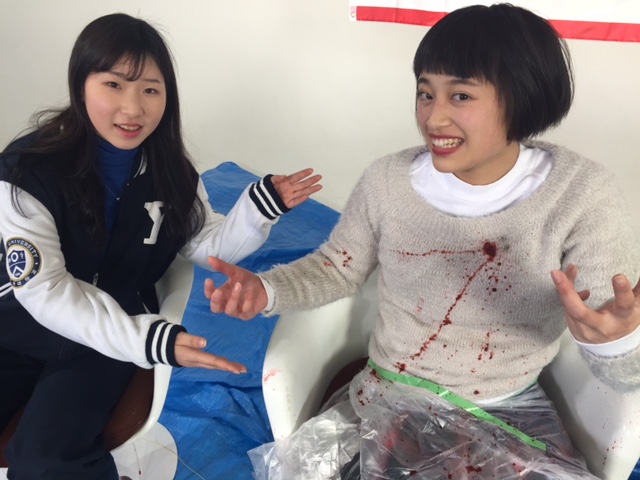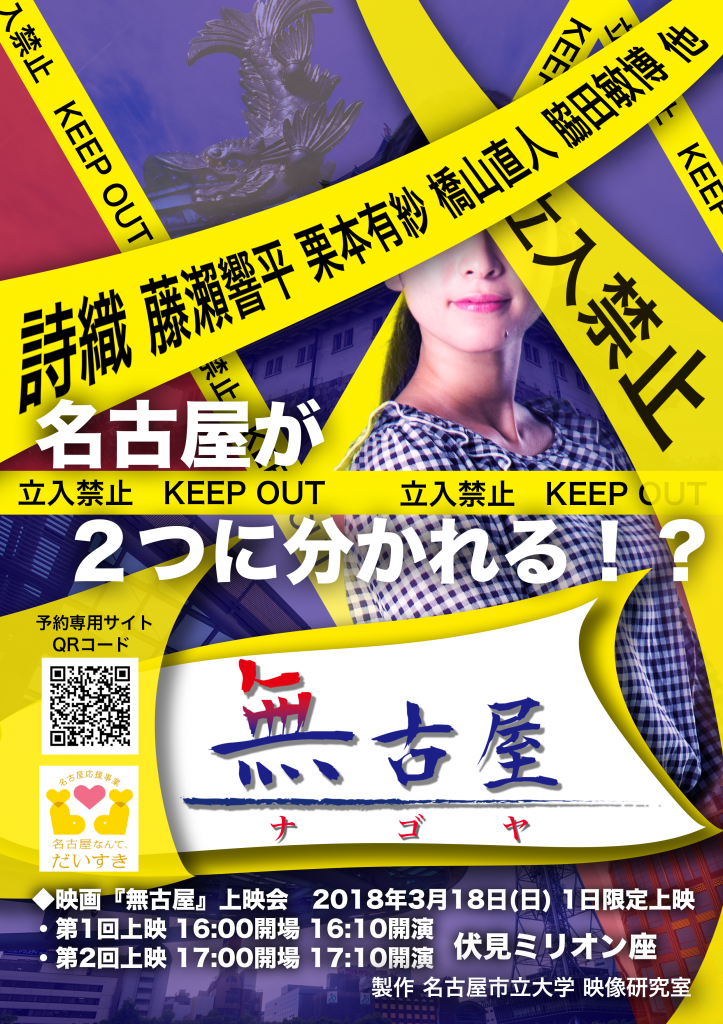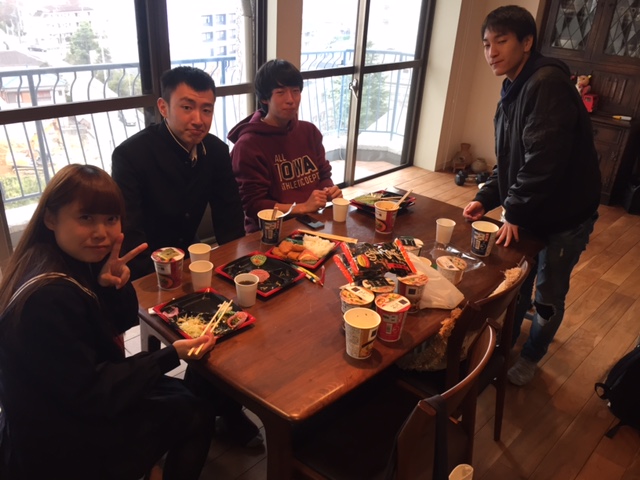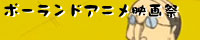講義メモ 2018.1.22
テーマ 「コメディ映画」
「モダンタイムス」 1936年 アメリカ映画 チャーリーチャップリン(監督/主演)
機械文明や徹底的な分業社会や資本主義への風刺をコミカルに描く作品。歯車にまきこまれる場面やネジを締めながら繰り広げられるドタバタが有名。現在に至る多くのコメディの源流。
「ブルースブラザーズ」 1980年 アメリカ 監督ジョンランディス 出演ジョンベルーシ、ダンアイクロイドほか
ミュージカル、コメディ、アクションを融合させた作品。
音楽界の大物である ジェームスブラウン、レイチャールズ、ジョン リー フッカーらを引っ張り出してその映画の世界観に馴染ませたのは画期的。現在でもシカゴをモチーフにした映画を代表する作品のひとつ。
「エース ベンチュラ」 1994年 アメリカ作品
出演 ジムキャリーほか。
新人時代のジムキャリーの代表作。アメリカらしい、徹底的にバカバカしい映画。
冒頭の宅配便業社に扮するジムが荷物を蹴飛ばしながら配達する姿は現代の問題を示唆していたのかも!?
参考上映 「ライアーライアー」ダイジェスト上映とラストのNG集など。
「下妻物語」 2004年 日本映画 監督 中島哲也
その年の数々の映画賞を受賞したコメディ映画。
のちに「嫌われ松子の一生」や「告白」など多くの名作を手掛ける中島監督のジャンピングボードとなった作品。
テンポ良く、スタイリッシュな映像で描かれるギャグが冴える。
日本映画ではなかなか根付かない「コメデイ映画」の近年の代表作のひとつ。
ほか、「バスターキートン大列車追跡」ほか。(学生の発表)また、駅馬車との比較における「MAD MAX2」の追跡戦闘場面
、「ゆきゆきて神軍」のダイジェスト上映と解説。(前回DVDデッキ不調で上映できなかったため)