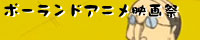一昨日までアメリカに出張でした。BaltimoreのMICAにいきました。
SAIC時代の同窓生のNadiaがコーディネートしてくれて授業を行い ました。(写真の女性。もうひとりは学部長)こちらから持っていた作品では内田君の作品と天野君の作品が好評でした。

こちらの大学はGraduateレベルではArt系スクールのなかで全米三位にランクされています。今年の1位はロードアイランド、二位はSAICでした。
Baltimoreは今回初めて訪問しましたが、ゆったりとした田舎町で大学もアットホームでとてもいい環境ではないかと思います。今後交換留学協定締結にむけて活動していきます。